
三重県の襖(ふすま)の張替えにスピーディーに対応!!


|
|
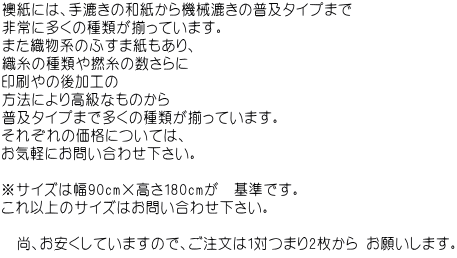
| 無料お見積りはこちら |
■鳥の子襖紙の種類
 |
新鳥の子(普及品)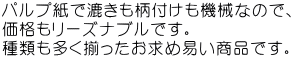
|
 |
上新鳥の子(中級品)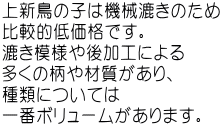
|
 |
鳥の子(高級品)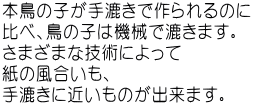 |
 |
手漉き本鳥の子(最高級品)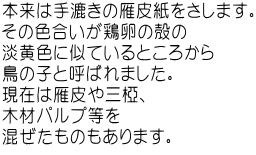
|
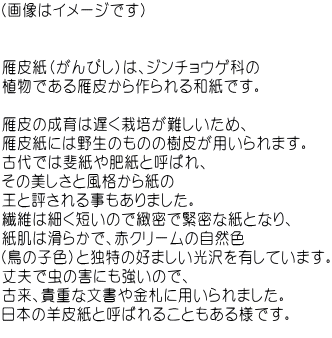
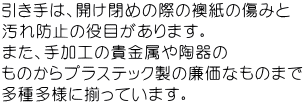
   |
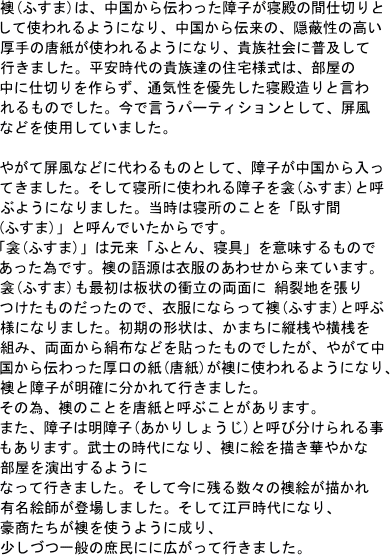
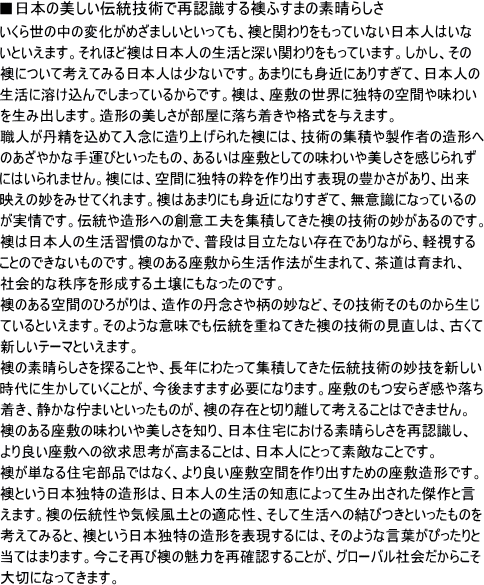
襖の耐久性
紙や織物でできている襖紙は、永年使用しているうちに経年変化として、色の褪せや煤けから、退色が起こります。日に当たるところはより早く褪せていきます。これはやむをえないことで、時代の箔がつくという考え方もありますが、新しい襖紙のすがすがしさは失われてゆきます。インテリア効果としては、材質によって、3年、5年、10年程度で張替のタイミングがくると判断してください。張り替えることで、新品同様になり、これが襖の最大の長所であるといえます。
襖の強度について、ご紹介します。襖には、様々な内部の構造があります。したがってそれぞれの構造により、襖の強度に差が生まれます。例えば、板を構造に使っている襖は、比較的強度が強く、また木の中骨に紙を幾重にも貼った「和襖」であれば、その柔らかな肌合いを楽しめますが、比較的突きや切り裂きには弱いという性質があります。 特に「和襖」をお使いの場合は、襖の表面に家具の角や刃物、鋭利なものがあたらないように気をつけてください。
襖紙の破損(破れ・凹み)防止対策について、ご紹介します。お使いの襖の内部構造がどうなっているかを、日頃から意識しておくことは有益です。ふすまには「和襖」「量産襖」などがあります。 「和襖」は、格子状の骨組みの上に、幾層かの異なる紙が下貼りされていて、その上に襖紙は貼られています。押してみると弾力があり、保湿効果・保温効果・消臭効果などがあります。襖紙の強度にもよりますが、強い突きの力や裂きの衝撃には比較的弱い性質を持っています。体をぶつけても痛くない、やさしい建具ともいえます。
襖の汚れ対策について、ご紹介します。ふすまのシミやカビの多くは、ふすまについた汚れから発生します。カビやシミは、いったん目立つようになると、もう元通りに戻すことはできません。ふすまの汚れについては、毎日のお掃除の時に気をつけておきましょう。 小さなシミなどの汚れは、気にしだすといっそう気になるものです。生活空間を取り巻く日常使いの用具ですから、次第に汚れていくことは、やむをえないものと考えましょう。
日頃のお手入れ法について、ご紹介します。襖を美しく保つコツとして、ハタキなどで埃を払い、汚れをつけた時には、すぐに処置をしましょう。敷居についたゴミや、敷居とふすまの底との間に挟まっているゴミは、竹串や楊枝で取るようにします。縁や引手は、乾拭きしましょう。縁についた傷が目立つ場合には、同色の塗料で補修をしましょう。 なお、新しくふすま紙を貼り変えた時に、引き手まわりに防水スプレーを吹きかけておくと、汚れがつきにくくなり、またついた汚れがふき取りやすくなります。
| 無料お見積りはこちら |
三重県津市について
三重県は、人口1,821千人で県の魚として伊勢海老、県の木は神宮杉、花がハナショウブです。その県庁所在地は、津市です。
三重県の津は歴史的史跡が多く残る地域です。伊勢平野の中心にあり、古くは安濃津として歴史的文献に記されている良港であり、平安京によっては重要な港であったことから単に「津」と呼ばれるようになったという歴史があります。津の歴史には、藤堂高虎が大きく関わりました。津は、津藩藤堂氏の城下町で、歴史をたどれば江戸時代は毎年秋に津まつりが開催されて、現在でも、三重県の無形民俗文化財に登録されている「唐人おどり」などが踊られていました。津城跡は津市の中心部にあり、現在は憩いの場として市民に親しまれています。藤堂高虎が津城に入城すると、下町の整備を行い、伊勢神宮への参詣路「伊勢街道」が慶長13年に城下町に取り入れられたことで、津城の歴史は宿場町としても発展していくことになったのです。藤堂高虎は、近江国犬上郡に生まれ、羽柴秀長に見込まれて、300石で召抱えられると多くの合戦で戦功を挙げ活躍してきた武将です。戦国時代という歴史のなかで功績をあげた藤堂高虎が、津の歴史を大きく変えていくのです。織田信長の弟・信包が伊勢上野城主のときに、安濃津城が築城されました。それから高虎により整備が成されて、明治維新までには32万石の城下町として栄えさせるという津城の華々しい歴史を作り上げていきました。明治時代に入っても、津の街は旧城下町の姿を残していましたが、明治の終わり頃になって、外堀が埋められて、新しい町作りが始まりました。現在では、津城は、本丸、西の丸、内堀の一部を残すのみとなっていますが、角櫓の三層の白壁と松ノ木、苔むす石垣は往時の姿を偲ぶことができる歴史を感じさせる趣ある景観を今も見ることができます。歴史的にみても城下町造成に一躍買った藤堂高虎もまた歴史をつくった偉人として石造が建てられこの地に佇みます。また、津といえば、日本人の心のふるさとともいわれ、1300年以上の歴史を誇る伊勢神宮へも近いことから、神様にまつわる歴史的史跡も多く残っています。伊勢神宮の歴史は、戦国時代で歴史の物語を彩った武将たちの話よりももっと昔に遡ります。津には、津観音や結城神社、北畠神社、高田本山、川上山若宮八幡宮など歴史的にみてもかなり長い歴史を誇る神社が残り、津の人々が神々を崇拝して大切にしてきた歴史を垣間見ることができます。また津には専修寺や寒松院、普門寺などの寺院もあります。これらの寺院は親鸞聖人にまつわる寺があったり、高松高虎公の霊を祀る寺があったりと、歴史的にも価値のある寺院であることが特徴です。