
紀の川市スピーディーに対応します!!




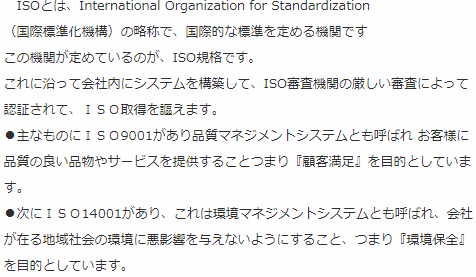
  |
| 無料お見積りはこちら |
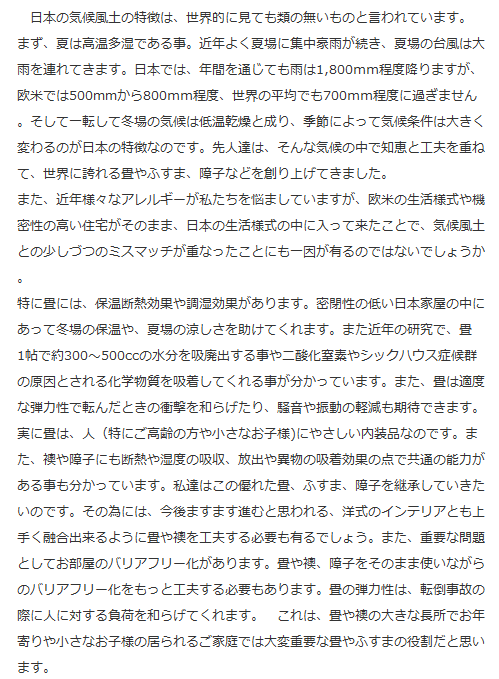
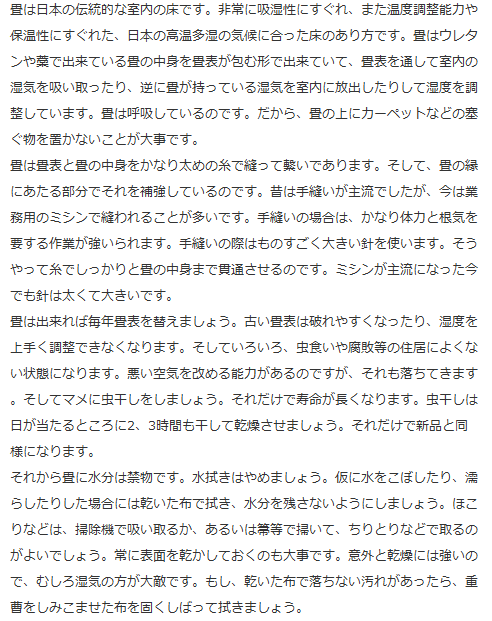
畳の構造
畳の構造は大きく分けて3つから成り立っています。その3つとは「畳表」「畳床」「畳縁」です。畳表はイ草で練り上げられていて、そのイ草の質・長さ・色調によって品質が決まります。イ草は天然の物から現在では変色しにくい人工素材の物まであります。
「畳床」とは土台の事です。土台はワラを細かく縫い上げています。現在ではボードやウレタンフォームなども多くなっており、用途に合わせて使い分けられています。「畳縁」は畳表の保護と共に様々な色柄があり、部屋の雰囲気を引き立たせる事に役立っています。
次は効果です。まずは様々な音の吸収をしてくれます。それは断熱効果があるとともに遮音材としても使用が可能です。また材料のイ草は空気の浄化作用もあります。自然のイ草には空気に発生する揮発性有機化合物の吸着をし、濃度を軽減する効果があります。
またこれらの寿命ですが、表面が変色したりボロボロになった時は交換が必要でしょう。また凹んだり隙間が空いている時もひとつの目安となります。またシミや湿り気からカビが発生してしまう場合もあります。カビは病気の元になる可能性があるので注意が必要です。
畳は四季の変化がはっきしりている日本の風土に非常に適した敷物として、古来から使われています。昔は身分の程度によって仕様が異なり、大きさや厚さ、色によって身分が決められていたようです。日本の家屋を象徴する物の一つとして現在も受け継がれています。
海外でも評価を得ている襖ふすま
襖というのは和室ではどんな機能があるのかというと、押入れや間仕切りに使える道具であり、装飾としては和室だけでなくその家の雰囲気を作っていく重要な道具でもあります。骨組みが木の襖においては、乾燥すると水分を出し、湿度が高い場合には水分を吸うといった機能があります。襖は和紙が何枚も合わさっているため、より効果を発揮していきます。そして、襖にはホルムアルデヒドやタバコの煙を吸うといった効果もあり、断熱効果もあります。温度や湿度の変化が著しい日本の気候にマッチしているため、千年にも渡り進化を続けながら襖は使われてきました。安さを追求した量産品とは違い、縁や紙、そしてヒキテといったパーツにこだわりを見せた襖の耐久性や美しさというのは、日本だけに限らず、海外でも襖の評価を得ています。襖は、実のところ木や竹クギ、そして紙といった天然素材から作られていて、張替えで頻繁に使っていけるといった具合に、リサイクル面でも優れている建具です。それから、今の日本にある住まいの事情においては、建具をはじめ、壁材や天井、そして床材といったものに人工的なオレフィンシートのようなものが多く使われていて、襖というのはあまり見られない天然素材でもあります。
| 無料お見積りはこちら |
紀ノ川は奈良県から和歌山県へと流れていく一級河川です。奈良県では吉野川と言われ和歌山県では紀ノ川と言われています。その紀ノ川には古くからの歴史があります。歴史で有名な万葉集の中には紀伊国を詠ったものが多いのです。大和の国から天皇の紀伊行幸のときに詠われたものです。額田王、柿本人麻呂、山上憶良、山部赤人、大伴家持などの歴史上代表的な詩人の歌です。特に紀ノ川に沿う南海道を歩かれたときの紀ノ川の景観の美しさを詠ったものが多くあります。「紀伊の暖かさは大和とはまた違い、紀ノ川の朝霧に象徴される」というものや紀ノ川の河原の景観を詠ったものなどがあります。このように紀ノ川の景観は古い歴史がある万葉集にも多く残されているのです。紀ノ川流域の用水路の歴史としては、紀ノ川下流の和歌山平野南岸と北岸を潤し、宮井という井堰は古墳時代から用水路として古代紀伊の豪族の紀氏と関連を持っていたという古い歴史があります。六箇井という井堰も古い歴史があります。その後江戸時代、吉宗の時代をピークに12堰の井堰を完成させたという歴史があります。中世の頃の歴史では、紀の国は山名氏、畠山氏らが守護を務めていましたが、高野山や粉河寺など寺社の力が強く織田信長が太田党や根来寺などを討伐したqという歴史がありますが和陸という形で決着をつけました。そして寺社勢力は強いままという歴史があります。その後いくつかの寺社が小牧、長久手の戦いにおいて家康の味方をして羽柴秀吉を的にまわしました。そこで秀吉は弟や甥とともに紀州征伐に乗り出し、太田城を水攻めをしたという歴史があります。太田城の周囲に堤を造り紀ノ川を堰止めて水没させる作戦でした。それは軍事的な河川工作物ですが、初めて紀ノ川を大規模工事したという歴史です。その後の歴史では、紀州藩は和歌山城の拡張と城下の発展のためには紀ノ川の治水が必要であると考え1.7kmの堤防を造りました。その補強のために柳や松も植えられました。そして多くの井堰も建設されたという歴史があるのです。元禄時代には奈良に紀ノ川の水を引けないかという吉野川分水の構想も出ていましたが和歌山県は抵抗しつづけていたという歴史もあります。近代の歴史としては、大正6年に紀ノ川に洪水が起きてから大正12年には内務省の直轄改修対象河川となり「紀ノ川改修計画」が策定されました。それは昭和11年には完成する予定でしたが遅延し太平洋戦争により中断してしまったという歴史があるのです。そして戦後の歴史ですが、奈良県に紀ノ川の水を流すという構想は「十津川・紀ノ川総合開発計画」により本格的に動き出しました。そして紀ノ川と熊野川という二つの紀伊半島の大河を利用した灌漑と水力発電を行う吉野熊野特定地域総合開発計画に発展したという歴史のある紀ノ川です。