
大東市内全域スピード対応!!

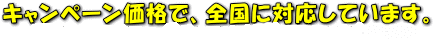



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
夏に網戸は欠かせない
暖かい季節になって、ちょっと窓を開けたほうが気持ち良いなという気候の時には網戸を開けることが多いです。虫がとても苦手なので、窓を開けっぱなしにすることは出来ません。網戸は絶対に欠かせないものです。また、クーラーを付けるにはそこまで暑くないという気候の時、掃除機をかける時などに網戸を使います。夏の季節に網戸は絶対に欠かせないものだと思います。ただ集合住宅に住んでいると、近隣の部屋の網戸の開け閉めが気になる時があります。とても急いでいるのか雑な方なのかわかりませんが、網戸を勢いよくガラガラと開ける音がとても響く時があるのです。自分ももしかしたら気づかず近所の方に迷惑を掛けているかもしれないと思い、網戸の開け閉めにはとても気を使っているほうです。どうしても急いでいる時や無意識の時には勢いよく開けてしまう時があるのですが、その時にハッと思い、網戸を閉める時だけは丁寧にしています。特に窓を開ける季節になると、あちこちから色々なタイミングで響くので自分も十分に注意しなければと思います。網戸は気づくとかなり汚れていることが多く、その汚れ落としにはすごく時間がかかります。ただ網戸は普段の生活に欠かせないものなので、定期的に掃除をするようにしています。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
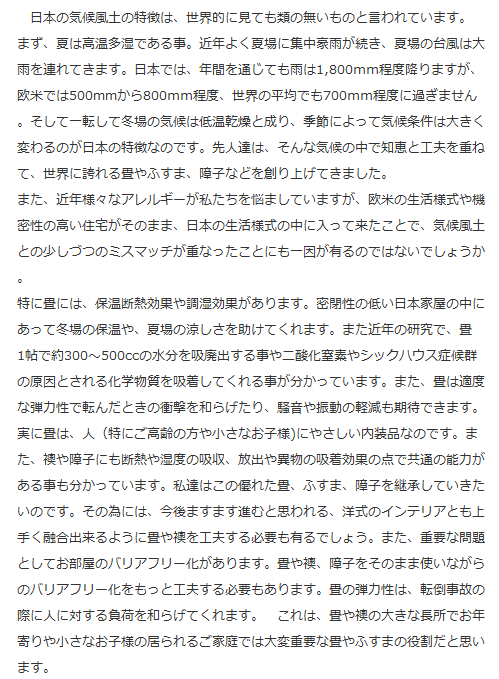
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
カビが生えた畳のお手入れ方法
畳に使われているい草は、とても吸水性に優れている素材です。 しっかりお手入れを行っていればトラブルが起こる事は無いものの、雨が長く続く・長期間にわたり窓を開けないなど換気を怠ってしまうと、吸水性の良さから畳にカビが生えてしまいます。 カビはアレルギーを招くなど健康に悪影響を与えるものなので、もし畳に生えてしまったら、早めに掃除を行い落とす事が大切です。 ただ、お手入れの簡単なフローリングとは違い、畳は間違った掃除をしてしまうと、かえってカビが生えてしまいます。 畳に生えたカビを落とすには、エタノールと霧吹きを用意しましょう。 霧吹きに入れたエタノールを直接、畳に吹きかけて掃除を行います。 エタノールの殺菌効果によって、カビを退治するのです。 この時、シミが心配であれば目立たない部分にエタノールを吹きかけて、様子を見てみる事をおすすめします。 通常、エタノールはすぐに蒸発するので、シミになるという事は少ないようです。 カビが気になるからといって、塗れた雑巾で拭いてしまうと畳に水分を与える事になり、余計に増殖してしまうので注意が必要です。 エタノールを吹きかけた後、畳の目に沿って歯ブラシやたわしでカビをかき出すように掃除します。 この後、乾いた雑巾でから拭きし、掃除機をかければ畳の掃除は完了です。
襖の種類と張替え
襖の下地材には、張替えが容易なものと、そうでないものがあります。
まず前者で代表的なものといえば、本襖や組子襖、チップボ-ル襖です。これらは何度でも張替えが可能で、事前に張替えることを前提としてつけるのには最適な襖です。中でも組子襖は反り返り等にも強いため、季節によって温度や湿度が左右されがちな日本では人気があります。比べて本襖はお値段が高くても高級感を出したい方におすすめ。チップボ-ル襖はリーズナブルに済ませたい方に広く用いられています。
次に張替えにくい襖には、発泡プラスチック襖やダンボール襖が挙げられます。素材が木ではなく、プラスチックやダンボールであるため耐久性に欠けるためです。全くできない訳ではないものの、仕上がりに難が残りやすく、業者によってはこのような襖の張替えを断っているところもあります。ただ本襖等と違い機械による生産が行われるので、安く手に入れることは出来ます。よって破れたり汚れたりしたときには、破棄して襖ごと取り替える方が多いのです。一つの襖を長く楽しむという点では、前者に挙げた襖が適切だと言えます。また洋室との境に使われるベニヤ襖に関しては、頑丈なものの重量がありますので襖を新調される場合は気を付けましょう。
障子の張替えはタイミングも大事
障子の張替えは遥か昔から行われてきていて、古くは江戸時代ぐらいから公の場で障子の製造とか障子紙とかの張替え及び障子本体の張替えとかが行われてきているため、この頃から既に多数の職人が全国的にいたとされています。障子の張替え方法とかは時代がたつにつれ徐々に進化していき今に至るといった感じでありますが、今の障子は昔のものと比べると頑丈でありカビとか汚れ及び変色とか腐りとかもしにくくなるような加工とかがされているため長く使えるようになっています。 障子の張替えとかをしたほうがいいのかどうか悩んでいる場合は一度ですが専門業者に依頼を出してプロの職人の方に来てもらいチェックを受けたりするのがおすすめであり、適切なアドバイスとか提案を受けることによって、障子の状態とか劣化具合などを知ることができ今すぐ張替えが必要なのかもう少し使ってから張替えをしたほうがいいのかの判断がつくので推奨します。 専門業者に依頼を出す時は名が知られていて実績が多数あるところがおすすめとなっていて、こういったところのほうが色々と融通がききますしこちらの要望や意見とかにもしっかりと応えてくれるからであります。障子の張替えをしてもらう際は部屋とかの掃除及び周辺にはなにも置かないように配慮しておくようにお願いします。これは施工を行う際とか新しい障子を運搬する時とかの際に障害物とかになってしまう場合があるからです。 また、地面が汚れていたり滑りやすくなっていたら、職人の方が転倒してしまい怪我とか新しい障子とかを破損させてしまう場合もあるため、依頼を出した方がしっかりと責任をもって部屋の掃除とか整理整頓をしておくようにお願いします。
大東市は人間尊重のまちづくりとつくろうヒューマン新都心大東やいきいき安心のまち大東をテーマに掲げています
大阪府北河内地域に位置しているのが、大東市という土地なのです。 この土地は、京都から高野山までの参詣道である東高野街道の経由地の一つとして、古来より発展してきたのです。 また、江戸時代には治水・新田開発などに関わる商都大阪にとっては重要な後背地になっていた経緯もあります。 縄文時代・弥生時代の大東市付近には、山と河内湖ができ集落が起こって人が住み始めます。 時代がさらにすすむと古墳が造営され、一大荘園が作成されたりして、国の歴史の流れに組み込まされる存在となってくるのです。
平安時代に入ると河内湖はさらに大きな池へと変化を遂げ、その様子は有名な随筆にも記されるようになります。 池が大きくなるにつれさらに人口が増えて集落が大きくなってきます。 現在大東市である付近一帯を含んだ近辺は、古代より水害に見舞われやすい地域ではあったのですが、池が大きくなるにつれ魚介が豊富にとれる上に特産物である蓮があったのです。 このために大東市付近は、古代では皇室の食料を調達するための供御領としての役目を担っていたのです。
現代の大東市付近は戦国時代に入ると、東高野街道を中心としていよいよ重要な一帯となってきます。 数々の城やキリシタンの教会も建設されたこの地域は、戦略上重要な地域として遠くは欧州まで知られるようになるのです。 戦乱の時代が落ち着くと、この一帯に新田開発が始まって農業が安定すると稲作を中心とした菜種や木綿といった作物も安定供給できるほど、生産が増大するのです。 現代では大東市と呼ばれる地域は、天下の台所と呼ばれる大阪を支える重要な位置づけをされることになります。
江戸時代に引き続き、明治・大正時代になっても豊かな農業生産を基盤とした大阪を支える支柱という地位は揺るぎないものがあります。 地元の篤志家により学校も設立され鉄道も開通し、近代化が推し進められていきます。 人口もさらに増加をし、1956年には3万人を超えたのです。 そして、この3万人を超えた年に住道町・四条町・南郷村が合併し大東市が誕生したのです。 大東市という名前の由来は、大阪府の東部であることと大阪市の衛星都市として展望が期待される事を光は東方よりという諺に託したことからです。
大東市は、戦後の高度経済急成長の波にのって、住宅・工場・事業所の進出が著しく人口が増え続けて1975年には、11万人を越す都市となってしまうのです。 しかし急激に増えた人口は、住宅事情や上下水道の不備などの様々な都市問題を引き起こしてしまうのです。 そうした問題を抱えながら、1975年に集中豪雨による河川の反乱を招き未曾有の水害を起こしてしまいます。 その後、この水害を教訓とした水害対策を掲げ官民一体となった積極的なまちづくりをしているのが大東市なのです。
無料お見積りはこちら
|
|
|
大阪桐蔭高校は開校された当初は大阪産業大学高等学校大東校舎という名称でしたが、設立された時点では高校入学希望者の増加時期における臨時的な措置というものでした。大阪産業大学高等学校の分校として一時的に大東市に設立された大東校舎でしたが、その後の卒業生などを含めた学校関係者の強い希望もあって大阪桐蔭高校として独立をすることになり、学校も一時的なものに終わることなく、その後も生徒の募集を行って学校運営がなされていくこととなりました。
分校という位置づけから独立した大阪桐蔭高校はその後進学や部活動に力を入れていくことになります。進学面においては難関国公立大学や難関私立大学を目指すコースがある一方で、活発な部活動の成果によるスポーツ特待制度などを利用した有名大学への進学を目指すコースもあります。大東市の大阪桐蔭高校の名前を日本全国に知らしめているのはこの活発な部活動の影響が大きいと言えます。日本全国で大阪桐蔭高校の名前を聞いたことがないという人はいないでしょう。
大阪桐蔭高校の部活動の中でも日本全国にその名を知られているものとしてまず最初に挙げられるのが硬式野球部です。創部してわずか4年目で春の選抜高等学校野球大会と夏の全国高等学校野球選手権大会に出場し、全国高等学校野球選手権大会では初出場で見事に初優勝を果たし、大阪桐蔭高校の名前を日本全国に知らしめることとなりました。その後も選抜高等学校野球大会の優勝や春夏連覇を達成するなど輝かしい実績を残しています。
また吹奏楽部も大阪桐蔭高校は全国レベルの高い技量を持つ学校として知られています。2005年に創部して早々に出場した関西吹奏楽コンクールにおいて金賞を獲得するというスタートから華々しい成果を挙げることとなりました。その後も全日本吹奏楽コンクールや全日本マーチングコンテストにおいて金賞を連続で獲得するなど、大東市の大阪桐蔭高校の吹奏楽部は創部して10年足らずの間に全国屈指の存在として名を轟かせるに至りました。
サッカー部も全国高等学校総合体育大会でベスト8に進出するなど全国レベルでの活躍を見せています。女子サッカー部は全国大会に出場するなどその実力を着実に伸ばしています。分校として開校した当時に創部されたラグビー部は全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会に優勝した実績もあります。陸上競技部は創部3年目で全国高校駅伝競走大会に出場する活躍をしています。このように様々な部活動において大東市の大阪桐蔭高校の名前は全国に知られています。
大阪はなぜ水の都と呼ばれているのか、その理由とは。
その昔、大阪は海の下に位置していた。海岸線は、平野のほうまで深く入り込んでいた。やがて、淀川が運んできた土砂によって湖ができ、その後新たな陸地ができた。これが、大阪の起源となる難波津である。難波津は、諸国の交易を盛んにし飛鳥時代まで栄えた場所である。その後、古代王朝は奈良や京都に都を移す時代が続き、そのせいで大阪が栄えることはなかった。しかし、海と川に囲まれた天然の要塞に恵まれた大阪に目をつけた武将がいた。それが豊臣秀吉である。海や川を活かして守りの堅固な城を築いた秀吉は、城下町を整備し、治水対策まで力を入れた。堀を掘った土が新しい土地を作り、それが繰り返されて町が整備されていった。整備された町は商人が行き交うようになり、大阪は栄えていった。江戸期までには15本もの堀が作られ、まさに水の都として大阪は成り立っていた。このように、水の都としての大阪は秀吉以降の都市開発も進み、全国一の交易拠点となった。これは北海道や江戸、畿内を結ぶ航路や、川を利用して京都や奈良に結ぶ航路もあったことが一つの要因と考えられる。しかし、水の都として栄えた大阪には水と闘ってきた歴史も忘れることはできない。台風の際の高波は、もともと海の下に位置していた大阪にとって危惧すべき事柄であり、それを避けるためにだんだんと都市を内陸へと移していった。近代に入ってからは、技術が発達してきたのでさまざまな水門を設けることでこれを回避することができるようになった。このように、大阪の人々は川に寄り添い、海を利用して都市として発展させていった。現代になり、都心部を回廊のようにめぐる川をまた利用できないか、と考えるようになった。世界で有名な水の都は、アムステルダムやベネチア、サンアントニオ、バンコク、蘇州などがあるが、都心部が川で囲まれた都市は大阪しかない。また、都市面積の10パーセントが水面という大阪は、やはり水の都といえるだろう。そこで、水の都、大阪の名を再び世に広めるために、様々なプロジェクトが開始された。水辺にシンボルを作り、さまざまな建築物のライトアップを目玉にし、また、船による観光などにも力を入れた。特に、水上バスやクルーズは人気を博し、多くの観光客が訪れるようになった。その結果、また大阪は水の都として世間に知られるようになった。昔から現在まで、大阪は水に寄り添い発展を遂げてきた。これからも水路を利用し、よりよい発展を目指している大阪。これが、大阪が水の都と呼ばれる所以である。
観光スポットやファミレスがたくさんある大東市
大東市には、飲食店がたくさんあります。その中でも、ファミリーレストランの店舗数は、大阪市でナンバーワンです。大東市では、深夜遅くまで営業している店舗が多いです。大東市には、市内を流れる大きな河川があります。河川の両岸には、防水壁が設けられています。洪水や氾濫を防ぐための知恵であり、緊急時には水害を食い止めることができるのです。大東市は、下水道復旧率が低い傾向にある地域です。そのため、水洗式のトイレが普及していない家庭も見られます。市内では、定期的にバキュームカーが巡回しており、廃棄物の処理を行っています。大東市には、数々のボウリング場があります。学生にお得なサービスを提供しており、証明書を提示すると割引価格でプレーすることができます。ボウリング以外にも、卓球コーナーや漫画コーナーが併設されています。難波や梅田へのアクセスが便利なことも、大東市の強みです。大東市から大阪の市街地にかけて、直通のバスが運行しています。大東市には、歌謡曲のテーマとなっている区域があります。誰もが聴いたことのある名曲で、現地にはモニュメントが建てられています。町内の商店街やスーパーでは、名曲のメロディーが流れています。
大東市には色々な観光スポットが点在しています。 一つ目が慈眼寺です。この観光地は大東市で有名な禅宗の寺院で、1300年前に行儀が今の大東市の地で観音像を安置したのを始まりとしています。創建当時の建物は戦乱により焼失しましたが、江戸時代に復興され今に至っています。また境内から飯盛山に通ずる登山道が通じており、休日は大東市民の観光客が訪れています。イベントとして行われる野崎参りは人形浄瑠璃などのフィクション作品の舞台となっています。 二つ目が深北緑地です。この公園は特徴として深野池を中心とした水辺ゾーンがあります。この空間は大東市民の自然観察や環境学習の場として、「かんきょうふれあいワークショップ」が開催されます。公園内にある波の広場ではローラースケートで遊べるところもあります。また、災害の時には地震や災害から守る広域避難地として機能しています。 三つ目として大東市立歴史民俗資料館です。この観光地は大東市の歴史と文化遺産に関する資料を展示しており、2012年に大東市歴史とスポーツふれあいセンター内に完成しました。この博物館には常設展示品として、北新町遺跡から出土した土器や勾玉などがあります。 このように大東市にはユニークな観光スポットが点在しているのです。
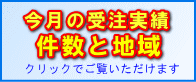
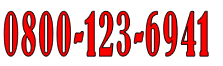
![]()

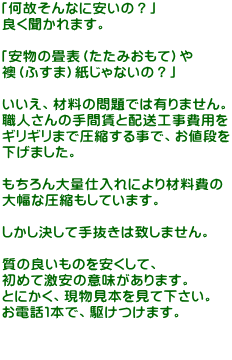
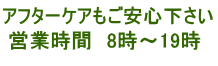
大東市迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
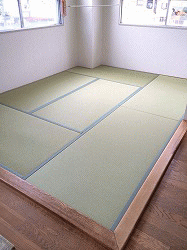
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
日本には独自の文化が沢山存在します。それらの文化は全て日本人が長い歴史の中でつくりあげてきたものです。日本の文化の発端は今から9千年程前にまでさかのぼります。当時に始まった農耕の文化が日本での最初の文化と言われています。自給自足で生活していたことが基本だったので、自分たちで畑を耕して狩りを行なう必要があったのです。これらの生活の中でも欠かせないのが住宅です。住宅は人間が雨や風を凌ぐ場所でもあり、外敵から身を守る場所としてつくられました。現在では住宅は当時と同様に人の手でつくられており、安らぎや癒しを与えてくれる場所として活躍しています。特に日本家屋には日本人が考案した工夫が沢山存在していて、それらを存分に利用して暮らしてきたのです。その工夫の中に襖があります。襖は木の枠でつくられたものに紙や布を貼って引き手をつけたものです。和室を仕切る時に使われる道具として有名です。現在は日本家屋自体が減少しているので、襖を見る機会も減りましたが、それでも襖は日本文化の特徴として残っています。襖の便利な所は木枠さえ損傷しなければ業者に簡単に張り替えを依頼することが可能です。襖の特徴はこのように張り替えさえ行なえば、長く使用できるところです。襖の張り替えは自分で行なうよりも業者に依頼した方が確実で、より長持ちするように施してくれます。