
全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

土岐市全域にスピーディーに対応します!!




  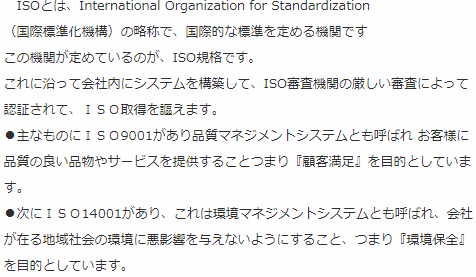 |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます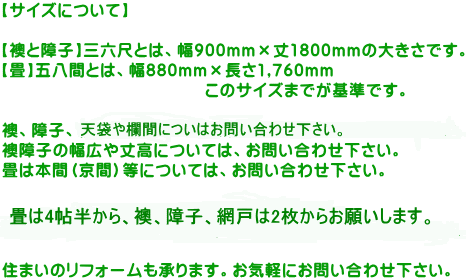
| 無料お見積りはこちら |
子供の頃から真冬に、こたつに入っているのが大好きで、どんなに寒くてもストーブは使わず、コタツだけで、暖を取るのが大好きです。最近は、若い方がフローリングにこたつをすることが増えているみたいです。ですが、コタツと言ったら畳だと思うのです。特に掘りごたつは最高で、出かけるのが嫌になるほどです。一度、仕事の出張でヨーロッパに行くことがあったのですが、とにかく寒くて、一緒に行った人は日本食が恋しいということでしたが、自分は、食べ物よりも、畳とこたつが恋しかったです。日本人はやはり畳だと思います。畳は、日本で利用されている伝統的な床材です。芯材になる板状の表面をい草の編み込んでできた敷物状の畳表でくるんで作るのです。縁には畳表を止めるためと、装飾を兼ねて、畳べりと呼ばれる帯状の布を縫い付けるのが一般的です。また、琉球畳に代表されるものでは、縁のなものもあります。畳には、縦横比が、2:1になっている長方形の1畳サイズと、これを半分にした正方形の半状サイズの2種類があります。一般的な企画としては、本間、中京間、江戸間、団地間の4種類が有名でありますが、このほかにも地域ごとに様々な企画が存在しています。
畳とは日本で利用される伝統的な床材です。日本人で知らない人はいないほど身近にある床材です。畳は芯となる板状の床の表面に、い草を編み込んでできた敷物状畳表をくるんで作ります。また縁には帯状の布を縫いつけます。このおような畳ですが実は、地域や建物によってサイズが異なります。大きく分けると5つのサイズに分類することが出来ます。サイズについては以前は尺や寸で表すことが多かったですが、最近は分かりやすいようにcmで表すことも多くなりました。まず京都や関西地方を中心に使われているのが、京間或いは本間と呼ばれているものです。サイズは191cm×95.5cmとなっています。また岡山や広島や山口を中心に使われているのが、六一間と呼ばれているものです。サイズは185cm×92.5cmとなっています。続いて中京間と呼ばれる畳が、名古屋を中心とした中京地方及び東北や北陸地方などで用いらえています。サイズは182cm×91cmとなっています。更に江戸間と呼ばれる畳が東京をはじめとして関東地方や全国で用いられています。サイズは176cm×88cmとなっています。最後に団地間がアパートや団地などで用いられサイズは170cm×85cmとなっています。このように地域でサイズが違うのは家の作り方に由来しているようです。またどの畳もサイズは違えど、2対1となっているのは変わりありません。
襖は基本構造となる部分が木で出来ているのでこれらが劣化する事は稀であり、大抵の場合において早く痛むのは和紙等が用いられた絵柄が施された部分ともなって来ます。これらは襖紙とも言われていて劣化したら張替えない限りは傷む一方なので、必然的に古い物を剥がした上で新しい物に変えると言った作業をどうしてもやる必要があるのです。しかしこの時に迂闊な手段を取ってしまえば再度剥がれたり破れると言った状態となり、下手をすれば木製の材質まで傷つける事もあるので十分に気を付ける様にします。木の方に何かしらの問題が及ぶと下手をすれば完全に取り替えないと問題が片付かないか、修復するにしても襖紙の交換費用とは桁が違って来るので甘く見ない様にするべきです。一番良いのはやはり襖の張替え等を専門的に扱っている業者に任せる事であり、これらは知識や経験ばかりではなく高い技術や専用の工具まで揃えているので問題なく行ってくれます。襖はその種類によっては構造的に繊細な物もあるので張替え方法に専門性を要する事もありますが、専門業ならばその様な点も難なく扱うので安心できるのです。しかも使う事を考えて確実に作業を行うので設置後の不具合に関しても特に問題とは成らず、見た目と実用性を両立した上で長く維持出来る事も可能となります。
網戸の張替えは使用している網戸の状態が良い時に専門業者にお願いを出したほうが施工にかかる費用も安く済ますことができるため、覚えておいて欲しいところであります。
ある程度ですが網戸の状態が良い時に依頼を出せば使用しているものをそのまま使って対応を受けることができ、新しい網戸を買わなくてもすむからであります。
張替えとかの方法は使用している網戸の状態によって決まってくるため、ここは心得ておいて欲しい部分となっていて、状態が悪くなってしまった場合は新しいものに交換することになるため、新品の網戸とかを購入してから張替え対応を受けることになります。
新しい網戸も価格がある程度してくるので、出費も増えてしまうため、張替えの対応を受けるタイミングとしては使用している網戸の状態がある程度よい時に出したほうが得策なのであります。
依頼を出すところも専門業者とかになりますが、業者選びも大事であり、有名かつ優良な専門業者であれば安心してサービスを受けることができつつ、張替えが完了した後も定期的なメンテナンスサポートも受けることができるので、メリットはあったりします。
使ってる網戸がまだ良い状態だけど、張替えとかの対応は受けたほうが良いのかどうか迷っている場合は専門業者に問い合わせを行い相談してみることを推奨します。
一度ですが、専門スタッフや職人の方に来てもらい使用している網戸のチェックを受け、適切なアドバイスや提案を受けたりすると更に安心できます。
網戸は多くのところで使われているものとなっていて、張替えに関しては全国各地で行われているため、今も多くの人達が専門業者や工務店などに依頼を出し対応を受けている状態となっています。
昔と比べると今の網戸は頑丈かつ耐性が強いものが多いため、張替えとかなどの対応を受ける回数はある程度ですが減っているけど、長く使っていれば網戸は劣化をしていき、破損部分が目立ちはじめるため、張替えの対応が必要となってきます。
網戸の張替えに関しては専門業者や工務店などのところに頼むのが当たり前となっていて、適切な判断を行うことができつつ、依頼者が使う網戸の状態によって無難に施工ができるのは専門業者とか工務店となっています。
ちなみにですが網戸の張替えに関しては依頼を出すところによって料金に差が出てきたり、ある程度だけど、安くなる場合もあるため、ここはしっかりと把握をしておきたい部分です。依頼を出すところとかが分かっている場合はインターネットを使って良し悪しを確認しておいたり、これから依頼を出すところを決める場合は自分にとってメリットがある専門業者や工務店を決めていかないといけないので、情報収集はしっかりとしておく必要があります。
これは豆知識だけど網戸というのはそもそも、遥か昔からありましたが、形状とかは異なり、利用する用途とかも異なっていたため、今のものと比べると使う頻度は少なかったですが、歴史がたつにつれどんどんと今のようなものとかに近づき、現在使ってるような網戸が登場したのは昭和30年頃と言われております。
| 無料お見積りはこちら |
岐阜県土岐市は県の南東部に位置し人口約58000人総面積116km2の市。ここは昭和30年土岐津・下石・妻木・鶴里・曾木・駄知・肥田・泉の8町村が合併して発足した。それらの各町は陶磁器の生産業によって財政を支えてきたところである。
南の山麗に源を発する2筋の流れが市の中央と東部を北流して東から流れる土岐川に合流している。この流れと付近一帯に無尽蔵に埋蔵する地下資源とによりこの地方の製陶が古くから盛んで、その歴史は古く3000年も以前に遡る。ここでは縄文式土器をはじめ弥生式、また古墳時代に於ける土師器から平安時代の須恵器と各時代にわたって連綿と焼き継がれてきた奈良時代に入ると僧行基の伝えたと言われる行基焼や手ロクロの発明によって生産工程も変革を遂げ、大量生産が可能になった。行基焼とは俗に山茶碗と言い鉢や皿などを10数段重ねて焼く手法が使われて、当時としては先進的なものであった。たがて安土桃山時代になると茶道が完成され陶器も茶碗の時期に入るがこの時代には加籐景延の東濃移住により伝えられた中国の新しい製陶技術の道入と相まって志野・織部等と言われる幽玄な作品が生み出されるようになり、陶芸史上非常に重要な時期を開いた。こうした長い歴史と伝統に支えられ土岐市は今も窯業一筋で支えられて花器・茶器などが生産され、多治見市・瑞浪市・笠原地区でえ生産されるものと共に美野焼と呼ばれ伝統工芸品に指定されている。
(乙塚古墳)
土岐市駅の北約1km程のところにある直径約18m、高さ7mの円墳。花崗岩で横穴式の石室があり奥壁まで13mある。古墳時代後期の東濃地方に良くみられる横穴式石室の特徴よく留めている。昭和13年に国の史跡に指定されている。
(久尻元屋敷窯跡)
乙塚古墳の西約500mのところにある美野焼の代表的な古窯跡。小川に面する傾斜地を利用した14mの連房を持つ幅3m長さ30mの登窯跡。陶工加藤景延が初めて織部焼を焼いたところと言われている。景延は、天正2年(1574年)に尾張からきて、久尻窯を開いて今日の美野焼の基礎を築いた加藤景光の長男。景延は古田織部正重然が指導する唐津・備前の進んだ製陶方を学び、美野焼をさらに発展させた。景延が織田信長に美野焼の茶器を献上し朱印を受けたのはよく知られている。
また県内各地に温泉があり、柿の温泉・曾木温泉・山神温泉などが知られていて古い歴史を持っている。
(美濃の壺石)
第三紀鮮新層の中に含まれる結粒の一種。珪岩・角岩などが鉄分を含む珪質粘土層の中にくっついたもの。内部は空で砂が詰まっている。砂を出すとちょうど壺のように成る所から壷石の名がある。学術上貴重なもので、昭和9年、国の天然記念物に指定されている。