
藤井寺市内全域スピード対応!!

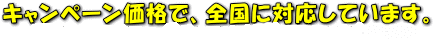



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |
(画像はイメージです)
季節ごとに網戸を掃除したほうが、部屋の中に入ってくる日光の量も異なりますし、網戸の機能を高めることにつながります。とはいえ、網戸を外して洗うのは手間がかかる場合や、集合住宅の場合には外しても洗うスペースがないことも珍しくありません。そこで、手間がかからず網戸掃除ができる方法を学んでおきましょう。ちょっとしたコツをつかむと簡単に掃除ができるので、事前に正しい方法を学んでください。簡単に手入れする方法の一つとして挙げられているのが、軍手を使う方法です。軍手を使って掃除する場合、軍手をはめる前にビニールの手袋をして、その上から軍手を使いましょう。水にぬらした軍手を手にはめ、網戸を両側からこすることで、簡単に掃除ができます。取り外さなくても簡単にきれいになりますが、場所によっては危険なので他の方法を試してください。事前に箒やブラシを使って目立つ土ぼこりを取り、スポンジや市販の吸着シートを使ってこすると、網戸がきれいになります。頑固な汚れは中性洗剤を市販の食器洗い用スポンジに含ませてこすりながら落とすと、簡単に落ちることが少なくありません。網戸に洗剤が残らないよう、網戸を塗れた雑巾で拭いておくと、取り外さずにきれいになります。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
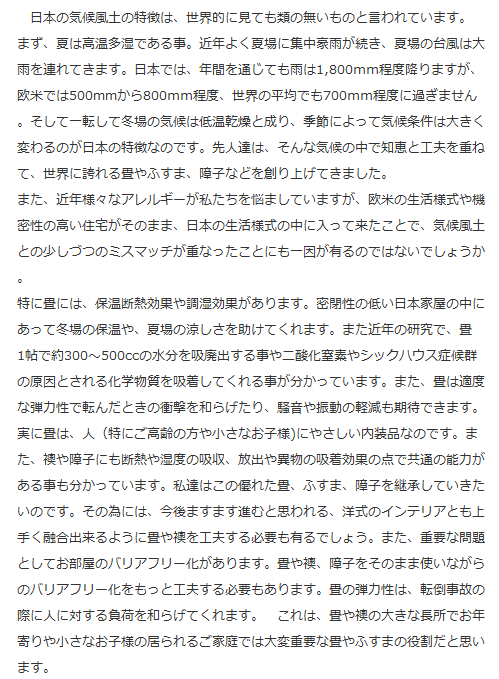
この国で畳が浸透していった背景
過去を振り返ると様々な変化が起こっています。その中でも重要なのが家具の進化に関わるものです。特に和室で使う道具も歴史の中で性能が向上しています。実際に畳も過去と比べると使いやすくなっています。その背景には技術の進歩があるので見逃せない部分です。また最新の技術を知っていると畳も選びやすくなります。この国では古い道具を大事に扱う習慣があります。畳も大切にされている道具の中に含まれています。実際に畳はこの国の家の中に残っている確率が高い道具です。それは昔から畳が使用されている現実を示しています。この畳は性能や見た目が優れているので、以前から人間たちに使用されているのです。現実を見ると優れた家具は家の中で使われています。畳も様々な家庭の中で高度な機能を発揮しています。また古くなった畳は素早く交換ができるので便利です。この機能は畳が人気を維持している理由にもなっています。つまり何度でもメンテナンスできる畳は極めてお得な道具なのです。この国では人気を持った家具が残るという特徴があります。近年の畳は様々な人間が支持しているので、常に衰えない人気を得ています。そういった現実がこの道具の価値や魅力を浸透させているのです。
和風コーディネートをするなら畳は必需品
畳というのは部屋に敷き詰めるだけで一気に和室になるすぐれ物インテリアアイテムです。部屋を和風にコーディネートする際に畳は必要不可欠な物です。ただ畳は本格的な物を使うとなると部屋の寸法合わせなどもきちんと行わないといけないので少し大変ですし、本格的な物をこしらえるとなるとプロなども雇う必要もあります。六畳ぐらいの部屋なら畳柄のカーペットなども使えるので、一人暮らしならカーペットで十分です。わびさび系の部屋にコーディネートするなら色のトーンはディープトーンあたりでまとめると和の雰囲気と合います。ディープトーンとは深い、濃いなどの意味を持った色のトーンで色彩用語です。基本的にわびさびはネイビーとかの深い色など特に相性がよくわびさびでコーディネートするならかなり使えます。なおかつ障子などある部屋だと一気にわびさびっぽくなります。畳は基本、ちょっと薄い緑が多いので、濃い系の色がとっても合います。他にも畳で合うコーディネートアイテムとして、デザイナーズ系の机などを書斎机として置くのもおすすめです。畳は置くだけで一気にわびさびになるので、部屋を和風のコーディネートにするなら畳は絶対に必要になるアイテムです。
歴史ある襖は張替えをする際はプロの職人に任せましょう
襖は歴史と文化があるものとなっていて、今も住まいで使われているものであり住まいを象徴するものでもあるため、多くの人に親しまれてきております。そんな襖ですが、張替えも深い関わりがあり江戸時代ぐらいの頃からの付き合いとなるため、張替えと襖は親密な関係のなかで幾多の時代を生き抜いてきていて、江戸時代ぐらいの頃から襖を作りつつ、修理とかをしたり張替えをする職人が多くいたとされているため、関わりがかなりあったりします。
襖が使われはじめたのが鎌倉時代ぐらいとなっていて、その頃から張替えとかはあったのかどうかはまだ明確な情報が明らかにされていないため、気になるところではありますが、この頃はまだ襖というものは上流階級の人たちとか貴族や武家、公家のみ保有できるものとなっていたため、一般的には知られていないものであり、一部の屋敷とか城内のなかで使われていたためひっそりと使われていたのであります。
襖が多くのところで使われはじめたのが室町時代よりあとの群雄割拠の時代とか安土桃山時代、戦国時代、江戸時代となっていて時代が経つにつれ徐々に一般的な家庭でも使われはじめたという感じであります。張替えとかも江戸時代ぐらいから色々なところで行われていたため、情報が明確となっているのであります。
ちなみに襖の張替えとかを頼みたい時は豊富な実績を持つところがおすすめとなっていて、そういったところには優秀な職人が多くいたりするため、無難に対応を受けることができこちらの意見とか要望にも応えてくれるのであります。張替えを行うタイミングとしては襖を使いだしてから10年ぐらいがめどになっています。
障子の張替え修理は低コストでダイソーで行うことができる!
じぶんは現在でありますが34歳の男性会社員をおこなっております。じぶんは先月でありますが、実家の障子の張替え修理をおこないました。障子の張替え修理でありますが、一見に聞くとかなりの費用が掛かるようなイメージがあるかと思いますが、コツなどをつかむことができれば、100均の商品だけで障子の張替え修理をおこなうことができます。まず水のりをダイソーで用意をして、活用をすることによって簡単に綺麗に古い障子をとりはがすことができます。つぎに障子のりという商品を活用して障子の骨組みのほうに塗布をおこなっていきます。次に新しい障子を用意をして、洗濯ばさみなどで新しい障子紙を端に固定をしてスクロールをしながら貼り付けていきます。貼り付けた後でありますが、余白の部分をカッターナイフを活用して簡単に除去をおこなうことができます。後は障子紙が乾燥をするまで待つのですが、ドライヤーなどを活用すれば、乾かす時間なども時間短縮をすることができます。後は障子を元の場所に復位をすれば張替え修理は完了となります。これらすべての材料をダイソーで購入をすることで障子の張替え修理にかかるコストをかなり低コストで抑えることができます!
網戸を外さず掃除する方法
春になると閉め切っていた窓を開けて、部屋に風を入れる事が多くなります。そこで活躍するのが網戸です。日本では蚊が沢山いるので、網戸がないと蚊が部屋に入ってしまい大変な事になってしまいます。しかし気になるのが汚れです。砂埃やキッチンから流れてくる油汚れ、タバコを吸う家庭ではヤニ汚れなど網戸はかなり汚れています。しかし網戸を取り外して洗うのは大変な作業です。そこで網戸を外さずに掃除出来る方法を紹介します。重曹とメラミンスポンジを使って掃除します。重曹は様々な掃除に使えますが、網戸掃除でも使えるのです。まずスプレーボトルを用意します。これは、100円ショップなどに売っています。その中にぬるま湯を200cc入れます。そして重曹を小さじ1杯入れて混ぜておきます。メラミンスポンジは、研磨力に優れた白いスポンジです。これも100円ショップやドラッグストアなどで購入出来ます。床が汚れるので、網戸の下に新聞紙を敷いておきましょう。網戸に、作った重曹水をスプレーしていきます。しばらく置いたら、メラミンスポンジに水をつけ絞り、上から下に拭いていきます。メラミンスポンジが汚れたら新しい物に取り換えましょう。これで乾くと綺麗な網戸になります。
| 無料お見積りはこちら |
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
多くの古墳群がある藤井寺市の紹介
藤井寺市は大阪府南河内地方にあります。藤井寺市と隣接する自治体は柏原市と羽曳野市と松原市と八尾市です。藤井寺市の地理を説明すると大阪平野の南東部の大和川と石川の合流点にあり平坦な土地が特徴です。藤井寺市の名前の由来は市内に残る葛井寺からと言われています。古来より堺と奈良を結ぶ長尾街道や竹内街道や高野山へ向かう東高野街道が通じ交通の要衝として発達します。現在の藤井寺市は大阪都心部のベッドタウンとして発展し南河内地方では人口密集地として住宅開発が盛んです。次に藤井寺市のおすすめスポットや魅力について紹介致します。まず紹介するのは古市古墳群です。藤井寺市は古墳の密集地として知られていて古市古墳群には誉田御廟山古墳など数多くの古墳が残され歴史ファンに人気のあるスポットです。次に紹介する藤井寺市のおすすめスポットは道明寺天満宮です。祭神は菅原道真と天穂日命です。学問の神として信仰を集め古くから多くの人から親しまれています。国宝や重要文化財を含め多くの文化財が保存されています。また梅の名所として知られていてシーズンには多くの観光客で賑わいます。次に紹介するのは春日山団地です。敷地内に藤井寺教材園があり様々な施設があり豊かな自然が残されコナラやアカマツの大木もあります。老朽化から建て替え工事も進められているなか再利用や保存もされています。
お客様の疑問にお答えします
「何故そんなに安いの?」
良く聞かれます。
「安物の畳表(たたみおもて)や
襖(ふすま)紙じゃないの?」
いいえ、材料の問題では有りません。職人さんの手間賃と配送工事費用をギリギリまで圧縮する事で、値段は下がるのです。もちろん大量仕入れにより材料費の大幅な圧縮もしています。しかし決して手抜きは致しません。質の良いものを安くして、初めて激安価格の意味があります。
とにかく、現物見本を見て下さい。
藤井寺市全域にお伺い致します。
アフターケアもご安心下さい
【年中無休・受付時間】
8時~19時まで