
全国の提携店とのネットワークで、全国にお伺い致します。
石川県全域にスピーディーに対応します!!




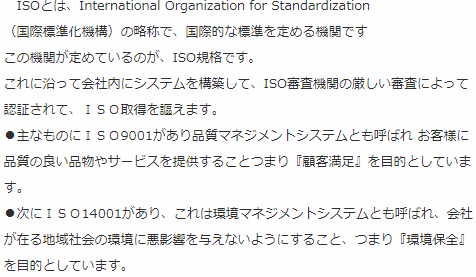
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)


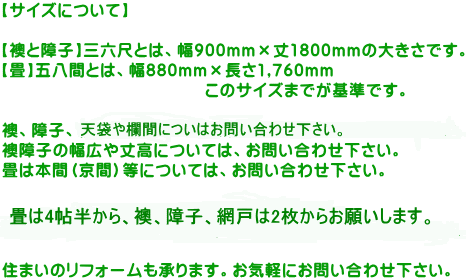
| 無料お見積りはこちら |
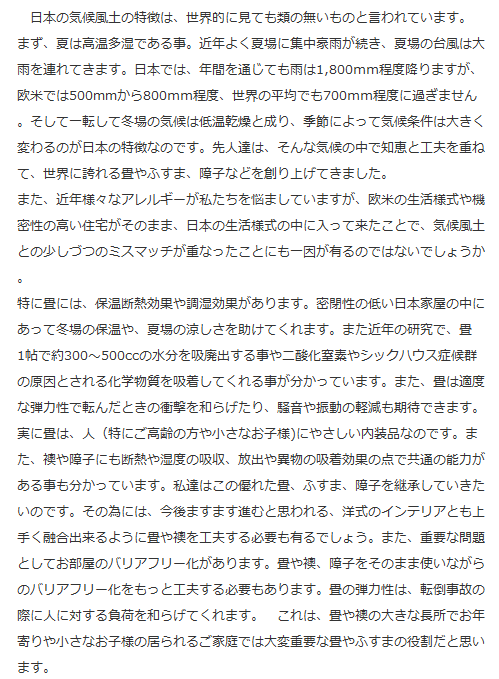
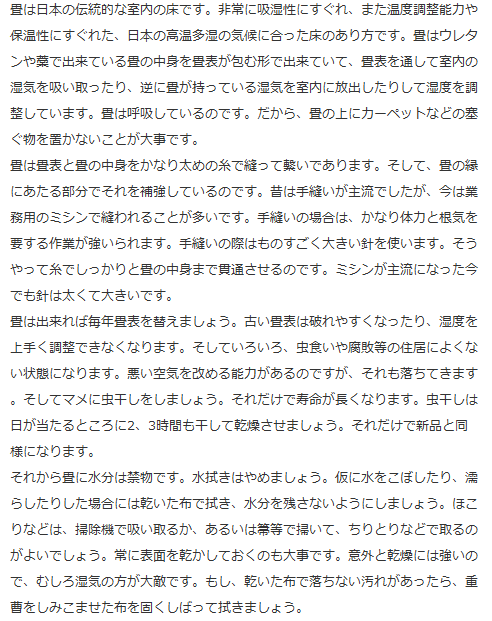
| 無料お見積りはこちら |
石川県の産業
石川県の基幹工業は繊維工業と機械工業のニつで、しかも近代工業と伝統工業が並存して発展している点に特色がある。繊維工業は、絹・人絹織物と、近年著しい発展を示している合成織物で主体をなし、隣りの石川県とともにわが国でも屈指の広域工業地帯を形成している。主な生産地は、金沢・小松・加賀の各氏と羽咋市を中心とする隣接各町で、金沢の加賀友禅、小松の小松綸子、加賀の羽二重、羽咋の能登上布などは全国にその名が知られている。また特色の一つは、小幅織物が少なく輸出用の広幅織物を主としていることで、とくに長繊維織物では全国一の生産量誇っている。機械工業は、繊維機械・建設機械・輸送用機械の製造が盛んで、主に加賀地方に工業郡立地している。なかでも小松市にあるコマツ製作所は有名で、ブルドーザーの生産量では世界第2位を誇り、ほかにパワーショベル・トラクター等の建設機械、大型プレス・小松マイプレスなどの産業機械を生産している。また、繊維機械の製造は、繊維工業と密接な関連を持って発達したもので、市場占拠率は全国の90パーセント強を占めている。しかし、全体的に見ると経営規模が小さく、中小、あるいは零細企業が多い。本県は、わが国でも京都と並んで伝統産業の盛んな土地柄である。全国的に著名なものばかりであるが、例えば、金沢の九谷焼・大樋焼・加賀蒔絵・象嵌・金箔・輪島の輪島塗、山中の山中塗などがあり多彩を極めている。いずれも藩政時代に盛んになったもので、古い伝統のままに行われており、現在でもその生産構造にはそれほどの変化が見られない。なかでも輪島・山中塗等の漆器の生産量は全国第1位で、金箔は全国生産額の約95.5パーセントを占めている。石川県の鉱業として、主要なものに非鉄金属の陶土と珪藻土がある。本県はどちらかというと地下資源に乏しい県であるが、陶土と珪藻土の埋蔵量は無尽蔵と言われている。陶土は九谷焼の原料で、本県の窯業盛大さをうらづける資源となっており、また、衛生陶器・硬質陶器の原料として県外にも大量に移出されている。小松市・辰口町・鳥越村などが主な生産地である。一方珪藻土は七尾市と珠洲市で量産され、レンガ・カワラ・コンロ・カマド等の原料として利用されている。なかでも七尾市のコンロは、全国トップの生産量を占めておりは、羽咋市の珪藻土は、切り出し珪藻土、としてその名が知られている。藩政時代以来、米どころとして知られた石川県は、今でも稲作を中心とした農業県である。北陸農政局の昭和60年の調査によると、県全体の農家数は5万7,050戸、内訳は専業農家3,370戸、兼業農家が5万3,748戸となっており、全国的な傾向にみられるように農家の兼業化が著しい。また総耕地面積4万7,620ヘクタールのうち、田4万115ヘクタール、普通畑5,891ヘクタール、樹園地1,617ヘクタールとなっている。米の主要生産地は、加賀地方の金沢平野である。金沢平野は、水田農業として日本で最も進んだ平野の一つで、大々的に機械力も導入され、耕地も整然と整備されている。また、農家の経営規模も大きく、単位面積当たりの収穫量も高い。わが国有数の早場米の産地として知られている。
石川県金沢市の伝統産業
石川県は、日本海側のほど中央部に位置し、石川県・岐阜県・滋賀県・京都府にそれぞれ県境を接していて西北方は日本海に面している。石川県は旧越前・若狭の2国からなるが県庁所在地の石川市をはじめ武生・鯖江・大野・勝山・敦賀などの主要都市は越前に属し若狭には小浜市がある。北陸道は古くは越のくにと呼ばれ越前はその玄関口として早くから大和文化に同化してその北辺を為していた様である。このことは県下から青銅器時代の遺物である銅鉾が数個出土されしかも井向で発掘されたものが銅鉾出土の北限に当たり弥生時代の後期には近畿を中心とする銅鉾文化圏に属することが推察される。
むかし北陸路を旅する者の最大の難所は木ノ芽峠であった。越の名の由来はこの峠にあったと言われている。これより東北を嶺北、西南を嶺南と呼んでいる。嶺北を地理的にみるとその西北越前平野があり、平野は三方を山で囲まれている。平野の西は丹生闇が走り山地を隔てて越前海岸がある。南方にあって東西に走っているのが越美山地、東北方にあって連山を為すのが加越山地と呼ばれている。この他越前中央には越前中央山地がある。
丹生山地と越前山地の間には越前平野に続く武生盆地、加越・越美・中央の3山地の間には大野盆地があり、越前平野と共に主要な生活の舞台となっている。
県の南方を走る越美山地は古生層からなり標高1200m前後の高原性山地で能豪白山・冠山等の高山がある。この山地には木ノ芽山陵から南東に小浜市から南東に走る熊川断層との間に多くの交通路が通じている。嶺南地方は若狭湾の大陥没に伴うリアス式海岸の典型をなし入り組んだ副湾を抱いている。
(加賀友禅)
江戸時代元禄年間(1688〜1704)を中心に活躍した京都の絵師、宮崎友禅により始められたと伝えられる。友禅染の本場、加茂川染とも称され、既にあった加賀友禅を母体として発達した着彩模様の染め物である。加賀友禅は、山水や花鳥など狩野派や土佐派の絵模様を基調として発達した画風で、加賀友禅五彩と呼ばれた。すおう・あい・おうど・すみ
を主色に、ボカシの組み合わせによって織りなされた華麗優雅なもので、世界で最も美しい染め物と賞讃されている。近年は高級和風として脚高を浴び、急激に需要ものびているが、職人不足などの問題を抱えている。
(加賀蒔絵)
蒔絵は漆で絵を描いて金箔や銀箔を蒔きつけて仕上げる技法で、漆工のうちで最も美術的な日本独特の工芸として世界的に知られている。加賀蒔絵は、寛永年間(1624〜44)3代藩主利常が、京都から五十嵐道甫を招いた奨励したのに始まり、正保年間(1644〜87)には江戸から推原市太夫が来沢して印籠・香合などの数々の逸品を制作した。製品は高級調度品や茶道関係の繊細華麗なもので、「加賀蒔絵」として珍重された。現在の金沢を中心とする蒔絵はその伝統を受け継ぐもので、製品に茶道具や各種装飾品がある。輸出品としても重きを為している。