
泉佐野市内全域スピード対応!!

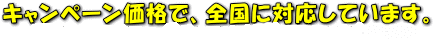



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。 ISOとは、International Organization
for
Standardization(国際標準化機構)の略称で、国際的な標準を定める機関です   |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
網戸をしないで寝たことが一度あったんです。その時は凄く大変でした。蚊には刺されていたるところが痒くなりましたし、蜂みたいな変な虫が大量に入ってきましたし、団子虫が入ってきたのが驚きました。2階に住んでいたんですけど、まさか団子虫が窓から入ってくると思ってもみなかったです。改めて網戸の有能さを感じざるおえなかったです。沢山網戸の種類があると思うんですけど、自分が住んでいたアパートの網戸は昔ながらの網戸だったんです。なのでかなり目が粗いなと思い、網戸をしても意味が無いのかなって思っていたんです。実験という事でも無かったんですけど、今になって考えるとなんで網戸をしないで寝なかったのかなって少し後悔しました。なんでこんなに後悔してるのかと言うと、蚊に刺された部分が痒くて無意識にかいてしまっていたんです。その結果、掻き毟ってしまった部分が痕になってしまったんです。女なので痕が残ってしまい、凄く後悔しました。こんな事なら網戸をしていればよかったなって思いました。しかし、後悔しても始まらないので、前向きに考えるようにしました。あれから3年経過したんですけど、掻き毟った痕はあまり目立たなくなったので本当に良かったです。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。
まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。
そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。
また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。
特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300~500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。
また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
襖の張替えで家の中の雰囲気を変えて見ましょう
襖は、日本に古くから伝わる建具で、基本的に木製の枠組みに紙や布等を貼り付け、部屋の仕切りや押し入れ等の開け閉めの為に引き手が取り付けられております。その歴史は平安時代迄遡ると言われており、その当時は鴨居等に掛け布団等が掛けられ部屋を仕切っていたとされております。室町時代になると布団では無く、無地の布や紙等を貼った物が登場します。又、襖は唐紙とも呼ばれ昔の中国の唐の時代に伝わったとされ唐紙障子とも呼ばれておりました。そんな襖には、和ふすまと量産ふすまと呼ばれる2つの種類に分類する事が出来ます。和ふすまは、襖の中に有る下地を何度も使用し、ふすま紙を張替えする事が出来る「浮かし貼り」と呼ばれる工法が使われます。一方の量産ふすまは、下地に糊を付けて直接ふすま紙を張替える「べた貼り」と呼ばれる工法が取られ、何度もふすま紙を重ねて張替える事から、最後にはふすま全体が反ってしまう等の不具合が発生する場合も有ります。これらの襖の張替えは、基本的に次の様な手順で行われており、工法は昔も今も大きく変わってはおりません。先ず襖の枠組みを外しますが、枠組みは釘を使って襖の下地に打ち込まれている為、その釘を抜く事で枠組みを外す事が出来ます。次に襖に取り付けられている引き手の部分を外します。次にふすま紙の上張りを剥がし、骨組みや下地等の補修を行います。ふすま紙を張替える場合は、ふすま紙の種類にもよりますが、再湿のりタイプのふすま紙の場合には、ふすま紙全体を水でしっかりと濡らし、ふすま紙を張った後は中に残った空気をきちんと押し出しておく事が大切です。その後は、襖その物をしっかりと乾燥させ枠組みや引き手等を取り付けます。この様に襖の張替えを行う事が出来ますが、数年毎に襖を張替える事で家の中の雰囲気を変える事も出来ます。
襖の張替え修理でまずは把握するべきこと
伝統的な日本家屋に欠かすことができない存在の一つが襖。
襖には断熱性と調湿性があり、まさに日本の風土に合ったものなんですね。
和室に使われる建具とか調度に木や紙製のものが多いのはそれらの材料が日本ではかなり豊富に取れるという点もありますが、気温や湿度の変化が大きいので、襖のような存在こそが快適に過ごすために必要であったからという理由でもあります。
さて、この襖ですが木と和紙でできている以上張替え修理が頻繁に必要になります。状態を気にしないという人であればいいかもしれないですが、客間の襖などは美しい状態を維持するためにも張替え修理はきちんと適度に行うようにしましょう。
最近では襖の張替え修理ではなく、もう使い捨てを前提にしているものもあったりします。例えばダンボールで作られているものなんかは上の襖紙を剥がして張替え修理をすることよりは新しく買ったほうがよいでしょう。
自分の襖がどういうレベルのものになるのかによって張替え修理へといくムーブも相当に違ってくることでしょう。高い襖なのか、使い捨てなのか、それすらあんまり普段から意識していない人もいるでしょうから、そこからの把握から始めることも大事なんですね。
無料お見積りはこちら
|
|
|
網戸は時代が経つにつれ色々な種類が登場し張替えも進歩している
網戸が一般的に使われはじめたのが昭和30年代前半となっていて、生産量も増え、一般家庭で使われはじめ注目を集め人気を呼んだのは事実であり、時代が経つにつれ網戸を製造する技術や知識もかなり良くなっていき、張替えとかもスピーディーに行えるようになっています。網戸については色々な種類が製造されていて、雨・風・雪などに強く壊れにくいまた網の部分が破れにくいものとかが出ていたりしていて、張替えとかも簡易的にできるものとかもあったりするので網戸の張替えとかもすぐにできる感じではあり、そういったことを専業としている専門業者も施工を迅速に行えるようになっています。
網戸の張替えとかの施工は業者によって異なったりしておりますが、優良なところであればあるほどリーズナブルな料金で対応してくれるのは事実であり、オーダーメイドとかもできるのでオリジナルの網戸とかも作れるようになっています。網戸の張替えとかは5年また10年を目安に考えたほうが良いとされていて、張替えようと思った時は業者に依頼を出して専門スタッフの方に診断を受けたほうが良いと話を聞いたことがあります。
網戸は素人の人が見ても張替えて良いものなのか今のまま使い続けて良いのかと迷ってしまいますが、プロの人の目だとすぐに診断がつくので無難なアドバイスや提案を受けられるようになっています。これは豆知識ですが、実は網戸は遥か昔から使われていて似たものがすでに鎌倉時代ぐらいからあっとされていて、張替えもその頃からあったのではないかと言われています。
関西の玄関口にある泉佐野市はええとこ
泉佐野は大阪の南部に位置する市です。人口は約10万にほどで中堅どころの街として昭和23年に泉佐野市となり、その後周辺の5つの村が合併し、現在へと歴史を刻んでいます。市の花は市内の山間部に咲くささゆりで、毎年6月ごろに可憐な白い花を咲かせています。また、市の木はイチョウです。その葉の形が扇状をしており、これが市章の形に似ているということから決まりました。秋にはその葉は美しい黄色に変化し道行く人の目を楽しませてくれます。
泉佐野市は山には緑があふれ自然を生かした産業があり、西側は海に面していることから漁業も盛んです。また、海沿いには交通の便を生かして、多くの企業が集まっています。特に泉佐野食品コンビナートは食コンも呼ばれ地域住民からも親しまれています。名前のとおり多くの食品を製造する企業が集まっており、世間でも名の知れた企業が多く、大阪府民はもちろんのこと、和歌山、奈良といった周辺地域からも多くの人が働きに集まってきています。
この泉佐野周辺の地域は、平成6年にできた関西国際空港の出現によってずいぶん変貌を遂げました。これまでは大阪の北部にしかなかった空港でしたが、こちらに国際空港ができたことで、人の流れも変わってきました。泉佐野は高速道路上でも大阪と和歌山をつなぐ要所となっていますし、東側からつながる沿線道路からは大阪南東部とのアクセスの拠点ともなっています。空港の発展とともに、現在では連絡橋のたもとには多くの商業施設が立ち並び泉佐野の見所ともなっています。
その町はりんくうタウンとも呼ばれ、高さ256メートルのりんくうゲートタワービルがそのシンボル的な存在となってそびえています。周辺には大観覧車やボーリングジョーに加え、飲食のできるお店も揃ったりんくうプレジャータウンや、最近各地で盛り上がっているブランド品のアウトレット品の販売を手がけているりんくうプレミアム・アウトレットがあります。また、温泉施設も隣接していることから、一日家族で楽しむことができる施設となっています。
そんな発展を遂げてきた泉佐野ですが、ここ最近は日本全体の流れと同様に若干人口が減少してきています。泉佐野と関西国際空港とは切っても切り離せない関係にはなっていますが、昔ながらのよさを見直すときにもきています。その中で泉佐野漁業青空市場で水揚げされる地元産の食材などを利用して、この土地ならではのサービスを売りに新旧織り交ぜ、融合した産業を発展させていくことで、さらに「ええとこ!泉佐野」になっていくことが期待されています。
大阪府泉佐野市について
大阪府泉佐野市は大阪府の南西部に位置する市で、大阪湾の沖合には関西国際空港があります。関西国際空港の一部も泉佐野市の市域に含まれています。訪日外国人が多く利用する関西国際空港の対岸に位置することもあって、泉佐野市はそうした人たちの宿泊需要の受け皿となっています。泉佐野市は古くから商工業の盛んな地域でしたが、関西国際空港ができてからはその立地を活かした観光などホスピタリティ産業にも力を入れています。泉佐野市では市のマスコットとして犬のようなキャラクターを採用しています。これは泉佐野市にある犬鳴山や特産品の泉州タオルをモチーフとしたものです。泉佐野市が公募して集まった作品を基に仕上げのデザインを行ったのはキン肉マンの作者で知られるゆでたまごです。泉州タオルがマスコットキャラクターに使われているように、泉佐野市はタオルの生産でその名を全国に知られています。泉州タオルは国内生産のおよそ半分のシェアを占めていて、国からJAPANブランド育成支援事業の認定も受けています。市内にある仁和寺の末寺は仏塔古寺十八尊のひとつに数えられ、国の史跡に指定されています。また、本殿が国の重要文化財である総福寺天満宮などもあります。
泉佐野市は、大阪府に位置しています。古くから農業や漁業、工業などが盛んなこともあり、繁栄を続けてきました。決して面積は広くないものの、豊富な産業の育成に成功したこともあり、人口が多くなったのです。泉佐野市の農業を語る上では、タマネギと水ナスを忘れるわけにはいきません。泉佐野市の名前を全国レベルにまで引き上げることになったのも、農産物があったからという声もあがっています。泉佐野市では、タマネギと水ナスの他にも、キャベツやブロッコリー、さといもなどの栽培が盛んです。いずれも、日本の食卓には良く登場する農産物であり、年間を通して食べられるようになっています。泉佐野市では、タオルの産地としても有名なことをご存知でしょうか。国内シェアの多くを占めるまでに成長を遂げています。今では泉州タオルとして、日本ブランドの一つになっています。また、泉佐野市では、ワイヤーロープの産地としても有名です。さまざまな現場で活躍を見せるものですので、注目に値するといえるでしょう。泉佐野市の誇る漁業では、カレイやシタビラメ、ワタリガニなどが多く獲れます。大都会でありながらも漁獲量が多いのが、泉佐野市の特徴ともなっています。