
神戸市西区全域にスピーディーに対応します!!




|
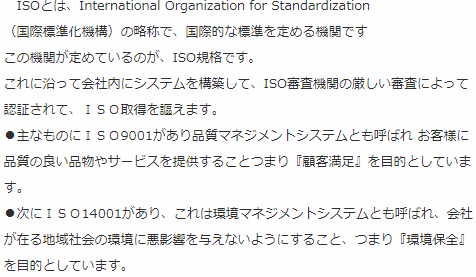   |
網戸の汚れを放置しておくと、雑菌が網戸を通して家の中に入るため、病気や家のいたみの原因になりやすいことは、あまり知られていません。定期的に網戸掃除を行う事で、家の中に雑菌やカビが入ってくるのを防ぐことが可能といわれています。掃除の方法として挙げられているのは、網戸を外して洗う方法ですが、集合住宅の場合や小さいお子さん、ペットがいる場合には、はずさずに洗える方法を実行しましょう。短時間でスピーディーに洗えるので便利ですが、カビなどが発生しないよう、定期的に行う必要があります。特に夏が近づいてきたとき、気温が上昇してきたとき、花粉シーズンを過ぎたらすぐ掃除することで、網戸に余分な汚れがついておらず、家の中に入る可能性が低いです。窓ガラスも一緒に掃除をしておくと、日光や網戸の汚れを少なくできるので、窓と網戸は一度に掃除することが有効といえます。掃除の際にはホームセンターで専用の道具が販売されていますが、自宅にある雑巾や重曹、さらに中性洗剤を使うことで簡単に掃除できるので、必ずしも購入する必要はありません。手順を覚えておくことで、定期的に掃除を行え、網戸や窓の清潔を維持できるため、家族全員で覚えておくことをお勧めします。
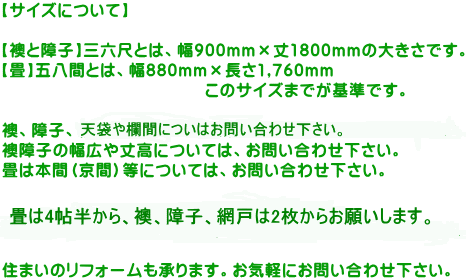
| 無料お見積りはこちら |
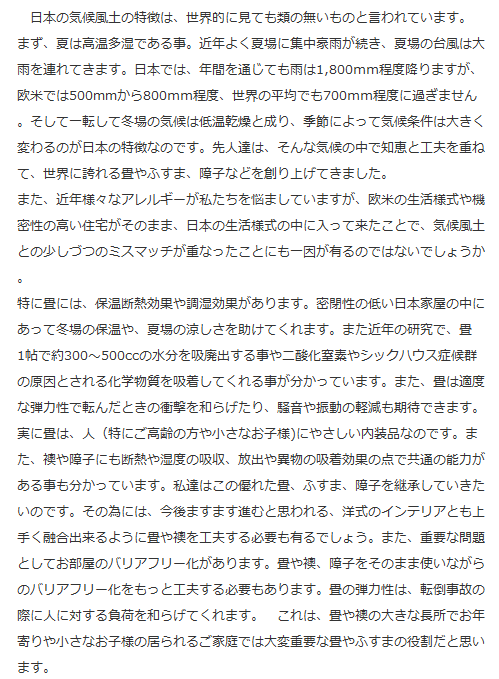
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
畳の張り替えを考えているという人がいますが、この作業は自分で行うと言うことがなかなか難しいので業者に依頼すると言うことをおすすめします。現在では畳の張り替えを行ってくれる業者が日本全国になるので気軽に利用することができるようになっています。
この畳の張り替え作業で気になるのがその価格です。コストを抑えたいというのであればその種類によって1畳当たり2700円から3500円、5000円ものがありますが、よりい草の香りを楽しみたいという人には高級品のものとして2万2000円のものもあります。
畳の張り替えに庵しては、畳の裏返しや畳の張り替え、このほかに新しく交換するという方法があります。それぞれの畳の状況によって業者が判断してくれるようになっています。また畳床にもこだわっているところが多いので、カビや湿気を防止することもできます。
襖の張り替えに関しては選ぶ襖の種類によって価格が異なってきます。業者によって採用されている銘柄に違いがありますが、さまざまな見本帳を見て選ぶことができるので、安心です。専門スタッフに相談することもできます。
障子の張り替え交換修理に関しては、障子の枠の汚れや傷をしっかりと取り除いてくれるので、障子紙がきれいになるということのほかに全体的に仕上がりがきれいになります。最近では強度に重視したタフトップといわれるものやビニールを使った障子紙も登場しています。
襖を張り替えるタイミングとは
襖を張り替えるタイミングは、大きく破れてしまったときや大掃除のときが多いです。畳を張り替えるのは、畳の表面が黄色く変色し、すれてぼろぼろになってしまったときなので5~10年に1回ほどの頻度です。襖はそんなに破れることがない上、畳ほど明確に変色や消耗をしないので、張り替えるタイミングが難しい建具です。襖にダメージを与えるのは湿気と日光です。換気ができていない湿度の高い状態が続くと、襖が波打ったままになってしまうことがあります。一方で、強い日光に当たりすぎた場合も、変色をしてしまうので、数年もすると、日光の当たっている場所と当たっていない場所で、襖の色が全く違うという状態になることもあります。襖も劣化や変色が目立った場合には、他の建具と同様に張り替えないといけません。変色した襖を張り替えることによって、和室の雰囲気が清潔で明るいものに変わります。襖を張り替えるコツや方法については、インターネット上で多数紹介されているので、自分で張り替えることが定着してきているようです。特に、シールで貼ることのできる襖紙を使えば、初めての人でも、簡単にしわになることなく、新しい襖を貼ることができるようです。
| 無料お見積りはこちら |
神戸市西区について
今の神戸市西区に当たる地域は、明治時代初期の廃藩置県で明石県の一部になった。垂水区と同様に明石郡に属していた地域で、隣接する明石市とも結びつきが強いが、かつては田園地帯・公共交通の空白地域
であったが、野田文一朗が明石平野に新都心が計画することを構想し、1965年の市議会で原口忠次郎が宅地計画を挙げたこと から1970年頃から、神戸市中心部のベッドタウンとして、開発が進み、西神ニュータウンや押部谷地域・玉津地域を中心に大
きく様変わりし、同時に公共交通の敷設計画をした区である。神戸市の新たな文化、教育の集積地としての期待がかかり、現 在のところ神戸市9区で最も人口が多く、市の3割近くを面積を当区が占める。1982年(昭和57年)に垂水区から分区して伊川谷町・櫨谷町・玉津町・平野町・押部谷町・神出町・岩岡町が西区となる。分区当初の人口は約9万4000人である。神戸市で一番新しい行政区である。
六甲山地の西側で播州平野の東端にあたる。大部分はなだらかな丘陵地帯とそれに明石川や伊川などの川に侵食された谷であ る。東部の丘陵地帯には神戸市が中心地の人口密度が過密なためにポートアイランド・六甲アイランドの土砂確保と同時に計
画した西神住宅団地、西神住宅第2団地(西神南ニュータウン)、西神工業団地、西神第2工業団地、神戸研究学園都市、神戸複合産業団地といった西神ニュータウンと呼ばれる新興地区などが存在し、谷は旧来の田園風景を持つ農村地帯となっている
。同様に隣接する北区も農村地帯があるが、当区では近郊農業地帯である。西部の神出町、岩岡町は印南台地の東端にあたり 、ため池が点在する農村地帯である。あまり高い山はない。
分区当時は全9区の中で一番少なかったが、玉津地区と伊川谷地区の区画整理事業・西神ニュータウン開発のために市の中心部 から流入されてきたために人口が増加し、更には阪神・淡路大震災後神戸市の人口は大幅に減少したが、当区は被害が少なか
った、かつニュータウンが開発中であったために神戸市内の中心部から人が流入し、西神南ニュータウンなどでのマンション建設によって神戸市中心部からの人口が急増した。
神戸市西区は神戸市の中でも大きな区です。ですから、地下鉄沿線とそこから離れた場所では雰囲気が全く異なります。中心部は西神中央で、西神中央駅には大型ショッピングセンターや百貨店があり、居住するには快適な場所です。また、西神中央駅周辺は閑静な住宅街が広がっており、治安についても申し分なく生活することができます。そして、教育機関も充実しており、保育園、幼稚園から学習塾まで子供を育てるにも不自由しない環境が整っていますので、住みたい街として人気を誇っています。そして、神戸市西区には西神中央駅の隣の駅に西神南駅があり、西神中央駅同様に閑静な住宅街が広がっており、若い世帯のファミリーが多く住んでいます。そして、神戸学院大学が神戸市西区の伊川谷にあることから学生が多く、大変活気のある街となっています。伊川谷には、居酒屋や飲食店、カフェなどが多数立ち並んでいるので、老若男女問わず人気のある街です。そして、神戸市西区には西神中央駅から車で5分くらいに位置する農業公園という施設があります。農業公園には、牛牧場やバーベキュー場、ワインの製造などをしており、1日楽しむことができます。また、夏場にはプールの解放をしており、地元の子供たちで賑わっております。そして、神戸市西区には広大な敷地から農業も盛んです。地元で採れた野菜などの直売所が至るところでありますので、新鮮な野菜をいつでも安く食べれます。
(太山寺)
三身山と号する播磨きっての巨刹であり、県下で最も多数の文化財を有することで知られている。奈良時代の霊亀2年(716年)藤原鎌足の子、定恵和尚の開山で、鎌足の孫、宇合が諸堂宇を造営したと言われている。元正天皇の勅願所となり、白河・後宇陀・崇光天皇も当寺に臨幸したと言われる。中世には寺運も隆盛を極め塔頭寺院も41坊を数えたが、時代が下るにつれ寺運も次第に衰え、江戸時代中期の享保10年には11坊と成り、明治4年になっては、5坊を残すのみと成っていた。しかし盛時の遺構は今によく伝えられ、本堂は国宝、仁王門は重要文化財に指定されている。
境内地は約14000m2でうっそうとした樹林に包まれた境内地には雄滝・雌滝・照明滝などが流れ春はサクラ、夏は新緑、秋は紅葉を求めて訪れる参詣客も多い。また奥の院の堂下から湧き出る水は、眼病に霊験があるとして参詣者も多い。
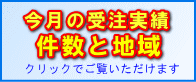
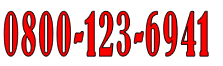
![]()

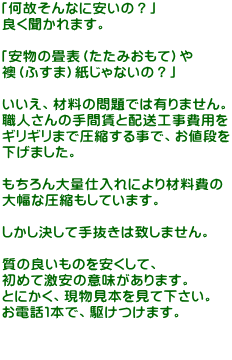
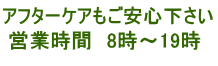
神戸市迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
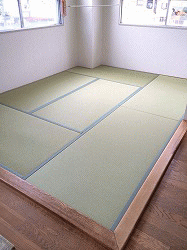
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
襖とは、木で作られた骨組みに紙や布を張り合わせて、開け閉めが可能になるように取っ手た縁を付けた日本の仕切りとして用いられてる建具です。
襖が開発されるまでは日本の貴族住居の仕切りはすだれや、衝立が使われていました。
襖が用いられたのは御所の寝殿を区切るものとして使われていたといわれています。
その当時の襖は絹の織物を張った形状となっており、現代の襖よりも薄かったといわれています。
その後唐(現在の中国)から「唐紙」と呼ばれるものが伝来され、襖に用いられていきだんだんと普及されていきました。
平安時代の末期には「源氏物語」に襖が描かれており、その頃には貴族のなかでも普及されていると思われます。
さらに時代は進み、武士が現れる時代になると武士の階級によっては、豪華な絵をあしらった襖を住宅に取り入れておりインテリアとしての需要も現れてきています。
現代でも、和室の押入れや区切りに使用されており、和室と洋室を分ける効果があります。
洋室側には木材調のデザインで、和室側からは布状の昔から変わらないデザインを用いることも可能となっています。
張替えや手入れを行うだけでモダンな雰囲気を作り出すことの出来る襖。
今も変わらず、日本人に愛されています。