
全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

大阪府豊能郡能勢町全域にスピーディーに対応します!!




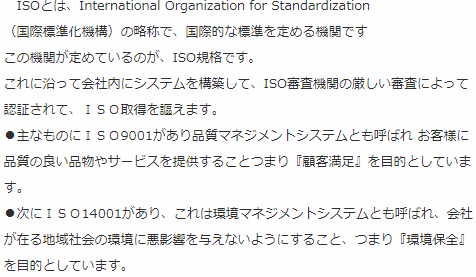   |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます夏場の快適な暮らしになくてはならない物の一つに網戸があります。窓を開けて網戸にすれば風が通るので当然涼しくなりますが、実は風だけではなく温度も3℃ほど下がる事が実験結果で分かっています。次に網戸も開けてみましたが温度はほぼ同じ状態でした。つまり窓を全開にしている状態と変わらず、虫よけにもなり日常生活の必需品と言えるでしょう。一口に網戸と言っても色んなタイプがあります、例えば一般的なパネルタイプ、これは引き戸形式でどこの家庭でも見られるタイプです。次にアコーディオン網戸、その名の通りアコーディオンのように降り曲がりながら収納できるタイプです。ロール式網戸はネットをロール式に巻き取ることが出来るタイプで、横引タイプと立て引きタイプがあります。巻き取り部分のサイズもコンパクトで取り付けも簡単で人気があります。最後に折り戸式網戸、これは二つに折れて開閉するタイプです。二つに折れることで出入時に邪魔にならず便利です。ペットと暮らす家庭ではペットが網をひっかいて破ってしまうという悩みがありますがそれらを解決する製品が開発されました、これはポリエステルにビニールコーティングし、弾力を持たせた、ひっかきなどに強い網戸です。また簡単にペットドアを網戸に取り付ける商品や、ペット対応されたくぐり戸付きなどもあります。夏場、玄関とリビングに網戸があれば爽やかな風が通り抜け、エコで快適な生活がおくれます。
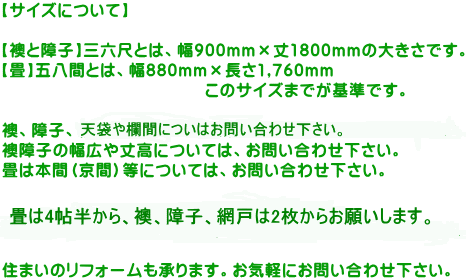
| 無料お見積りはこちら |
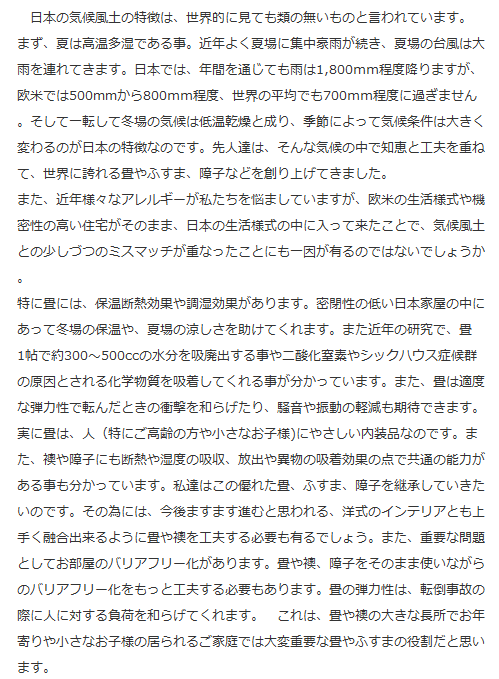
近年は日本の欧米化によりフローリングの部屋が増えてきましたが、畳は日本人にとっては馴染みのあるものでまだまだ根強い人気があります。新築やリフォームをする方も、1部屋だけは畳の部屋にしよう、という方も多いのではないでしょうか。畳の良さやメリットには何があるのでしょうか。そのまま寝転んだりくつろいだりすることが出来る点が畳の良さです。冬でも畳の上に布団を敷いて寝ることが出来ます。フローリングだと布団を直に敷くことは少なく、ベッドや厚手のマットレスなどを布団の下に敷くことが多いです。寒い冬場は直に冷たさが伝わってきて身体にもあまり良くないからです。畳のいぐさの香りは癒し効果もあります。また畳はフローリングと比べてクッション性があります。物を落としたときに壊れにくかったり、転んだ時に打撲を和らげることが出来ます。足音なども吸収してくれるので防音性にも優れていると言えるでしょう。畳はダニが発生したり変色しやすいなどの理由で畳を敬遠されている方は、和紙畳が人気が出ているようです。ダニも殆ど発生しなかったり、変色もあまりしないそうです。また、床暖房にも対応していることから新築で床暖房を考えている方などでも利用できます。
日本の気候にマッチして、日本人の生活になじみの深い畳を気持ちよく使っていくためには、適切なメンテナンスや手入れが必要です。自然素材の稲ワラやい草を使っている畳は呼吸をしています。人間も空気が汚いと病気になってしまうように、湿気がこもった状態が長く続くとカビやダニが発生して早く寿命が来てしまいます。畳は水分が大敵です。普段の拭き掃除には濡れた雑巾を使わないようにしてください。掃除機やほうきをかけるときには、畳の目に添ってかけてください。できれば、年に1回は畳を天日干ししてあげたいのですが、天日干しができない家庭では天気が良い日は風を通してあげるだけでも畳の中の水分をだいぶ飛ばしてあげることができます。普段の手入れでも畳が快適に使える期間を伸ばせますが、さらに張替えをすることによって新品に交換するよりも安価で新品と同じように気持ち良く使うことができます。畳表の裏と表を入れ替える裏返しをすれば日に焼けていないきれいな面を使うことができます。また、畳表を完全に交換する表替えをすれば縁も交換になるので、新品同様の見た目と香りが楽しめます。普段の手入れと張替えをすれば、15年程度は畳を新品と同じように利用することができます。
奈良時代から平安時代にかけて、貴族の邸宅は大広間に柱が並んでいる形になっており、西洋のドアに類する建具はありませんでした。そのかわりに几帳や屏風や衝立が、間仕切りのために利用されていました。その中でも寝所を区切るために使われたのが襖障子です。襖はもともと掛け布団の意味でしたが、これを衝立に掛けて仕切りとしたことから、襖という言葉が定着しました。平安時代も後期になると、現在のような引き違い式の襖が使われるようになります。また従来の絹織物ではなく、紙を貼った襖が用いられるようになり、装飾性や防寒性が向上します。室町時代から安土桃山時代にかけては、書院造の住宅の襖に水墨画や大和絵を描くことが流行します。豪華絢爛で芸術性の高い障壁画が制作され、現在にまで残っています。江戸時代になると町家にも襖が普及しはじめ、一品物ではなく印刷による襖絵が描かれるようになります。明治に入ると和洋折衷の戸襖が発明され、やがて庶民の住宅にも広まって、芸術品ではなく生活の一部となっていきます。現在では合成樹脂や合板を材料にした製品も生産されていますが、伝統的な製品は本襖と呼ばれ、平安時代からほとんど変わらない製法で作られています。
窓サッシに必ずセットされている網戸ですが、日本で今のように使われるようになったのは意外と最近で、早く見積もっても昭和30年代以降の高度経済成長期からです。この頃になると国民が豊かになり、住宅が洋風化してガラス窓が増えて網戸の需要が高まります。さらに日本で樹脂から作る網戸ネットが開発され、安価で大量生産できた事で一気に普及しました。では海外ではどうかというと、網戸のようなものというのは、中世のヨーロッパで記録が見られます。細かいレースの網などを窓に張って、蚊や蝿などを防いでいたようです。そして17世紀になって金属製の網を使用した網戸が登場しており、現在の網戸の原型となっていると考えられております。ヨーロッパよりも高温多湿で蚊の多い日本なので、網戸の需要ははるかに高いはずですが、日本で同様の物が使われなかったのは、家の通気性をよくするために隙間が多い構造だったため、窓を覆うような網戸を設置するのが難しく効果も低かったためです。そのかわり日本には蚊帳がありました。蚊帳は奈良時代に中国から渡来した技術者によってその製法が伝えられ、昭和初期まで日本における防虫対策の主力として活躍し、それ以降は網戸にその役割を譲りました。
| 無料お見積りはこちら |
大阪府豊能郡能勢町は大阪府の最北端に位置する町で、京都府亀岡市や兵庫県川西市に隣接するなど他府県に多く囲まれています。能勢町には鉄道路線が乗り入れておらず、大阪府下で唯一隣接する豊能町へ直接出る道が一本しかないなど、大阪府内の自治体でも独特の地理的環境にあります。このように能勢町は交通網があまり整備されていない一方で多くの自然が残されています。町を取り囲むようにそびえる山々や、山間に広がる田園風景など、日本で失われつつあるかつての光景を能勢町では満喫できるのです。また、こうした自然環境が残っている能勢町には珍しい生物も生息しています。特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオやモリアオガエル、ヒロオビミドリシジミなどの生息が確認されています。自然豊かな能勢町には観光スポットも数多くあります。妙見山という名前の山は全国各地にありますが、能勢町にある能勢妙見山には日蓮宗の寺院があり、勝海舟や坂田三吉も参拝に訪れたと言われています。能勢妙見山へは妙見の森ケーブルがあるほか、車で上がることもできます。春には桜、秋には紅葉、冬には雪景色など四季折々の風景を楽しめる能勢町の名物スポットになっています。