
住吉区内全域スピード対応!!

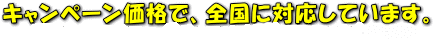



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
網戸は異物の侵入を防ぐために使う建具の一種ですが、住宅などで広く普及している樹脂製の網戸は引っ掛けや高温に弱く、少しの刺激で破れてしまうことがあります。網戸が破れると異物を遮断する効果が無くなるので速やかな補修が不可欠ですが、破れた部分だけを塞ぐ重ね張りはすき間が出来る原因になるので、網戸を丸ごと張り替えるのが無難な対処法です。網戸の張り替えは専門業者に依頼するのが一般的ですが、費用が嵩んでしまう問題があります。近年では特定の寸法に裁断された補修用の網戸が市販されているので、業者任せにせず自分で補修する方法もあります。市販品の網戸には補修の手順を記した説明書が同梱されていることが多いので、初めて網戸を補修する人でも不具合を出さずに仕上げることが可能です。その一方で作業を手際良く進める必要がある他、補修用の網は乱暴に扱うと破れてしまうので取り扱いには細心の注意を払うことを心がけます。また、古い建物は窓の寸法が現在の規格に合わないことがあるので、事前の入念な計測が不可欠です。市販の網戸で対応できない寸法の窓は業者に張り替えを依頼することになるので、窓の形状や張替えに用いる網の材質を詳しく説明して作業をスムーズに進めるように配慮するのが大切です。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
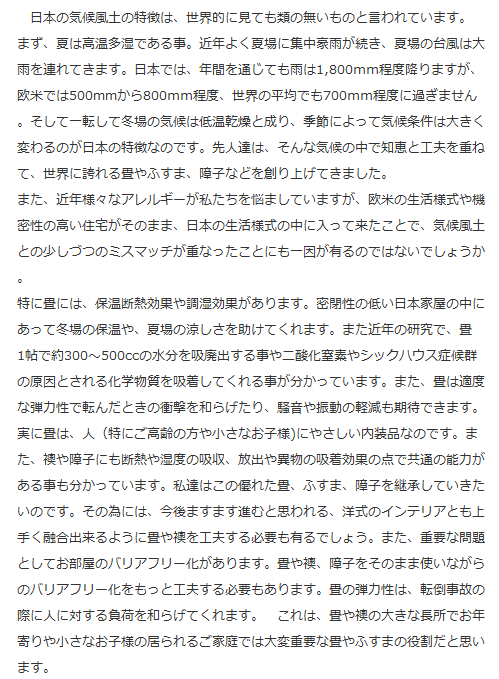
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
日本の伝統 襖の張替え
襖の歴史は古くは平安時代から、千利休の茶室ができた安土桃山時代には絵師が傑作を生み出し、襖絵の黄金時代とも呼ばれています。一般的に普及したのは江戸時代の頃、今や和室には欠かせないものとなっています。このように古くからの歴史ある襖は、季節で温度環境の激しい日本の家屋を快適に過ごすことができるように作られています。そんな住まいの襖を長い間、張替えをしたことがなく、全体的に茶色になっているということはありませんか?実際襖の張替え時期というのは意外と気がつかないということが多いものです。見た目もさながら、建て付けなど悪くなったらそれは張替え時です。張替えの折にふれ一番大切とされる下地により、襖には種類と施工方法(貼り方)がそれぞれ違ってきます。ではここでいう襖の下地とは一体何なのでしょうか?住まいの襖の下地は組子骨という木を欠いて組んで作成されたものと発泡、ダンボール、チップボールなどの芯でできた量産襖に分けられます。組子骨はコスト面以外において強度や耐久性に優れ、当然それにより襖の張替えのお値段も変わってくるのです。住まいの襖の張替えを専用業者に依頼をする際には、内容をよく確認することが重要です。
網戸の張替え修理は大変なのでお願いしてしまう
網戸の張替えは壊れていましたから、それはよいタイミングといえるでしょう。
網戸に穴があいているとそれはよくないことです。そこから間違いなく虫やほこりが入ってくることになります。 ですから、そんな状態の網戸であれば張替え修理は早急に行わなければならないわけですね。しかし、張替え修理をしようとするためにものすごく準備が必要になりますしこれまで行ったことがある人と言うのであれば良いかもしれないですが、行ったことがない人はどんなことからやらなければならないのかといったようなことまで調べてる必要があるんですよ。これがとにかく手間。上手くできる保証もないですしね。
網戸の張替え修理は自分でするには、けっこう時間がかかりそうと思うのは正しい認識ななんですよ。 では簡単に張り替えるにはどうすればいいのか、それは張替え修理をしてくれる業者にお願いすることです。
取り外しから、設置まで総合的にやってくれることでしょう。 気をつけなければならないのはどんな網に張り替えてくれるのかとかもそうですし値段的な問題もそうでしょう。値段に関しては確実に見積もりを出してくれるところにお願いするということで安心できるようになりまます。
網戸の張替え修理は少しでも安いところにお願いしたいものです。
大阪市住吉区について
住吉大社に由来する広域の地名を継承するもの。住吉大神が住むべき国を探していた際、当地に至って「真住み吉し」として社地を定めた故事による(『風土記』)と伝えるが、『新撰姓氏録』の住吉氏が当地を管掌したとする説もある。
大阪上町台地の南部で大阪市の最南部にあたる。大和川をはさんで堺市隣接しています。6本の鉄道、あびこ筋とあべの筋の2本の主要道路が、いずれも都心部と南北に結ばれています。区の北部は、阿倍野区南部から続く住宅街で、阿倍野区の帝塚山一丁目から住吉区の帝塚山中、帝塚山西と大きなお家が並びます。
その南に位置する住吉大社を中心にした住吉、上住吉は、旧家の多い昔からの静かな邸宅地域で、その周囲に清水丘、墨江、遠里小野、南住吉、山之内などの住宅地が続いている。現在の区域はおおむね、大阪市編入前の住吉郡(のち東成郡)住吉村・墨江村・長居村・依羅村の大半と、西成郡粉浜村の一部に当たる。
1950年代頃までは区の東部・南部に農地が広がっていたが、宅地開発が進んだため区のほとんどが住宅地となっている。住吉は古代では「すみのえ」と訓み、万葉集にも登場し、歴史は古い。現在、住吉、住之江、墨江は、別な地域名となっているが、
元は住吉の読みの「すみのえ」の異表記でした。
もとは摂津国住吉郡といい、古代には住吉津(すみのえのつ)とそれを護る住吉大社が栄えたことで難波津など大阪中心部とは独自の発展をした。
住吉津は古代の国際港であり、難波津(なにわのつ)が作られるまでは日本の国際的窓口であり、遣隋使や遣唐使はここから出発し、
またシルクロードの玄関でもあり、仏教もここから日本に入った。中世には、住吉大社宮司の津守氏の館の住之江殿(正印殿)に
南朝の後村上天皇の御座所(皇宮)が約10年間置かれ(住吉行宮)、南朝の拠点となった。
1878年(明治11年)に「郡区町村編制法」が施行されて大阪府住吉郡が誕生し、郡内では唯一の町だった安立町に郡役場が置かれた。
1896年(明治29年)4月に新しい郡制が施行され、住吉郡は東成郡に併合され消滅した。住吉区は、1925年に大阪市の第二次市域拡張に伴って東成郡全域が大阪市に編入された際、旧住吉郡全域(平野郷町、喜連村、北百済村、
南百済村、田辺村、依羅村、墨江村、住吉村、安立町、敷津村、長居村)と旧東成郡天王寺村の区域で誕生した。大阪市編入の際には、
当初は名称を「阿倍野区」とする案が出されたが、最終的に住吉区の名称が採用された。
その後、1943年の分増区により、当時の阿倍野区・東住吉区にあたる区域を分離した。1943年の分増区の際、当時の住吉区役所は現阿倍野区の
区域にあったことから、現在の阿倍野区が「住吉区」の区名を継承し、現在の住吉区の区域を「住之江区」とする案が出された。
しかし住民の反対によりこの案は撤回され、住吉大社周辺を含む当区の区域が住吉区の区名を継承した。
また1943年の分増区の際、隣接する西成区との間で区の境界の見直しがおこなわれ、一部区域(天下茶屋・山王地区および旧敷津村の一部)
が西成区に分離編入されると同時に、当時西成区に属していた粉浜地区が住吉区に編入された。
1974年には住吉区と住之江区に分区された。従来の区について、細井川(細江川)以北は南海本線・細井川以南は阪堺線を境に東西に分け、
西部を住之江区とした。住之江区の分区により、住吉公園や安立、浜口などは住之江区に属することとなった。
住吉区は大阪市にある区で、古くは摂津郡住吉郡に属していた地域です。1925年に大阪市の市域が拡張された時に行政区としての住吉区が発足しました。1943年には阿倍野区と東住吉区を、1974年には住之江区を分離しています。区の花はカキツバタです。住吉区には万代池があり、聖徳太子が曼陀羅経で魔物を退治したことから「まんだら池」と呼ばれるようになり、それが転じて現在の名前になったと伝えられています。周辺は遊具が設置された公園として整備されており、花見の名所としても有名です。また、冬には渡り鳥の姿を観察できます。大阪市住吉区には複数の神社が鎮座していますが、中でも有名なのが日本三大住吉の一つであり全国の住吉神社の総本社でもある住吉大社です。神功皇后の御代に創建されたと伝えられており、地元では「すみよっさん」とも呼ばれます。本殿は国宝で、重要文化財に指定されている建物も多数あります。止止呂支比売命神社という素盞鳴尊と稲田姫尊を祀る神社もあり、4月と12月に鎮火祭が行われます。区内にはJR西日本、南海電気鉄道、大阪市営地下鉄、阪堺電気軌道の路線が合わせて6本通っています。大阪市営バスの利用も可能です。
お客様のお話
以前、大阪、東京共に住んでいたことがありますが、比べると大阪は馴染みやすい町だと感じました。 私の地元が愛媛県であり関西色の強い地方であることが関係しているのかもしれませんが人懐っこく、人情味あふれる方が多く居たように思います。但し、方言の違いから「怖い人達だな〜」と思ってしまうことも多くありました。(実際はそんなこと無いのですが。) ただ、地元言葉に近いので東京の方より意思の疎通は取りやすく、言い方は乱暴だけど率直な意見を聞くことが多かったように感じます。大阪の生活は当時、学生だったこともありのんびりしたものでありましたが、それでも都会の生活リズムは独特のものがあり当初戸惑ったことを覚えています。せっかちなのか、大雑把なのかどうもリズムが早いように感じました。 嫌いでは無いのですが疲れることもありました。 東京に比べ、街や電車がゴミゴミしてるように感じてその県民性を伺うことができます。 それが好きだという方もおられるでしょうからそれが大阪のカラーなのでしょう。大阪に住んで最も残念だったことは水が不味い事でした。 大阪市の水瓶は琵琶湖だと聞きましたが東京に比べて随分臭かったことが記憶に残っています。 当時はミネラルウォーターの販売やサーバーの設置など多くは無かった時代ですからイヤイヤながらも臭い水道の水を飲んでいた記憶が残っています。 今では改善されているのかも知れませんが私が住んだ町で大阪が一番水がまずかったです。あと、タイガースファンが多く野球の話題が多いこと。個人的に野球に興味が無いので少々困りました。地元愛が強いのでしょうが、行き過ぎのような気もします。逆に良かった事は野菜を始めとした食品の価格が安かったこと。これは大阪の圧倒的な勝利でした。あと、店のおばちゃんが値引きしてくれる率も大阪の方が高いです。 さすが商売の町といったところでしょうか。 仲良くなると何も言わなくてもまけてくれたり、オマケしてくれたりして随分助かりました。 東京ではこういったことが一件もありませんでした。これは運の問題なのかも知れませんが、私の印象には「大阪の人はまけてくれる」と強く残っています。東京にはもう住みたいとは思いませんが大阪ならまた住みたいと思える町です。今なら水の問題はあまり気にしなくていいですから。 人口も多すぎず住みやすいところだと思います。東京は多すぎてちょっと落ち着きません。 何よりも地元に近いので便理です。 東京に比べて暖かいですし必要十分な機能をもった程よい都市ではないかと思います。
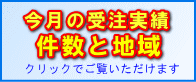
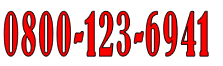
![]()

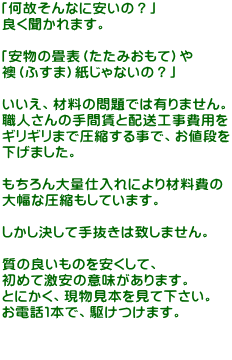
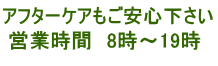
住吉区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
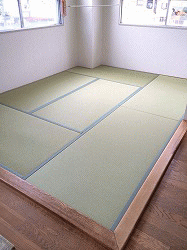
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工

洋室で生活する事が多くなっている現代では、なかなか障子の手入れや張り替えを行う機会は少なくなってきています。海外では日本の文化が注目されるようになり、日本の住宅で一つは和室を取り入れる家庭も増えてきています。そこで悩むのが障子の張り替えのやり方やタイミングです。あまり、目立つ汚れなどはなくても3年から5年ぐらい使っていると、紫外線などの影響で劣化してしまうものです。長くても5年ぐらい使用したら張り替えるのがおすすめです。張り替えのタイミングは和室を使う前がいいです。正月前やひな祭りの人形を飾る前などが最適です。綺麗な新しい障子でその日を迎える事で気分が良くなります。張り替えの準備として障子紙や糊の準備が必要です。障子紙は近くのホームセンターなどで簡単に手に入れる事ができます。昔ながらの和紙を使った障子紙の他に、小さな子供やペットがいる家庭ように破れにくいものもあるので、家庭環境に合わせて購入できます。糊は一般的に知られるハケで塗るものの他に、チューブタイプのものもあります。糊は難しいと感じる場合は両面テープで代用も可能です。あまり難しく考えず、自分がやりやすい方法でやることができます。業者の方にお願いする事も可能ですが、なかなか体験できるものではないので自分でやってみると新しい楽しさを発見できるはずです。