
大阪府堺市東区全域スピード対応!!
|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
網戸をしっかりとしてるのに、虫が入ってくるのでなんでかなってずっと思っていたんです。窓に付いてる網戸ですけど、アコーディオンみたいな感じなんです。ジャバラ方式と言えばもっとわかりやすいですかね。なので、下の部分が結構、隙間があるので、そこから侵入してくるのかなと思ったけど、大きな虫は入ってこないので違うかなって思いました。その後も虫がどんどん入ってくるので、我慢の限界になり、網戸から虫が入ってくる様子を観察したんです。すると網戸の網目から虫が入ってきてるのが確認出来たんです。まさか網戸の網目から入ってきてると思ってもみなかったので、少しショックでした。網戸の網目を細かくする事も出来ないので、対処法に困りました。結局、網戸を交換しようと思ったんです。借家なので大家に了承を取ろうとすると、網戸の交換は駄目だと言われました。まさかそんな事言われると思ってもみなかったので、少しショックでした。そのショックから立ち直れなかったので引越しを決意したんです。引越しをする際に重要視したのが網戸でした。網戸がしっかりと虫の侵入を防ぐ物件を見つけたので、そこにしたんですが、心霊現象が酷い部屋で凄く嫌でした。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
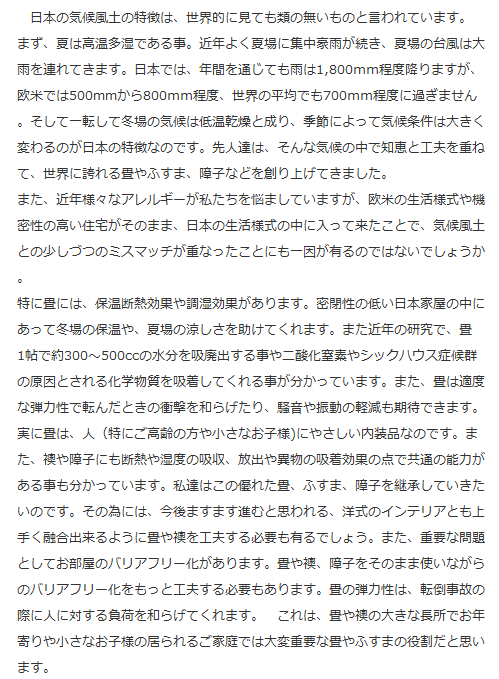
畳の変遷
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
襖の張替えは室内の雰囲気をよくする
襖もキレイな状態ですと室内に張りができるみたいな雰囲気の良さを出してくれることにはなるのですが、ボロボロであったり汚れたりしている場合においてはさすがに張替えたほうがよいに決まっています。襖の張替え自体は綺麗に極端にやろうとしない限りはそれほど面倒なことではないです。しかし、綺麗な張替えをしようとすると途端に難易度が上がるということになります。ですから、襖の張替えというのは全て業者にお任せしてしまったほうが圧倒的に楽ということがあります。襖の張替えをしてくれる業者というのは一体どんなところであるのか、といえば内装屋とかです。他にも表具屋なんかがやってることがあったりするのでそういうところを探してみて襖の張替えをしてみるようにしましょう。一体いくらかかるのかということをしっかりと見ることです。襖を綺麗にするといっても色々と柄があることになりますし、色もあります。それによって雰囲気も違うことになりますから、折角業者に依頼するわけですから、少しでも自分が気に入るようにしましょう。それができるところも自分でやるのではなく、業者にお願いすることができる最大のメリットであるといえるでしょう。雰囲気をよくさせることができます。
障子の役割と現在の種類
障子は和室には欠かせないアイテムですが、和の雰囲気だけでなくきちんとした役目もあります。障子は断熱性に優れ、換気機能もあるため閉め切っていても息苦しさはそこまで感じられません。また部屋の湿度を適切に保つ効果もあるため、古くから日本では親しまれてきました。障子を閉めても微かに明かりが漏れるという点も、情緒があり日本人に好まれる理由と言えるでしょう。現在は張替える障子紙の種類も増えてきました。両面テープや糊で貼るものや、アイロンを使うもの、破れにくいプラスチック製というものなどがあります。生活環境によって、扱う障子紙を替える方も居ます。子供やペットの悪戯対策には、強度のあるプラスチック製のものがおすすめです。プラスチックなため水にも強く、汚れても拭く事が出来ます。ただプラスチック製は、本来の障子の役目である湿度調節が出来ないため、自己での湿度対策が必要になります。破れにくいという点では優れているので、小さな子供が居る家庭には最適です。また、明るさを調節出来る障子紙もあるため、自分の好きな雰囲気に合ったものを選ぶ事が可能です。値段は低価格なものから高価格なものまで様々なので、ホームセンターや専門サイトなどで比較してみるといいでしょう。
晴れている日は網戸掃除をしよう
少し時間がかかっても良いのでしっかりと網戸を綺麗にしたいと考えている方は、網戸掃除をする際に晴れている日を選ぶようにしましょう。乾燥している状態になるので汚れを取る際は苦労をしてしまう事が多いですが、晴れている日に行うとメリットがあるので覚えておくと良いでしょう。どんなメリットがあるのかと言いますと濡れた網戸が早く乾き、早い段階で乾いてくれるので網戸に埃やごみが付着しにくくなります。そのため少しでも長く綺麗な網戸で生活をする事ができるようになります。晴れている日にしか得る事ができないメリットになります。網戸が早く乾いてくれると言う事もあり、網戸を外して洗ったりする事もできます。徹底的に綺麗にしたいと考えている方は晴れている日の方が良い場合もあると覚えておきましょう。ここで重要になってくるのは乾燥しにくい場所に置いておく事になります。濡れたままで網戸を窓の部分にセットする方もいますが、これでは網戸のレールの部分に水が溜まってしまい少し不衛生な状態になってしまいます。立て掛けておく事ができる場所を探す事によって、不衛生になってしまう事も無くなるので、乾かす事ができる部分があるのかを考えてから網戸掃除をするようにしましょう。
| 無料お見積りはこちら |
堺市東区の特徴や名所などについて
堺市東区は大阪府に位置している行政区である。近畿地方にあり面積は10平方キロメートルで、人口は約8万5000人となっている。堺市東区に隣接している自治体や行政区は、堺市の北区や中区や美原区、大阪狭山市となっている。
東区役所の場所は、大阪府堺市東区日置荘原寺町195番地1となっている。堺市を構成しており、堺市の東側、美原区と共に南河内郡の旧郡域となっている。堺市東区のほぼ全域が丘陵地となっている。したがって住宅地や田畑がたくさん見られる。
堺市東区の北西方向から南西方向にかけて南海鉄道が走っている。また南海高野線北野田駅周辺は、商業の中心地となっていることから、いくつかのお店の姿を見ることができる。また北野田駅周辺はかつては別荘地として開発が行われてきた。
堺市東区は田園地帯が広がり、計画的に整備が行われてきたので、ここは閑静なベッドタウンとして人気が高くなっている。北野田駅周辺は高級住宅地として有名である。初芝駅周辺も日本の田園都市の一つとなっている。
堺市東区にはいくつかの施設や名所があり、出雲大社大阪分祠や野球場がある初芝体育館や天然温泉千寿の湯などがある。これは民間のスーパー銭湯となっている。このほかにはみの池運動公園や登美丘北公園などもある。
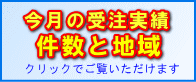
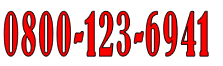
![]()

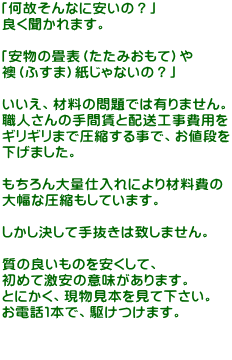
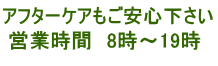
堺市東区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
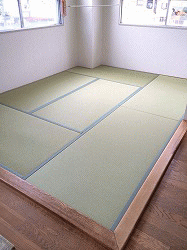
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
外国から伝わった文化をアレンジして使用することが多い日本ですが、畳に関しては日本独自の文化です。ただ、畳が現在のような形状になったのは、現在確認できる限りでは奈良時代であり、それ以前は現在のござのようなものであったと推測されています。
但し、形状は奈良時代に確立されていても、奈良時代と現代とでは使い勝手が異なります。当時はベッドのような寝具、あるいは座る際の座布団、クッションのような使用法でした。現代のように畳が床一面に敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代以降となります。
ただ、畳を使用していたのは身分の高い家でした。町人に普及し始めたのは安土桃山時代のことであり、一般的になったのは江戸時代の中期です。農村に関しては明治時代以降の普及となります。ですから、実は畳は一般人にとっては、まだまだ新しい文化だと言えるのです。
畳はメンテナンスフリーとはいかず、定期的なメンテナンスが必要となります。もちろん、掃除等といった日常的なメンテナンスも必要ですが、もっと大掛かりなメンテナンスも必要なのです。大掛かりなメンテナンスは裏返し、表替、新畳の3つです。
裏返しは、ござの部分を表裏逆にすることです。表替は、ござ部分を張替えることです。新畳は、すべて新しいものと交換することです。時期の目安としては、それぞれ新品の状態から、裏返しが3〜4年、表替が6〜7年、新畳が15年となります。