
大阪府堺市南区全域スピード対応!!

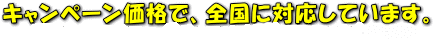



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
お客様のお話
高層マンションに住んでいるんですが、窓に網戸アミドがついてるんです。しかし、かなり高い層に住んでいるので、虫はこないんです。虫も来ないし、何か浮遊物がくる事も無いので、網戸アミドって何でついてるのかなって日々疑問に思っていたんです。しかし、低階層の住んでいる友人の家に行くと網戸アミドの重要性を感じました。ここまで虫が来ると思っていなかったです。夜にお邪魔をしたんですけど、部屋の明かりに吸い寄せられるように虫が大量にくるんですよ。大きな蛾や小さな蚊にハエや得体のしれない虫が数多く来ていたので恐怖を感じました。自分の住んでいる高階層では体験の出来ない数々だったので、網戸アミドの重要性を知ることが出来ました。滅多にというか一度も虫が来たことは無いんですけど、念のため網戸アミドをするようになりました。網戸アミドをすると風通しが悪くなるのかなって思っていたんです。しかし、風通しが悪くなった印象は無くて生活に不自由さを感じません。今までなんで網戸アミドを毛嫌いしていたのか自分でもわからないです。主人に話すと網戸アミドをするなんてそんな事当たり前だよと言われました。常識が無い人間呼ばわりされたので、大喧嘩になりました。今は仲直り出来ましたがあの時の喧嘩はかなりやばかったです。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸アミドは2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
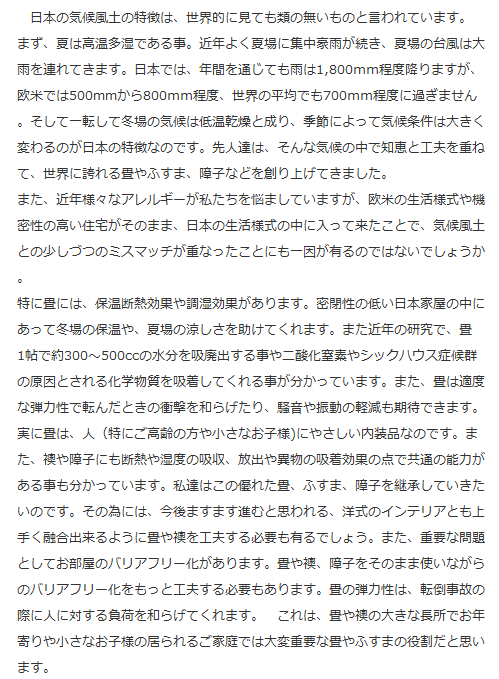
畳の変遷
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
網戸と蚊帳の共通点と張替え修理について
張替え修理をした網戸は機能性能を取り戻し、快適な住空間を支えてくれます。
網戸は、外部から虫などを入れないためのものです。 ちなみに、網戸の歴史のなかには蚊帳があります。 奈良時代よりも前に中国から伝わった蚊帳は、網戸の原型だといわれています。
また、戦国時代は身分の高い上流階級だけの贅沢品として利用されており、庶民が利用するのはまだ先の話しになります。 蚊帳が原型というだけに、網戸がなかったり、網戸の張替え修理を行わずにいることにより、様々なトラブルが発生してしまいます。
例えば、虫が自由に侵入してしまいます。 空気の入れ替えとなる換気も気軽に出来なくなったり、それによる温度調整も難しくなります。 穴が空いたままなら外から部屋の中が丸見えになってしまうこともあります。
網戸がない、張替え修理をしないだけで室内環境が大きく変わってしまいかねません。 張替え修理の目安となるタイミングとしては、網の状態によりますが、1年程度が良いでしょう。
ちなみに、業者に張替え修理を依頼すると、戸車の交換、網戸枠自体の交換も状況に合わせて提案してくれます。 海側、山側、川沿いにお住まいなどによってもトラブルは異なります。
塩害によるサビつきがあるなども、張替え修理の対象です。
| 無料お見積りはこちら |
堺市南区について
堺市に住んでからかれこれ今年で29年になります。簡単に自己紹介ですが、場所はずっと堺市南区で在住です。途中6年間北区(中百舌鳥)に住んでいました。小学校は地元の公立小学校、中、高校は堺区の上野芝にある賢明学院に進学しました。 こちらでは、交通便、教育(学校)、子育て中のママの気になる幼稚園情報、おいしい食べ物屋さん情報をご紹介させて頂きます。 交通便は、南区、北区、中区、美原区は、車が無いと大変不便かと思います。最寄駅の近くに住んでいたら特に不便はないかと思いますが、基本車での移動が多くなります。南区は特に坂道が多いです。最近では、高齢者の方向けのふれあい バスなどが充実してきました。南区の泉北高速鉄道線は特に電車賃は高いです。泉北線沿線に、平日10〜16時、土日に使用できる割引切符自販機が出来ています。それで往復分も購入できます。10〜20円ほどやすく切符が買え、 難波などに買い物に行く際にも利用できて大変便利です。 教育面ですが、堺市が主となる第8学区と昔学生時代には言われていた地域は特に教育熱心で、学習塾が多い地域です。 南区内は新設の学習塾が本当に多くなりました。電車で通う小学生も多いです。 幼稚園情報ですが、大きく分けて、公立または私立、そしてのびのび系とお勉強系幼稚園に分かれます。お勉強系では、賢明幼稚園が有名です。南区では香梅、青英、晴美台幼稚園です。堺市の各区役所で、『私立幼稚園ガイドブック』が配布されてますので、参考にされたらと思います。各幼稚園のくわしい方針や諸費用、園長先生からのメッセージなどが掲載されています。 おいしい食べ物屋さん情報ですが、ランチもディナーもやっているカフェでおいしいお店で、堺東駅近くの『グラン』、三国ヶ丘駅最寄の『茶倉』ランチで行きましたが、堺でとれたての野菜を盛り込んだ野菜中心のお料理が大変おいしかったです。堺では野菜がおいしいので、産地直送の野菜が食べられるお店は特におすすめです。 深井駅近くの『ナチュラルガーデン』バイキング形式でしたがここもおすすめです。子連れで行くと外食に気を遣いますが、こちらのお店はバイキングということもあって入店しやすく店員さんの対応も大変良かったです。店員さんの対応がいいとまた通いたくなります。 泉ヶ丘駅前の串カツ中心の居酒屋『万ぼう』は長年通い詰めてますが、味が何年経っても変わらず、子連れでも大人だけでも食事が出来て串カツが絶品です。串カツ用のたれは各個別に出してくれますので、安心して食べれます。家族でされているお店です。 大阪市にも近く、でも南部過ぎず、街も郊外もあって住みやすい街です。
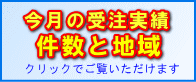
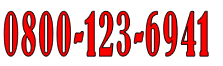
![]()

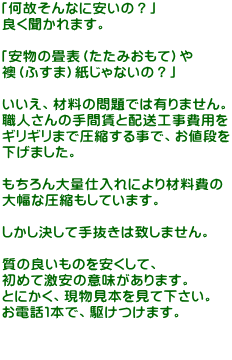
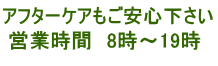
堺市南区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
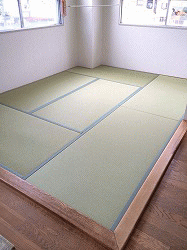
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
外国から伝わった文化をアレンジして使用することが多い日本ですが、畳に関しては日本独自の文化です。ただ、畳が現在のような形状になったのは、現在確認できる限りでは奈良時代であり、それ以前は現在のござのようなものであったと推測されています。
但し、形状は奈良時代に確立されていても、奈良時代と現代とでは使い勝手が異なります。当時はベッドのような寝具、あるいは座る際の座布団、クッションのような使用法でした。現代のように畳が床一面に敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代以降となります。
ただ、畳を使用していたのは身分の高い家でした。町人に普及し始めたのは安土桃山時代のことであり、一般的になったのは江戸時代の中期です。農村に関しては明治時代以降の普及となります。ですから、実は畳は一般人にとっては、まだまだ新しい文化だと言えるのです。
畳はメンテナンスフリーとはいかず、定期的なメンテナンスが必要となります。もちろん、掃除等といった日常的なメンテナンスも必要ですが、もっと大掛かりなメンテナンスも必要なのです。大掛かりなメンテナンスは裏返し、表替、新畳の3つです。
裏返しは、ござの部分を表裏逆にすることです。表替は、ござ部分を張替えることです。新畳は、すべて新しいものと交換することです。時期の目安としては、それぞれ新品の状態から、裏返しが3〜4年、表替が6〜7年、新畳が15年となります。