
堺市西区全域スピード対応!!
|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
昔ながらの網戸は目が粗いため、よく蚊の侵入を許してしまいます。しかし、最新のメッシュの細かいものは蚊はもちろん、花粉などのほこりの侵入さえも防ぐことができるのです。見た目は薄い黒布に見えるので通風性が悪いイメージがありますが、しっかりかぜを通すことができます。さらに雨の侵入も防げるので天候に関係なく窓を開けることができるのです。いままでずっと目の粗い網戸を使ってきたのであればメッシュの細かい網戸に交換することをおすすめします。そうすることで室内の虫の数とほこりの量を減らすことができるのです。空気清浄機を購入するよりも効率よく室内を綺麗にできるので、網戸にはしっかり気を使いましょう。古い網戸は見た目ではわからないほどに小さく破けていることもあるので気を付けるべきです。最新のメッシュのものは破けているとすぐわかるので、交換のタイミングもつかみやすいといえます。家の網戸を最新のメッシュに交換し、住環境をより快適なものにしていきましょう。子供やお年寄り、アレルギーもちの家族がいるのであれば特におすすめです。網戸は引き戸式が主流ですが、他にも様々な形のものが多くあります。住宅によって都合のいい種類が変わってくるので業者にしっかり相談すると、よりよい網戸を手に入れることができるでしょう。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
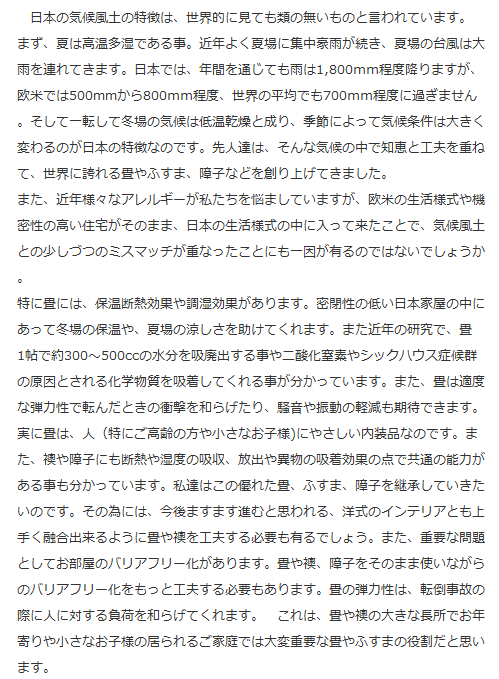
畳の変遷
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
| 無料お見積りはこちら |
襖は張替えによって機能性を保つことが出来る
自宅に和室があるという方なら襖も身近な存在ですが、その襖が機能性に優れた便利な建具であるという事を認識している方は少ないかもしれません。襖というのは平安時代に誕生した日本独自の建具です。元々は木の板に布や紙を張っただけのシンプルな物でしたが、時代が下るほどに構造が複雑化して、現在のように大きく分けて骨組みと枠に紙を重ね合わせて張り付けるという独特な構造の襖に変化しました。その構造上襖は見た目より軽量ですが、同時に内部に空気層が出来る事で温度を遮断する効果が一般的な板戸などに比べて高い事が知られています。また和紙が吸湿効果を持っているため、湿度が高い日本の気候において室内の湿度を一定に保つ効果もあります。物を保管する押し入れの戸としても、湿気を吸収するという効果はカビなどの発生を抑える効果が期待できます。これらの性質は古くなることで機能性が低下しますが、これも襖ならではの特性として張替えによって復活させる事が出来ます。張替えは文字通り襖紙を新しい物に張替える事を言いますが、襖の表面は糊で張り合わせてあるので、張替えに際しても骨組みや枠を傷める事無く、張替え作業を行う事が出来ます。これにより大切に扱えば何十年と使い続ける事ができ、張替えによって新品同様の状態を長く楽しめるように工夫されています。
障子の種類を知って最適な張替え方法を検討しましょう
障子を張替える時には、自分の家にある障子がどのような種類なのかを理解した上で張替え方法を検討するようにしましょう。種類によっては通常の張替えが困難な場合や、張替え方によっては問題が起きる事もあるのでよく確認しましょう。伝統的に日本建築で使用されている障子ですが、長い歴史の中で様々な種類が作られてきました。現在最も一般的とされるタイプが荒組障子です。組子と呼ばれる中央の格子状の木組み部分が広くとってあるのが特徴で、非常にシンプルで明るい見た目をしています。組子に使用する材が少ないので価格も安く、シンプルな見た目が現代的な住宅にもよく馴染みます。伝統的なものとしては横繁と竪繁といった障子が代表的です。横繁障子は横に渡した組子の数が多いタイプで、主に関東地方で使われます。一方の竪繁は縦の組子の数が多いタイプで関西地方でよく用いられてきました。他にも旅館などでよく見られるデザイン性の高い組子障子や、スクエア状の現代的な枡組障子など多種多様です。通常組子の数が増えるとその分紙を剥がした後の処理や、糊を置く場所が多くなるので張替えの手間はかかりやすくなります。また繊細な細工が施されている場合などは破損の危険もありますので、こうした障子の張替えの際には専門の業者に依頼して張替えてもらうようにするのが安全です。
障子は長い歴史と文化があり日本を象徴するものとしても知られていて、一般的な住まいで使われはじめたのが戦国時代ぐらいからであり、この頃より少しずつだけど色々な住まいで使用されはじめていった感じとなっています。
鎌倉時代から室町時代及び戦国時代の初期頃までは国人衆、大名、武家、公家などの身分の方が保有できるものとして使われていましたが、時代が経つにつれて徐々に一般的な住まいでも使われはじめていき、江戸時代に入ってから多くのところで障子を使い、張替えとか修理・修復などをする職人も全国各地に展開しはじめたとされています。
障子の張替えもこの頃から活発的に行われはじめ、製造技術・修理や修復の技術・張替え技術とかも進化していき、今に至る形となっております。
今の障子は色々な加工が施されていて、耐久性とかもあったりするので、長く使えるように設計がされておりますが、長年使っていると障子の張替えとかが必要となってくるため、ある程度ですが状態の良い時に張替えとかの対応を受けたほうが良く、使用している障子をそのまま使い施工を受けることができるためであります。
障子の張替えは専門業者に依頼を出すのが一番良く、チェックを受けた時の襖の状態によって施工方法とかも変わってくるため、ある程度ですが状態が良い場合は料金を抑えて施工を受けることが可能となっております。
状態が悪い襖になってしまうと全て新しいものとかに交換する必要があるため、襖本体の購入や襖紙とかの購入もしないといけないので、施工にかかる料金と合わせて、支払いをすることになるため、それなりに高くなってしまいます。
施工方法とか料金の相場とかはインターネットを使えばすぐに調べることができ、知識として覚えておくと良いので、一度ですが、検索してみることを推奨します。
網戸は長く使うと劣化するので数年おきに張替えしましょう
冬の間は使う機会が少ない網戸も春を過ぎて暖かくなってくると出番が増えてきます。そんな時に数カ月ぶりに網戸を見たら破れて穴が開いていた、というようなケースも結構あります。実は網戸の網というのは消耗品で、長く使って劣化してくると特に物をぶつけたりしなくても自然に破れてしまう事もあります。気づけばその都度張替えれば問題ありませんが、目立たない所が破れていると気づかないで使い続けてしまい、それが原因で虫が沢山入ってくるということもありますので気を付けましょう。そうならないためには劣化が出る前に張替えてしまう事が大事です。使用状況にもよりますが、網戸は5年から10年くらい使用したら、張替えたほうがいいとされています。特に日当りが良い場所や雨風の影響を強く受ける場所については、思っている以上に劣化が早くなりますので、張替えのスパンは短めの方が安心です。なるべく本格的に網戸を使用する事になる夏前に、一度破れが無いか網が弱くなってないか点検しておく事をお勧めします。網戸を張替えればそれだけ網戸の持ちがよくなりますし、換気の際の空気もリフレッシュして気分も一新できます。中には家を購入してからこれまで一度も網戸の張替えはしてないというご家庭もあるかもしれませんが、これを機会に一度網戸を張替えてみてもいいでしょう。
| 無料お見積りはこちら |
堺市西区について
堺市に住んでからかれこれ今年で29年になります。簡単に自己紹介ですが、場所はずっと堺市西区で在住です。途中6年間北区(中百舌鳥)に住んでいました。小学校は地元の公立小学校、中、高校は堺区の上野芝にある賢明学院に進学しました。 こちらでは、交通便、教育(学校)、子育て中のママの気になる幼稚園情報、おいしい食べ物屋さん情報をご紹介させて頂きます。 交通便は、西区、北区、中区、美原区は、車が無いと大変不便かと思います。最寄駅の近くに住んでいたら特に不便はないかと思いますが、基本車での移動が多くなります。西区は特に坂道が多いです。最近では、高齢者の方向けのふれあい バスなどが充実してきました。西区の泉北高速鉄道線は特に電車賃は高いです。泉北線沿線に、平日10~16時、土日に使用できる割引切符自販機が出来ています。それで往復分も購入できます。10~20円ほどやすく切符が買え、 難波などに買い物に行く際にも利用できて大変便利です。 教育面ですが、堺市が主となる第8学区と昔学生時代には言われていた地域は特に教育熱心で、学習塾が多い地域です。 西区内は新設の学習塾が本当に多くなりました。電車で通う小学生も多いです。 幼稚園情報ですが、大きく分けて、公立または私立、そしてのびのび系とお勉強系幼稚園に分かれます。お勉強系では、賢明幼稚園が有名です。西区では香梅、青英、晴美台幼稚園です。堺市の各区役所で、『私立幼稚園ガイドブック』が配布されてますので、参考にされたらと思います。各幼稚園のくわしい方針や諸費用、園長先生からのメッセージなどが掲載されています。 おいしい食べ物屋さん情報ですが、ランチもディナーもやっているカフェでおいしいお店で、堺東駅近くの『グラン』、三国ヶ丘駅最寄の『茶倉』ランチで行きましたが、堺でとれたての野菜を盛り込んだ野菜中心のお料理が大変おいしかったです。堺では野菜がおいしいので、産地直送の野菜が食べられるお店は特におすすめです。 深井駅近くの『ナチュラルガーデン』バイキング形式でしたがここもおすすめです。子連れで行くと外食に気を遣いますが、こちらのお店はバイキングということもあって入店しやすく店員さんの対応も大変良かったです。店員さんの対応がいいとまた通いたくなります。 泉ヶ丘駅前の串カツ中心の居酒屋『万ぼう』は長年通い詰めてますが、味が何年経っても変わらず、子連れでも大人だけでも食事が出来て串カツが絶品です。串カツ用のたれは各個別に出してくれますので、安心して食べれます。家族でされているお店です。 大阪市にも近く、でも南部過ぎず、街も郊外もあって住みやすい街です。
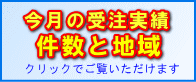
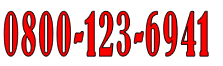
![]()

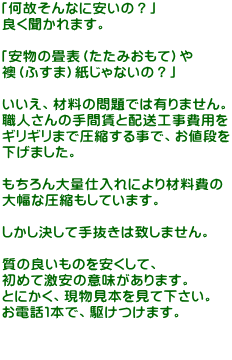
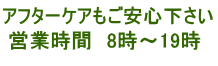
堺市西区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
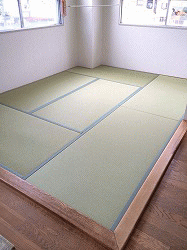
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
外国から伝わった文化をアレンジして使用することが多い日本ですが、畳に関しては日本独自の文化です。ただ、畳が現在のような形状になったのは、現在確認できる限りでは奈良時代であり、それ以前は現在のござのようなものであったと推測されています。
但し、形状は奈良時代に確立されていても、奈良時代と現代とでは使い勝手が異なります。当時はベッドのような寝具、あるいは座る際の座布団、クッションのような使用法でした。現代のように畳が床一面に敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代以降となります。
ただ、畳を使用していたのは身分の高い家でした。町人に普及し始めたのは安土桃山時代のことであり、一般的になったのは江戸時代の中期です。農村に関しては明治時代以降の普及となります。ですから、実は畳は一般人にとっては、まだまだ新しい文化だと言えるのです。
畳はメンテナンスフリーとはいかず、定期的なメンテナンスが必要となります。もちろん、掃除等といった日常的なメンテナンスも必要ですが、もっと大掛かりなメンテナンスも必要なのです。大掛かりなメンテナンスは裏返し、表替、新畳の3つです。
裏返しは、ござの部分を表裏逆にすることです。表替は、ござ部分を張替えることです。新畳は、すべて新しいものと交換することです。時期の目安としては、それぞれ新品の状態から、裏返しが3~4年、表替が6~7年、新畳が15年となります。