
堺市堺区全域スピード対応!!

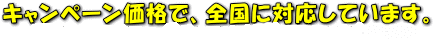



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |
(画像はイメージです)
最近では、高齢者が増えてきており、車の運転の事故も多くなってきています。そのため、車で買い物に行くことをためらい、必要なものが手に入らない、という環境になってしまっている場合があります。これは、ホームセンターでの買い物にも当てはまっており、DIY好きな人にとっては、つらい状況になっています。網戸を張替えようと思っても、網戸に使用する資材を購入することができない、ということで、時間はあれども遅々として進まない、という状況に陥っています。実際、自転車などで網戸の資材を購入しに行ったとしても、かなり、かさばることから網戸を持ち帰ることができない場合があるのです。誰かとともにホームセンターに行けば良いものですが、それまで車になっている場合、そういった関係作りも難しいものなのです。しかし、最近では、買ったものを届けてくれるというサービスを行っているところも出てきました。網戸のような軽くても、かさばるものはこういったサービスを利用することです。また、出向いて購入することができない場合は、網戸をネット上で購入することもできます。ネット上であれば、網戸の種類をじっくりと家にいながら選ぶことが出来、網戸のサイズがわからない時でも、その場で計測することができ、なかなか便利です。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
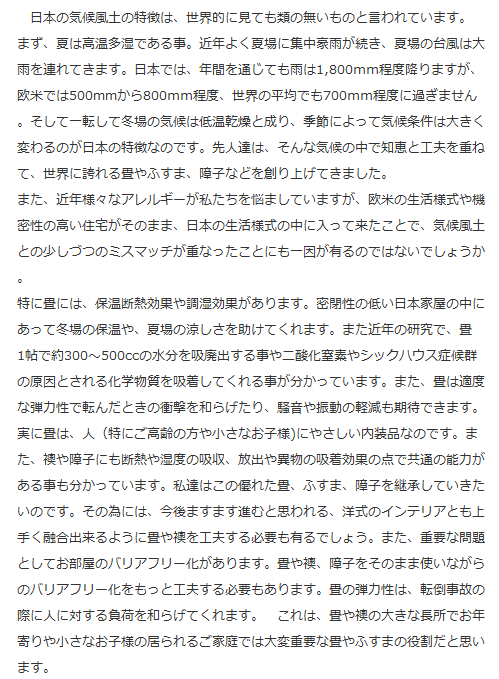
畳の変遷
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
| 無料お見積りはこちら |
和室に使用される襖の種類
日本家屋にかかせないのが和室になりますが、和室を作るために欠かせない家具は多くあります。畳や障子などもありますが、部屋同士の間仕切りや押し入れの戸として襖があります。戸に貼られている襖紙には様々な素材のほかに柄などもあるので、襖紙によって和室の雰囲気も大きく変わってきます。この襖ですが和室に使用する戸として基本的に2つの種類があります。まずは押し入れの戸として使われる本襖です。特徴としては襖の枠となる部分が取り外せるという点です。また本襖自体は軽いので、開け締めが楽に行えます。張り替え作業を行う場合は、枠を取り外す必要があるので、多少手間がかかります。もう1つの種類となるのが板襖です。部屋と部屋との仕切りに使われる戸となり、特徴として戸自体が本襖よりも重みがあります。また枠は取り外せないので、張り替えの際は枠からはみ出る部分は裁断して張り替えを行います。板襖には和室との仕切り戸で使用する場合と、洋室との仕切り戸として使われる物があります。洋室とのしきりに使われる戸の場合は、片面は化粧合板が貼りつけてあるのが特徴となっています。使用する場所によって様々な使い方ができるので、襖は便利な家具の1つと言えます。
襖の張替えでお部屋の模様替えが
襖というと柄が無地の白、もしくは和風の絵や柄が書かれているイメージがあります。そのため襖がある部屋では床をカーペットなどで洋風に模様替えできても襖がそのまま残っていては洋風にならないというイメージがあります。しかし現在襖に使用される紙に関しては従来の和風のものに加えて木目調やポップな柄や、無地でも青やピンクなどのカラフルなものもあります。そのため襖の張替えをするタイミングで洋風に適した襖にすることができます。この時にかかる費用ですが、洋風の柄やデザインであるからといって高くなるとは限らず、従来の和風の襖と価格に大差がないことも多いです。また張替えにかかる費用についても1枚当たり数千円とそれほど高くなく、枚数が多ければ多いほど割引をしてくれたりして他の室内の設備をリフォームするよりは安く済むこともあります。また張替えについて気になるのが仕上がりの時期ですが、一部屋に使っている分の襖であれば朝業者が引き取りに来て夕方張替えを完了したものを届けに来ることもありますし、業者が遠方であれば室内や家の敷地内で張替えてくれることもあります。いずれにせよ和風の部屋を洋風に変えるためには襖の張替えは欠かせないものと考えるべきです。
普段、優先的に気にすることがない網戸の張替え。そもそも網戸の役割とは何でしょうか?今回、その歴史とおすすめの張替え方法を紹介させて頂きます。 そもそも網戸とは、害虫などの侵入を防ぎながら、家の通気性も保つ、という居心地の良い生活を送るためには欠かすことの出来ないアイテムです。 日本は昔から木造住宅が多く、網戸などで虫やその他の生き物を防ごうという発想はありませんでした。虫よけの蚊帳などが有名ですね。そして、昭和から網戸が普及し、現在に至ります。もっと歴史が長い、と認識する方も多いと思いますが、網戸は、意外と40年から50年位前からしか使われていないのですね。 そして、網戸が普及してきたと同時に、張替えについて迷う方も出てきたのではないでしょうか。 冒頭でも記述しましたが、特に虫嫌いの方や、夏の暑さなどが苦手な方、家の空気を換気させたい方など現代の我々の生活には欠かすことが出来ません。 張替えですが、業者さんに頼むのが良いのでしょうか? 手先が器用な方は、自分で張替えをする、というのも良いかもしれませんが、このコロナ禍の中で生活習慣が大幅に変わった、と中々時間が取れない方などは、業者さんに頼むと良いでしょう。 身近な普段気にすることの少ないであろう網戸ですがそれを直すか直さないかで、このステイホームを快適に過ごせるかが決まってくるのかもしれませんね。
| 無料お見積りはこちら |
堺市堺区
大阪府内で第二の都市である堺市は、2005年に近隣の美原町と合併して、政令指定都市となりました。なお堺市の行政区は7つ存在しております。堺の歴史は古く、南北朝時代から商業の町として大きく発展を遂げて、一時期は東洋のベニスとまで言われるくらいに、大きな経済的な成功を収めた町になっています。そして堺市も現代では工業都市として、京阪神工業地帯の一角を占めるとても重要な都市なのです。また西日本の中心とも言える大阪市に隣接しているということもあり、特に大阪市中心部へのアクセスがとても良好で、ベットタウンとしての機能も堺市は果たしているのです。堺市の地形ですが、大阪湾に近い西部は平坦な地形になっており、閑静な住宅街が多く存在しています。また港湾地区には大きな工場や港湾設備など多く存在しております。堺市は一時期工場の夜景がブームになりましたが、この港湾地区にある工場群も、高速道路からの眺めが良く、良好な夜景スポットとして有名になったこともあります。堺市東部は丘陵地帯になっていますが、大阪市内へ直接行くことができる地下鉄があり、またその終端の駅から、鉄道が新たに引かれていることもあって、とても多くの人が住んでおり、またそれに合わせて商業施設も多いのも特徴の一つです。堺市中南部については、開発が遅かったのですが、ニュータウンの開発と鉄道の整備により、急速に人口を増やしてきているのです。さてその堺市の中心部と言えば、堺東駅中心となります。現在でも大きな百貨店が駅と一体になっており、さらにすぐ近くに大型の商業ビルが営業しています。また堺市の周辺の商店街は今も昔の趣を残しつつ、賑わいを見せています。なおこの堺の商店街は有名な男性デュオが、インディーズ時代に路上ライブを行ったところでもあり、特にその中にあるレコード店は、この男性デュオのアルバムに写真が使われているなど、ファンの中ではとても有名な商店街なのです。さてその堺市の観光スポットですが、自転車の製造が有名ということもあり、その自転車の博物館があったり、日本の松林100選に選ばれた公園などの自然も多く存在していますが、やはり古墳群を外さないわけにはいきません。特に日本で最大の前方後円墳である仁徳天皇陵には、その規模の大きさにきっと驚くはずです。また大阪南部で良く開催されているだんじり祭りも、この堺市でも行われています。大都市とはいえ、いろんな観光スポットやお祭りも多く存在する堺市は、観光先としても魅力的なのです。
堺市堺区について
堺市堺区は大阪府の西部に位置し、堺市の7行政区のうちの中心部である区です。堺市堺区は西区や北区、そして大阪市住吉区などと隣接する自治体です。総人口は約140000人で、周囲に掘を配する環濠都市となっています。堺市堺区には大仙陵古墳があります。日本最大の墳丘長で、仁徳天皇の陵に治定されていることから仁徳天皇陵とも言われています。堺市堺区の主要な観光地で、正面の拝所や二重濠の外側堰堤まで立ち入ることができます。堺市堺区の大阪湾に面する地域に、旧堺燈台があります。日本最古の現存する木製様式の灯台跡で、国の史跡に指定されています。明治10年に築造され、約1世紀その役割を果たしていました。今は堺市堺区のシンボルとして保存されています。堺市堺区は歌人である与謝野晶子が生まれた街です。生まれてから夫の鉄幹と結婚するまでの23年間を過ごしていた街です。現在では与謝野晶子生家跡として碑と歌碑が建てられています。また堺市立文化館には与謝野晶子文芸館があります。大阪府堺市は堺打刃物が特産で、堺市堺区にも数多くの歴史あるお店が残っています。堺打刃物は料理人が用いる包丁のシェアが9割にも上り、切れ味抜群で良質で有名です。堺の刃物の歴史は古く5世紀からで、江戸時代には他の産地のものと区別されるほど専売されていました。
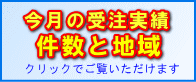
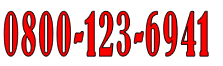
![]()

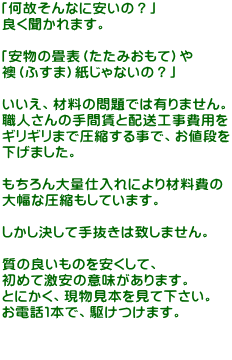
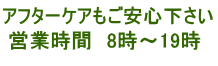
堺市堺区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
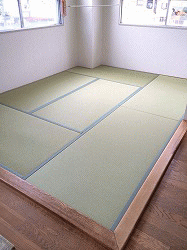
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
外国から伝わった文化をアレンジして使用することが多い日本ですが、畳に関しては日本独自の文化です。ただ、畳が現在のような形状になったのは、現在確認できる限りでは奈良時代であり、それ以前は現在のござのようなものであったと推測されています。
但し、形状は奈良時代に確立されていても、奈良時代と現代とでは使い勝手が異なります。当時はベッドのような寝具、あるいは座る際の座布団、クッションのような使用法でした。現代のように畳が床一面に敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代以降となります。
ただ、畳を使用していたのは身分の高い家でした。町人に普及し始めたのは安土桃山時代のことであり、一般的になったのは江戸時代の中期です。農村に関しては明治時代以降の普及となります。ですから、実は畳は一般人にとっては、まだまだ新しい文化だと言えるのです。
畳はメンテナンスフリーとはいかず、定期的なメンテナンスが必要となります。もちろん、掃除等といった日常的なメンテナンスも必要ですが、もっと大掛かりなメンテナンスも必要なのです。大掛かりなメンテナンスは裏返し、表替、新畳の3つです。
裏返しは、ござの部分を表裏逆にすることです。表替は、ござ部分を張替えることです。新畳は、すべて新しいものと交換することです。時期の目安としては、それぞれ新品の状態から、裏返しが3~4年、表替が6~7年、新畳が15年となります。