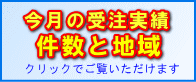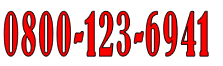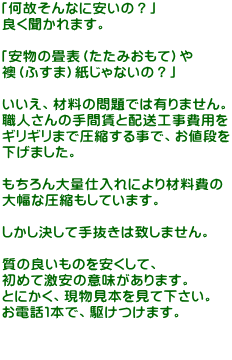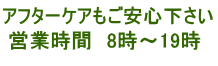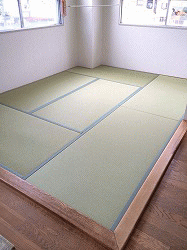小金井市スピード対応!!
企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。
関東圏、東京都、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。ペットディフェンスも扱っています。
高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。
業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、
皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。



(画像はイメージです)
現代の建築において、網戸が設置されていない住宅というのはほとんどないと思います。窓がないなら別ですが、開閉する窓が設置されている以上は通常網戸が設置されています。それほどまでに身近な建具である網戸ですが、専ら実用的な建具であるために普段顧みられる事は殆どないと言っても過言ではないでしょう。それはそれで正しい事です。実用的な建具である以上、人が意識してしまうような状態にあるというのは決して良い事とは言えません。ただその分メンテナンスがおろそかにされがちというのが、網戸の難点と言えます。ところが網戸というのは地味な見た目に反して、役割としては非常に大きなものがあります。というのも網戸は、住人の健康に大きな影響を与える存在なのです。具体的に言えば、網戸は虫の侵入を防ぐ建具です。虫、特に蚊の場合には不快なだけでなく、吸血に伴う感染症のリスクがあります。網戸というのは感染症のリスクを下げるという、非常に重要な役目があるのです。昨今では温暖化などの影響で、日本国内でも蚊が媒介する感染症のリスクが高まってきています。網戸も物質である以上、メンテナンスをしないと本来の役目を果たせない場合があります。異常がないか点検する位でも構わないので、たまに網戸の手入れをしてあげるようにしましょう。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。
まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。
そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。
また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。
特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300〜500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。
また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。
また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。
私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。
その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。
そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。
畳のメンテナンスについて
日本の住宅事情は昔とは全く違ってきています。
洋風の住宅が増えてきたため、床も畳からフローリングの部屋へと変化してきています。
それと共に畳の技術も進化してきて、洋風の部屋に合うようなカラー畳や置き畳などが登場しています。
フローリングの床にカーペットやじゅうたんではなく置き畳を敷いたり、洋室の一角に和室を設けたりなど、畳の良さが改めて見直されています。
その理由の一つには健康志向の高まりがあり、畳の健康効果が高いという点に起因しています。
たたみは断熱性と保温性があるため、冬場は温かく過ごすことができます。
フローリングだとどうしても足元が冷えてしまいますが、たたみだとその心配もありません。
また、湿度を一定に保つ性質を持っているので、機密性の高い洋風住宅で湿度コントロールの役目をしてくれます。
そして、たたみは空気中の有害物質を吸着する働きを持っています。
二酸化窒素やアセトアルデヒドなどの有害な物質を、たたみが吸着してくれるので、きれいな空気に変えてくれて健康的な生活を送ることができます。
また、新品のたたみのい草の香りにはリラックス効果があります。
このように健康に配慮された昔ながらのたたみの良さが見直されていて、洋風の部屋でも和モダンとして取り入れられています。
環境にも優しく、表面を張替えるだけで10年以上も使用することができるので、たたみを敷いているなら業者に定期的に張替えをしてもらって、長く使っていくのが大切です。
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
昔ながらの日本家屋はもちろんのこと、洋風建築が主流となった現在でも、畳が敷かれた部屋がある家はまだまだ沢山あります。畳は、断熱性や吸湿性があり、湿気の多い露の時期がある日本の気候にあった建築構造の素材の一つです。
たたみの構造と畳のメンテナンス
畳は、メンテナンス次第では、30年はもつといわれています。メンテナンス次第とはいっても、そもそもの構造をご存知でしょうか。畳床(たたみどこ)・畳表(たたみおもて)・畳縁(たたみべり)からできています。畳床は稲のワラで、畳表は天然の、畳縁は綿・麻・絹等の天然素材でできています。
たたみは表替えや、裏返しをする事で部屋の雰囲気を変える事ができます。たたみ表は、両面使えますから、裏返して、さらに数年したらたたみ表を新しいものに交換します。また、たたみがヘタってきたように感じたたら、たたみの交換時期でしょう。
何れのときも、へりは交換しますので、イメージチェンジするいい機会となります。へりの色やデザイン、素材を変えるだけでも、ずいぶんと雰囲気が変わるものです。さらに、和室には、襖とか障子がある場合がほとんどですから、そちらもメンテナンスすると、イメージを一新する事ができます。
ふすま紙を張り替えたり、障子を張り替えるだけでもすっきりとします。ほんの少しの手間と、お金をかける事で、まるでリフォームしたかのような、まるで新しい空間にする事も可能になります。センスのよい、モダンな和室に変身させましょう。
小金井市の人気の観光スポットについて
東京都の小金井市には、小金井市民や市外から多くの方が訪れる観光スポットがあります。それは、都立神代植物公園というところです。こちらの小金井市にある公園では、一年にわたって、きれいな花を観賞することができます。
園内は非常にきれいに整備されて、季節ごとの花を楽しめるようになっています。 特に小金井市の神代植物公園の見所は、5000株以上あるバラです。バラの見頃は5月下旬といわれ、その時期には多くの方が小金井市に観光に訪れます。
色々なバラの種類を堪能することができ、圧倒されます。その他にも、秋には紅葉、3月から4月の時期には桜を鑑賞できます。それ以外にも、温室には南国の植物も見ることができます。あまりにも多くの種類があるので、丁寧に見て行くと時間がたりなくなってしまいます。
展示内容が四季を通じて変わり、企画展も充実しています。 こちらの小金井市の神代植物公園は、広い芝生広場もあります。ですから、家族や友人とお弁当を広げてゆっくり過ごすこともできます。その他にも、高台にはカフェも開店しています。
ここでは、バラのソフトクリームやドリンク、ケーキが販売されて、休憩にぴったりです。たまには静かに過ごしたいというご家族には最適のスポットと言えます。興味がある方は、小金井市に遊びにいらっしゃると良いです。
小金井市のキャラクターである「こきんちゃん」
小金井市のキャラクターである「こきんちゃん」は、スタジオジブリの宮崎駿氏がデザインしています。宮崎駿氏は小金井市の名誉市民でもあり、ジブリ作品には小金井市にある実在の建物や場所が数多く登場しています。そんな小金井市の魅力とは何でしょう。東京の真ん中を東西に走る中央線沿線にある小金井市。1つ目の魅力は、アクセスの良さにあります。東京駅まで乗り換えがなく行けますし、東京駅までの途中駅で様々な在来線に乗り換え可能なので、非常に便利です。2つ目の魅力は、駅周辺の充実さです。駅前開発により、武蔵小金井駅周辺は大きく変わりました。南口には大型スーパーのイトーヨーカドー。北口にも大型スーパーがあります。また、駅にはnonowa武蔵小金井が開業し、より洗練された駅になりました。小金井市の再開発計画はまだまだ進行中なので、今後の発展が楽しみな街でもあります。3つ目の魅力は、自然環境の素晴らしさです。小金井市は、駅から徒歩15分くらいの場所に、都立小金井公園があります。小金井市のシンボルでもある桜。小金井公園の桜は都立公園で最大規模をほこり、春の桜まつりには多くの人が訪れています。このように、小金井市は利便性と自然のバランスを兼ね備えている街なのです。

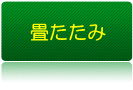
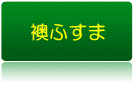
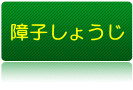
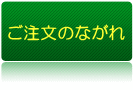
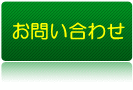




![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)