
全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

能美市全域にスピーディーに対応します!!



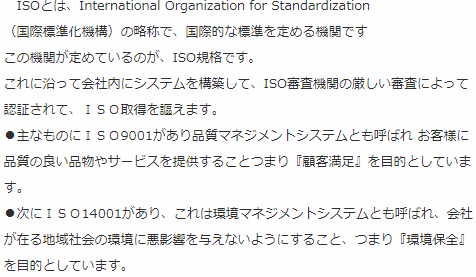
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)


網戸の張替えは、破れたらすれば良いという考え方の人が少なくありません。しかし、網戸の張替えをしようとしても、真夏の暑い時期に依頼すると専門店の人も作業が大変です。そこで、なるべくまだ暑くなる前に網戸の張替えを依頼するようにしていますが、必ずどの網タイプにするのか毎回確認が入ります。最初の頃は同じタイプの網で良いという話をしていましたが、サンプルを見せてもらうと蚊が入りにくい工夫を凝らした防虫性が高い網が登場していることを知って驚きです。
人間の目で見た時の網戸と虫の目線で見た時の網は必ずしも同じとは限らず、網戸の張替え後には虫の目線では壁に見えてしまう網戸が理想だと分かります。網目が細ければ良いという従来の考え方も大切ですが、そもそも張替えを行った後に快適性を求めるなら自然の風を感じたいと思っても不思議ではありません。網戸の張替えを行うならば、防虫対策可能な網を選択してみても良いでしょう。また、網戸は左右どちらの窓でも使えますが、右側の窓で使った方が良いと知らない人が少なくありません。虫が入りやすくなる部分は網目だけとは限らず、サッシ経由での侵入が多いと知っておくと良いでしょう。網戸の張替えを行う際には、機能性網戸の存在を知った上で依頼すれば、エアコンに頼りすぎない自然の風を感じられるようになるわけです。
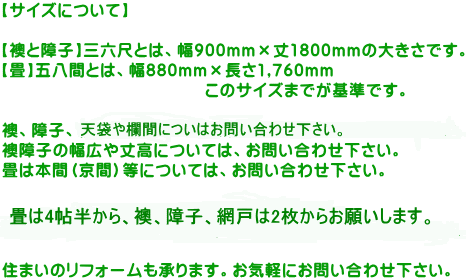
| 無料お見積りはこちら |
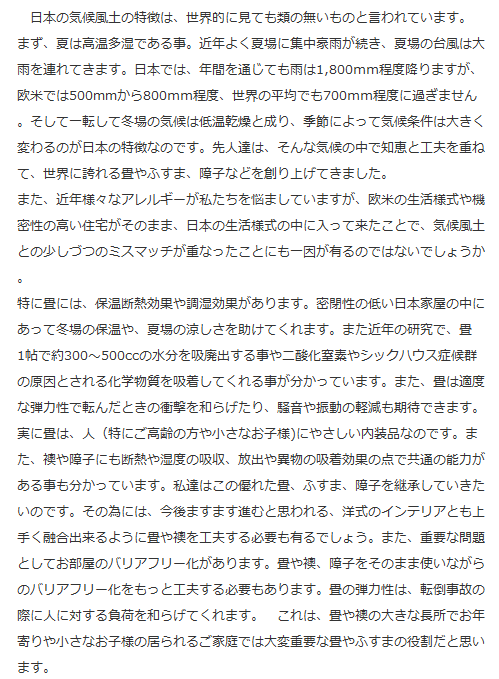
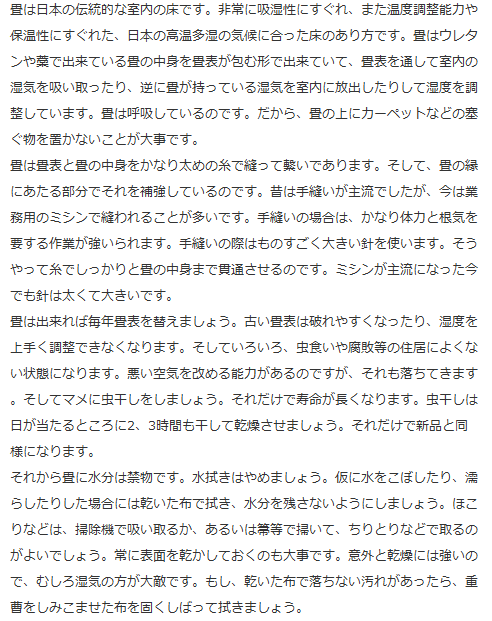
畳は日本で古くから使われています。フローリングとは違った魅力が沢山あるのです。畳のある生活は日本人の暮らしの中では当たり前の風景なのです。西洋化されてきている現在ですが畳は日本の気候や風土に合っているのです。
畳に使われているい草には様々な効果があるのです。ひとつは空気を浄化してくれる効果です。い草は空気中の有害物質を吸収してくれるのです。保湿や断熱性の効果もあります。い草の断面はスポンジのようになっていて適度な温度を保ちます。
部屋の湿度のコントロールもしてくれます。畳のある部屋の中が乾燥してきたら水分を放出してくれるのです。自然に湿度を調節してくれます。その為常に一定の湿度を保つ事ができるのでダニやカビから守ってくれるのです。
フローリングとは違って弾力性のある畳はお子様やお年寄りとても優しいのです。足に負担のかからない生活ができて発育期の子供のバランス感覚を養うのに効果的なのです。遮音性にも優れているため足音や声なども和らげてくれます。
畳は両面使用できるのです。片面の使用期間は大体5年程です。時期が来たら裏側に交換して再び5年程使用できます。両面使い込んだり、踏んだ時にへたってきたら新畳に交換する時期です。新畳のい草の香りでリラックスできます。
日本の住宅に欠かせないものに襖があります。襖は、下地の材質などで種類が別れています。木を格子に組んだものに、紙を何枚も重ねた下地のものを、本襖と言います。ベニヤなどの板が下地になっている板襖や、量産できる段ボール襖などがあります。襖紙にも種類があり、和紙と織物があります。和紙の襖紙は、鳥の子と呼ばれるものを使用します。材料によってランクがあり、安価なものは再生紙を材料としていたり、機械で漉いたものです。高級なものになると、手で漉いて作られています。織物は、使用される織糸の数によってランクが別れます。高級品は、天然の材料を使用して作られます。鳥の子も織物も、印刷や装飾によって価格が変わり、ランクに違いが出ます。襖紙の張り方の方法もいくつかあります。紙に糊が付いているものや、アイロンで張れるものがあります。注意しなくてはならないのが、下地の種類によって、張り替えができるものと、できないものがあることです。下地が、発泡材の襖は、アイロンを使用した張り替えは、溶けてしまう恐れがありましす。また、段ボールの下地では、張り替えをすることで、反ってしまうため、できないです。このように、下地と襖紙の相性などがあります。
| 無料お見積りはこちら |
能美市は、石川県南部の加賀地方に位置する市です。能美市の西部には日本海が面し、北部には手取川が流れています。その手取川の豊富な伏流水を利用する電子部品、繊維関連の企業が多く立地しています。能美市の現在の面積は83,85平方キロメートルで、総人口は49,071人です。
能美市は、能美郡にあった根上町、寺井町、辰口町の3町が合併してできた市です。根上町は、元内閣総理大臣の森喜朗氏や元メジャーリーグ選手の松井秀喜氏の出身地です。寺井町は、九谷焼や古墳群で有名です。辰口町は、辰口温泉といしかわ動物園があります。
「松井秀喜ベースボールミュージアム」は、能美市出身である松井秀喜氏の功績を残すための資料館として、父の松井昌雄氏が1994年に「松井秀喜野球の館」としてオープンさせました。2005年12月に、施設が狭くなったことから新たに新本館を建設し、この完成時に現在の名称に改称しました。
能美市で生産される九谷焼の歴史は、江戸時代初期の1655年(明暦元年)まで遡ります。加賀藩の命により、後藤才次郎は肥前有田で製陶を学び、その技術を導入して江沼郡九谷村で開窯したのが九谷焼の始まりといわれています。
能美市にあるいしかわ動物園は、1999年(平成11年)10月に開園しました。自然の地形をいかした中に植栽や岩、池などを配置し、動物たちの本来の生息環境に近い環境を再現しています。また、高齢者や身体障害者の方でも安心できるような設備があるのが、この動物園の特長です。