
大阪全域スピード対応!!

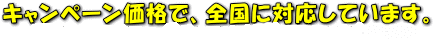



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。 ISOとは、International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称で、国際的な標準を定める機関です   |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
網戸もお安く!ペットディフェンスやマジックネットも用意しています!!
(画像はイメージです)
日本に於ける網戸の発達と現在
私たちの住まいには、欠かせないものとなったのが網戸ですが、意外とその歴史は浅くまだ50年ぐらいのものです。しかしその機能は目まぐるしく向上していて、虫自体を寄せ付けない網を使ったものやお部屋の中を見難くしたプライバシーを守るタイプのもの、極めつけはゴム系の素材を使いペットに破かれ難くしたもの(ペトディフェンス)などが開発されています。網戸は基本的にそれを取り付ける窓や玄関などのサイズや形状に合わせて作ります。洋服のイージーオーダーの様なものだと思って頂くと良いと思います。日本の昔の住宅は、囲炉裏やかまどの焚火などの煙で虫などを追い出していました。それを補う為に蚊帳等をつっていました。それらを使うことが少なくなってきた為に必然の要求として網戸が使われだし、発展してきました。初期の網戸は木枠に麻糸などを張ったものだったのですが、やがてアルミで枠を作るようになりました。(いわゆるアルミサッシです)そして網も塩化ビニール系のものからポリプロピレン系の素材へと変遷しました。このポリプロピレンは塩ビ系と違い焼却しても、有毒ガスの発生が少なく環境にも優しいと言われます。この網戸の普及は虫を媒介とする伝染病の防止にも役立っています。デング熱やジカ熱などの伝染病を予防する意味に於いても日本の住宅には欠かせないものに成っています。世界を見渡しますとまだまだ網戸の概念が普及していないため、蚊を媒介にした伝染病に苦しむ人々が多数います。最近では日本の網戸の技術は世界80ヵ国以上の国々に供給されています。
リビングや寝室の網戸を張替え忘れることは滅多に無いはずですが、意外と忘れがちな場所として浴室の窓が挙げられます。換気扇を普段は回してしまうので気づかないことが理由ですが、初夏の陽気で暑くて浴室の網戸を開けて家に刺された経験をした人もいるのではないでしょうか。その場では蚊に刺されていなくても、浴室を乾燥させるために開けっ放しにしたことが原因で、夜中に蚊が飛ぶ音がした経験はしたくないものです。訪問見積もりを行っている網戸張替え業者ならば、個別に浴室の窓はどうするか聞いてくれます。しかし、電話見積もりを行った場合の張替えは、到着後に指定された場所を確認して網戸の張替えを行う流れで間違っていません。
網戸の張替え業者が自ら浴室の網戸はどうしますか?と聞いてくれる場合もありますが、戸建ての場合には全部の網戸を一斉に張替えするとは限らないので、依頼があった場所のみの張替えを行って帰っても不思議ではないわけです。何度も依頼先で注文外の作業を確認することは、依頼者にとってはあまり心地の良いものではありません。そこで、やんわりと他に網戸があったら張替え予定はありますか?という丁寧な対応をしてくれた業者に対しては、感謝しかありません。
【サイズについて】
【襖障子、網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの
大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖ふすまの天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖ふすま、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。
まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。
そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。
また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。
特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300~500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。
また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。
また、襖ふすまや障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。
私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。
その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖ふすまを工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖ふすま、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖ふすまの大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。
そしてこの優れた畳、襖ふすま、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。
畳は日本固有の文化です
日本固有の文化である畳は世界でも類がない伝統的な床材です。その原点は古代から存在し、むしろやござなどの薄い敷物の総称です。使わない時は畳んで部屋の隅に置いたことから、「たたむ」が「畳」になったのが語源とされます。平安時代までは床に敷くクッションのように使われていましたが、室町時代では書院造の登場により、部屋全体に敷かれるようになりました。江戸時代になると畳が重要な建築物の一部として見なされるようになり、畳奉行なる役職も登場しました。畳の寸法には本間、京間、江戸間などがあり、最近の住宅で使われる和室には様々なサイズの畳があります。一帖を1.62平方メートル以上として和室の広さを表す基準としています。畳表の素材に使われるい草の香りは日本独特の文化の香りを象徴し現代でも和室は日本人にとってくつろげる場所の1つとなっています。時代とともに日本の住宅は欧米化が進み、和室がないマンションも出てきています。日本の伝統文化である畳を使った和室を見直すことで、昔ながらの生活スタイルを守ることで外国にはない良さを再認識し、日本を訪れる外国人の人たちに日本の良さをアピールできる要因の1つにもなります。訪日外国人が年々増えている今、日本の伝統を守り後世に伝えていくことこそが大切です。
畳を長持ちさせる方法
日本の家に欠かせないものの一つに「畳」があります。洋式の家屋が増えてきたため畳を部屋に敷き詰めることは少なくなってきましたが、それでも部屋の一部に敷いたり、数枚程度をクッションとして利用したりと現在でも広く利用されています。 普段何気なく使っている畳ですが、間違った使い方をしていると寿命を縮めてしまいます。例えば、畳は「湿気」に弱いという特徴を持っています。湿気の強い部屋に長期間置いておくとカビやダニが発生することがあります。定期的に部屋の換気を行ったり、年に1回から2回程度日光で干したりするとカビ・ダニ防止に効果的です。また、掃除を行う際には濡れた雑巾は使わず、掃除機か乾いたぞうきんを用いることが大切です。通気性を保持するため、畳の上にはじゅうたんなどを敷かないようにしましょう。 このような方法で畳を大切に使っていても、不注意で汚してしまうことはよくあります。例えば醤油をこぼしてしまった場合には小麦粉が役に立ちます。こぼした場所に小麦粉をふりかけて醤油を吸収させ、掃除機で吸い取ります。タバコを落として畳を焦がしてしまった際には、オキシドールを含ませた脱脂綿で漂白するのが効果的です。汚れや傷みがひどくなってきた場合には畳の業者に相談して修理を行ってもらうのがおすすめです。
| 無料お見積りはこちら |
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の心材(畳床)をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
畳をもっと生活に取り入れることで畳の良さを実感
畳は古くから日本の家庭などで愛されてきました。ほとんどの家は畳の部屋で構成され、家族が座って食卓を囲んだり、お客様をお招きして談笑する場でした。来客のための畳の部屋はお座敷と呼ばれることもあります。また、ご先祖様を大事にする家庭では、そういった部屋にお仏壇を置き、月命日にはお坊様にお経をあげてもらいます。夜には押入れから布団を取り出し、敷いて眠ることで疲れをとります。このように畳の部屋があるのは当たり前のことだったのが、最近では変わりつつあるようです。
畳に座って食事をとったりテレビを見たり、布団を敷いて眠りにつくという文化が、ダイニングテーブルで椅子に座って食事をし、ベッドで眠るという文化にとって変わられようとしています。そういう生活状態の変化とともに、フローリングの部屋が多くなってきたことで、畳の部屋はどんどん少なくなってゆきました。今では全く無いか、一室だけ客間としてあるだけというご家庭もあるほどです。幼い子供達は、家庭ではなく、幼稚園や公共の施設で接する経験しかない場合もあるそうです。
しかしここで考えていただきたいのは、日本人は外国人と違い、家に帰って靴を脱いで寛ぐ文化を持っているということです。外出先から戻り、玄関で靴を脱いでほっとすることは誰しも実感していることでしょう。そして、フローリングの部屋でソファなどがあるにもかかわらず、ソファを背もたれにして、じかに座って食事したり寛いだりすることが多い人もいるのではないでしょうか。日本人は結局のところ、畳に座って生活することが体に染み付いているのです。
フローリングの部屋でじかに座ると冷たかったり固かったりするので、たいていの人はカーペットを敷いたり、座椅子やクッションなどを敷いて座っているようです。畳の部屋なら、そんなものが無くともじかに座って寛げるのにと感じます。また、冬場の昔懐かしい光景に、コタツを囲んで家族が勢ぞろいし、みかんを食べるというものがありましたが、最近ではコタツを利用している家庭が激減しているそうです。家族が揃ってコタツを囲むことがなくなったのも、畳の部屋が無くなったせいでしょう。
畳には色々な精神的効果があります。普段畳の生活をしていない人なら特に、旅館などの畳の部屋に入った時、なんともいえないほどのほっとした感情を持つのではないでしょうか。畳が真新しい時は、そのいぐさの香りを心地よい匂いと感じる人も多いことでしょう。やはり日本人には畳は必要不可欠なものなのです。畳の部屋が欲しくてもいまさらそのためだけにリフォームなんてという人は、フローリングの上から好みのサイズで自由に組み合わせて敷くタイプのものがありますので、試してみてはいかがでしょうか。
掃除機を使用した畳のお手入れ方法
日本の一般的な家庭において、和室として畳を使っている部屋は多くあります。畳はい草独特の良い香りがし、肌触りなども柔らかいのが特徴です。フローリングに比べてクッション性の高いい草を使用しているので、小さい子供が遊ぶにも安心です。そんな畳を使用している和室ですが、日頃からお手入れとして掃除をすることが大切となります。目にはあまり見えませんが埃やゴミなどが溜まってしまうと、い草の劣化につながりあます。そのため日頃から掃除機を使用して汚れを綺麗にすることが重要になります。掃除機を使用して畳を掃除する場合ですが、掃除機をかける向きに注意することが大切です。畳の表面部分になるござには目と呼ばれる流れがあります。その畳の目の流れにそって掃除機をかけるようにすることがポイントになります。目にそって掃除機をかけると、よりい草の奥にある埃やゴミなどを吸いだすことができるので綺麗に手入れをすることが可能です。逆に畳の目に逆らった向きで掃除機をかけてしまうと、埃やゴミを綺麗に吸い取ることが難しくなります。また摩擦によってい草部分が擦れてしまい、毛羽立ちや劣化といった原因になってしまいます。畳の目の正しい向きに沿って、優しく掃除機を利用することが重要といえます。
襖ふすまは我が国固有の素晴らしい建具です
日本人に身近な建具の一つに襖があります。我が国で誕生して1000年ほど、生活環境が大きく変わった今日においてもいたるところで、現役で活躍しているまさに我が国を代表する建具です。そんな襖ですがどのような形で作られているのか、詳しく聞かれて答えられる人は少ないでしょう。表面上見える部分はまだしも、内部構造においてどのような仕様になっているのかは、意図的に調べようと思わない限り知る機会はないのは当然です。まず表面に襖紙が張ってあるのは、見れば誰にでもわかります。そして表面に見える部分では他に、襖を開け閉めする際の取っ手である引手があります。そして襖の周囲、四辺を囲むように角材の縁がつけられています。安価な工業生産品はこの限りではありませんが、伝統的な襖の場合は縁も外れるようにできています。芯材となる部分は障子のように格子状に組まれた木製の芯材があり、そこに下地から表の襖紙まで幾重にも紙が貼られています。表の襖紙を張るまでにどれほど紙を重ねるかは、種類やランクによって変わります。紙を多く張っていれば、襖自体の強度も上がります。詳しい話をするとややこしくなるので省きますが、少なくとも木製の芯材がありそこに何枚も紙を貼り重ね、そして表地となる紙を貼ったうえで縁と引手をつけたものが襖なんだと覚えておきましょう。
| 無料お見積りはこちら |
日本の気候風土に適した、襖ふすまふすま・障子の発達
建具として、家の部材に利用した、襖ふすまふすま、障子。木と紙や絹・布で作られたものが、日本の四季を通じて非常に柔軟に対応している。この発想が日本人の優れたところで、四季の変化が大きく、また湿度の変化も高いこの国の気候風土に適したものか、今さらながらに関心するばかりである。
唐渡りの屏風から思いついたのであろうが、それを折りたたまずに柱簡に嵌めこむことを思いつき、さらに上下に鴨居・敷居をしつらえ、そこに彫り込んだ溝に滑らせて、開け閉めの出来る工夫をしたのも、高床式の家の構造だったからこそ実現可能だったのだろうが、部屋の仕切りとしては、巧妙な仕組みであろう。さらに、それに絵を描く、あるいは文様のある唐紙を貼ることで、室内空間を飾る効果を作り出したのは、これだけでも日本人の美意識を物語る大きなテーマとなる。鉄・コンクリート・ガラスと言ったハードな材質による近代建築が、ここまで発達してしまった今日、どちかと言うとソフトな材質による日本独自の建築と内装を顧みるにつけ、驚くことばかりである。さらに、この建具ひとつを作る要した職人の手作業の細やかさにも驚かされた。骨組みの材を選ぶのにも気を配り、柾目を表んにして歪みの出ないようにし、下貼りの紙を貼るにも、その日の湿度・温度を体感しながら糊の濃さを調え、張っては乾かし、乾かしては張ってを繰り返しして仕上げるので、災害にあうかよほど手荒に扱わない限り、その上に描かれた四百年も前の顔料を厚く塗った絵画をほぼそのままに見る事が出来る。京都智恩院の長谷川等伯らの「桜・楓図」の壁画が、温度調節装置などを備えたコンクリートの収蔵庫に入れてからのほうが、顔料の剥落が激しくなった様に見える事にも、かっての職人の身に付けた業の確かさを思わざるをえない。
襖ふすま
襖はかなり古い時代から、日本家屋の間仕切りに使用されてきた建具です。空間を仕切るだけの目的ならば、木の一枚板で仕切るだけで十分です。しかし、わざわざ木と紙で作られた襖を使用することで、様々な恩恵を享受することができるようになっています。
まず、襖は何度でも簡単に張り替えることができますので、破れたり汚れたりしてしまうようなことがあったとしても、丸ごと交換する必要がありません。上張りの紙を張り替えるだけで、新品同様になるのですから、非常に効率的な建具です。
また、襖に描かれている模様を楽しめるというメリットもあります。水墨画のような絵柄の襖紙を使用すれば、グッと格調高い雰囲気の和室にすることができますし、幾何学模様などにすれば、モダンな雰囲気の部屋にすることが可能です。
さらに、木と紙という天然素材が持つ調湿機能や有害物質の除去機能は見逃すことができません。最近は住宅の気密性が高すぎるために、重いアレルギー反応に悩まされる人が少なくありませんが、襖には適度な通風性がありますので、アレルギーが出にくくなります。
一方、襖は、蝶番などで壁面に固定されているわけではありませんから、簡単に取り外すことができます。木と紙でできていますので、重量もあまりありません。必要に応じて部屋の広さを自由に変えることができますので、住まいの活用範囲がグッと広がります。
襖の張替えには適した時期と言う物が存在します。この適した時期を把握することで襖の張替えを専門としている業者の方に依頼を引き受けてもらいやすくなります。逆に言ってしまえば、適していない時期に襖の張替えを依頼すると断られることになるのですが何故適している時期があるかを説明します。まず、襖の張替えですが、時期は年がら年中張替えること自体は可能です。ですが業者の方が最も忙しいのは新しい月の初めである1月から8月が忙しくその理由は襖は空気が暖かいと感想が容易であるためこの時期の張替えは忙しいのです。逆に八月になりますと湿度が上昇するが故襖の張替えの依頼も減少します。この理由は障子と襖の構造が似ていることから障子のように襖も湿度が高いと綺麗に貼ることが出来ないのではないかと考えるため雨が増え始める8月以降はまず依頼者が減少するのです。その上でお勧めの時期が12月になり、この時期は空気が乾燥しており気温こそ低いが襖の張替えを行うに際して最も適している時期であると言えます。と言うのもこの時期は依頼者が減少する時期でかつ乾燥に時間が掛かる時期であるため襖の張替えに時間こそかかりますが、仕上がりにおいては梅雨の多い時期と比較して綺麗に襖を張ることが出来るので仕上がりを急がない場合お勧めの時期となります。襖の張替えには適した時期と言う物が存在します。この適した時期を把握することで襖の張替えを専門としている業者の方に依頼を引き受けてもらいやすくなります。逆に言ってしまえば、適していない時期に襖の張替えを依頼すると断られることになるのですが何故適している時期があるかを説明します。まず、襖の張替えですが、時期は年がら年中張替えること自体は可能です。ですが業者の方が最も忙しいのは新しい月の初めである1月から8月が忙しくその理由は襖は空気が暖かいと感想が容易であるためこの時期の張替えは忙しいのです。逆に八月になりますと湿度が上昇するが故襖の張替えの依頼も減少します。この理由は障子と襖の構造が似ていることから障子のように襖も湿度が高いと綺麗に貼ることが出来ないのではないかと考えるため雨が増え始める8月以降はまず依頼者が減少するのです。その上でお勧めの時期が12月になり、この時期は空気が乾燥しており気温こそ低いが襖の張替えを行うに際して最も適している時期であると言えます。と言うのもこの時期は依頼者が減少する時期でかつ乾燥に時間が掛かる時期であるため襖の張替えに時間こそかかりますが、仕上がりにおいては梅雨の多い時期と比較して綺麗に襖を張ることが出来るので仕上がりを急がない場合お勧めの時期となります。
外国人の目から見た障子
障子は日本の伝統的な建具であり、日本人から見れば特殊な存在ではありません。 しかし障子は日本独特の文化であり、他に似たようなものがないことから、外国人観光客の目にはかなり変わった存在として映ります。「木材と紙でできた家屋」というのは、日本人からすれば気候に合わせた住みよいものなのですが、欧米からやってきた人に言わせれば、「精神の壁」により構築されている異質な存在になるそうです。 これはヨーロッパの家屋が石やレンガで作られていたのとは無縁ではありません。彼らは物理的に破壊しにくい家屋を用いるのが当然であり、簡単に火がつくような家には住みたくないそうです。 そんな彼らからすれば、指先一つで穴が開く障子など、障壁にはならないと感じるようです。いざという時に、危険から身を守れないものなど危なくて使えない、というのが彼らの意見です。 しかし日本では襖や障子は壊してはいけないという暗黙のルールがあり、皆がそれを遵守していると聞いたときには、彼らの大半は先に記したように、障子に対し精神の壁との評価を与えました。 これは民族的な美意識に基づいて用いられるものであり、扱いとしては芸術品と同じなのだと解釈したのです。 障子は現在も様々な改良が加えられており、これからも日本人そして海外からの観光客の目を楽しませてくれるでしょう。
最近の日本家屋には、和室を有する物件が少なくなっています。畳の部屋よりもフローリングの方が好まれる傾向が強くなっています。しかし、逆に日本に住む外国人は畳の部屋を希望する人が増えているのです。それも、背の高い大柄な外国人の多くが畳の部屋を借りたいと希望するのです。このような傾向に、不動産業者も首を傾げたということですが、そこには意外な理由があるのです。その訳は、日本ではトールサイズのベッドが手に入りにくいという事情があります。背が高い外国人の中には、日本製のベッドが窮屈に感じるといいます。敷布団や掛布団は自分で何とかできても、ベッドは手作りではできません。そのような理由から、畳の部屋で布団を敷いて寝る生活を希望する人が増えているのです。そして、狭いアパート住まいの場合、布団を上げ下ろして部屋を広く使える畳の間の方が便利なのです。今では、日本人が忘れた畳の部屋の有効活用を実践している外国人が多いのです。已むに已まれず畳の部屋で暮らす人も多いのですが、畳を大いに気に入る人も結構います。日本での生活を終えて本国に帰っても、畳の部屋を用意するほどの熱の入れようだと言います。今や畳の人気は国際的に広まりつつあります。
和室用建具として障子はある意味ではセット共言える存在ではありますがその構成からどうしても傷み易く、更には人為的な負荷等によって容易く破れてしまう物でもあります。ボロボロに成った障子は見た目にも悪くそれを直す為には張替えと言った事を行うべきですが、機能と言った物を知ると如何にコンディションを整えて使った方が良いかも分る部分があります。障子に白い紙と言った物が使われているのは適度な明かりを取り入れつつも目隠しをする為であり、穴等が空いていれば当然用を成さない上にその他の利点も失う事と成るのです。多くの場合において障子はその使われている紙によって少なからず空気の流れを制御してもおり、これは湿気等を取ると言った役割も持っているので快適な空間を生み出す要素とも成っているのです。それ故に障子本来の良さを引き出す為には和紙と言った物を選んで張替えるのが最適で、近年に成って普及し始めている合成樹脂等の物は単に見た目のみだけと成るので良く考えて使う必要もあります。確かに現代では湿気の調整も家電によって理想的な状況に保つと言った事も可能とは成っている物の、省エネやエコと言った事を見直す場合はやはり障子の機能性に今一度注目する必要もあるのです。
 ペットが襖を破ってしまったら
ペットが襖を破ってしまったら
ペットが襖を破ってしまった」そんなことがあっても慌てることはありません。なぜなら襖は張り替えが可能だからです。張り替え用の紙が市販されているのでこれを購入すれば張り替えることが出来ます。張り替えの方法はその紙の機能によって変わってきますが、ノリや水、アイロンや粘着テープなどの種類があるので好きなものを選んで張り替えることが出来ます。また、古い襖紙を剥がしてから貼る方法と古い襖紙の上に重ねて貼る方法があります。重ねて貼った方が楽ですが、3枚程度しか重ねられないので注意が必要です。そして、ペットなどが破ってしまった場合はそこを補修してから貼り重ねるときれいに張り替えることが出来るでしょう。 襖紙は市販の襖紙を購入すれば張り替えることが出来ますが、これが面倒なら専門の業者に依頼するという方法もあります。依頼すれば古い襖紙を剥がしてから張り替えてくれるのできれいな仕上がりが期待できます。自分で張り替える場合に比べると費用はかかりますが、襖紙のバリエーションが豊富なので、オリジナルの襖をデザインすることも可能です。プロがきれいに貼ってくれた襖はきれいで見栄えが良く、とても丈夫なので、長く良い状態で保つことが出来るでしょう。
| 無料お見積りはこちら |
2025年に大阪万博が大阪市にて開催されます
大阪万博は2025年に再び日本で行われることが決定していて、いのち輝く未来社会のデザインをコンセプトに会場内には色々な施設や建物などを展開させ、海外の人たちも招き、盛大な万博イベントを行うことがで決まっているため、日本にとって大事な一大イベントの一つとされております。
ちなみに2025年の大阪万博に関しては会場が大阪府大阪市此花区で開催される予定となっていて、初日が5月3日で最終日が11月3日というロングランなイベントになるため、これは多くの人たちが足を運ぶことは間違いないと思っています。前回は大富豪が集まるドバイにてドバイ国際博覧会が開催され、そして今回が日本と決まった感じとなっています。また日本の後は2030年に国際博覧会が予定されているため、既に事業計画がたてられはじめている感じとなってます。
大阪万博といえば、 1970年に大阪府吹田市にて行われている一大イベントになっていて、2025年に開催されれば実に55年ぶりの万博開催となるため、日本もかなり気合いが入っていたりします。2025年の大阪万博は国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)が達成される社会と日本の国家戦略Society5.0の実現を目指して行われるものでもあるため、人々に豊かさをもたらす社会を目指そうという気持ちをこめてイベントが行われるようになっています。
大阪万博では現在密かにつくられている建物とか施設もあったりするため、お披露目が2025年になるという感じであるため、いまから楽しみであります。
大阪について、その歴史と現在の大阪市について
大阪という地名は、もともとは、大和川と淀川の間に南北に横たわる、上町台地の北端あたりをさし、古くは摂津国東成郡に属した。現在の大阪市のもとである、大阪の町は、古代の日本の最初の本格的な首都である、大化の改新の際の、難波長柄豊碕宮や、住吉津難波津を起源にもつ、歴史的な国際的港湾都市であった。江戸時代になると、日本屈指の大都市となり、日本経済の中心都市となった。15世紀に、「大坂」という名称で呼ばれるようになり、江戸時代の中期には、「大坂」と「大阪」が混在して使われるようになった。明治維新後の、1868年に、新政府がもとの大坂三郷に大阪府を置いたことが、「大坂」に代わって、「大阪」が正式な名称として使わはじめたきっかけであったといえる。明治維新の直後は、廃藩置県による、「大名貸」の貸し倒れや、地租改正による金納化によって、大阪の経済は大きな打撃を受けたが、経済産業が近代化するにつれて、次第に西日本の中心地としての地位を確立していった。現在の大阪は、関西の経済や文化の中心的な地域である。大阪府は、日本第3の都市圏にある愛知県を、域内総生産で上回っている。また、アジアのゲートと呼ばれている福岡県に対しては、福岡空港に対して、大阪の域内に存在する。関西国際空港が、国際線旅客数、国際貨物取扱量で、大きく上回っている。大阪市は、大阪府の府庁所在地である。政令指定都市に指定されており、近畿地方の行政、経済、文化、交通の中心地域である。サンフランシスコ(アメリカ合衆国カリフォルニア州)やサンパウロ(ブラジル連邦共和国)、ミラノ(イタリア)などと姉妹都市であり、香港やシンガポール、マニラやバンコクなどと、ビジネスパートナー都市となっており、各国の総領事館も多く存在するなど、国際的にみても、その存在は重要なものとなっている(平成25年のアメリカの調査によると、世界33位の金融センターと評価されている)。平成24年時点における、大阪市の人口は、2677375人であり、日本の中においても、大都市である。市内経済総生産は、約22兆円であり、近畿地方の経済圏の中心地であるといえる。大阪市を含め、大阪府全域が、瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖な気候であるが、夏場の暑さは、非常に厳しいものとなる。現在、大阪市は「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という理念の下で、市政の改革に取り組んでいる。
大阪はなぜ水の都と呼ばれているのか、その理由とは。
その昔、大阪は海の下に位置していた。海岸線は、平野のほうまで深く入り込んでいた。やがて、淀川が運んできた土砂によって湖ができ、その後新たな陸地ができた。これが、大阪の起源となる難波津である。難波津は、諸国の交易を盛んにし飛鳥時代まで栄えた場所である。その後、古代王朝は奈良や京都に都を移す時代が続き、そのせいで大阪が栄えることはなかった。しかし、海と川に囲まれた天然の要塞に恵まれた大阪に目をつけた武将がいた。それが豊臣秀吉である。海や川を活かして守りの堅固な城を築いた秀吉は、城下町を整備し、治水対策まで力を入れた。堀を掘った土が新しい土地を作り、それが繰り返されて町が整備されていった。整備された町は商人が行き交うようになり、大阪は栄えていった。江戸期までには15本もの堀が作られ、まさに水の都として大阪は成り立っていた。このように、水の都としての大阪は秀吉以降の都市開発も進み、全国一の交易拠点となった。これは北海道や江戸、畿内を結ぶ航路や、川を利用して京都や奈良に結ぶ航路もあったことが一つの要因と考えられる。しかし、水の都として栄えた大阪には水と闘ってきた歴史も忘れることはできない。台風の際の高波は、もともと海の下に位置していた大阪にとって危惧すべき事柄であり、それを避けるためにだんだんと都市を内陸へと移していった。近代に入ってからは、技術が発達してきたのでさまざまな水門を設けることでこれを回避することができるようになった。このように、大阪の人々は川に寄り添い、海を利用して都市として発展させていった。現代になり、都心部を回廊のようにめぐる川をまた利用できないか、と考えるようになった。世界で有名な水の都は、アムステルダムやベネチア、サンアントニオ、バンコク、蘇州などがあるが、都心部が川で囲まれた都市は大阪しかない。また、都市面積の10パーセントが水面という大阪は、やはり水の都といえるだろう。そこで、水の都、大阪の名を再び世に広めるために、様々なプロジェクトが開始された。水辺にシンボルを作り、さまざまな建築物のライトアップを目玉にし、また、船による観光などにも力を入れた。特に、水上バスやクルーズは人気を博し、多くの観光客が訪れるようになった。その結果、また大阪は水の都として世間に知られるようになった。昔から現在まで、大阪は水に寄り添い発展を遂げてきた。これからも水路を利用し、よりよい発展を目指している大阪。これが、大阪が水の都と呼ばれる所以である。
大阪市内がテーマパークです。楽しく面白い大阪
皆さんは大阪と言われたら何が思い浮かぶでしょうか。たこ焼き、お好み焼き、通天閣、海遊館など大阪には魅力がたくさんあります。見たり遊んだりするオススメの場所はたくさんあり、大阪城や道頓堀、海遊館にユニバーサルスタジオジャパンなど昔からある歴史を感じる所も様々なアトラクションがあるテーマパークもあります。まず大阪独自のものを感じたいなら大阪市南エリアに行ってみましょう。道頓堀には、よく見る大きな蟹やふぐの看板、さらにグリコのマークの看板など見所もあり、またくいだおれの街を体感できるでしょう。他に、大阪のシンボルと言える大阪城天守閣。元々の大阪城天守閣は豊臣秀吉によって本願寺跡に建てられましたが、戦や落雷により度々消失され、現在の大阪城は昭和6年に大阪市民の寄付により建てられたものです。大阪城天守閣に行き、戦国時代の建物の作りや天守閣からの大阪城下の眺めを楽しむというのはどうでしょうか。そしてもうひとつ、こちらもシンボルと言える万博公園にある太陽の塔です。1970年に開催された日本万博博覧会の為に、岡本太郎氏によるものです。ゆったりと緑の中を散歩というのも良いのではないでしょうか。万博公園までは阪急京都線と大阪モノレールで約40分です。そして、大阪の食べ物と言えばたこ焼きだと思います。色々なたこ焼きが食べ比べたい、そんな時は大阪たこ焼きミュージアムがオススメです。有名なたこ焼き屋が5軒揃い、他にもたこ焼きについて知ることができる場所です。さらに、その大阪たこ焼きミュージアムのすぐそばには日本で一二を争うテーマパーク、ユニバーサルスタジオジャパンがあります。ハリウッドの超大作映画をテーマに様々なアトラクションがあり、臨場感たっぷりなライドやショーに大興奮です。そのユニバーサルスタジオジャパンの海を越えた反対側には海遊館があります。巨大な水槽をぐるぐる回りながら降りて行くことで、様々な魚たちと会うことができます。中でも人気なのがジンベイザメです。巨大な水槽の中を悠々と泳ぐ姿は圧巻です。大阪と言えばお笑いも忘れてはいけません。なんばグランド花月で吉本新喜劇を見れば嫌なことも忘れて大笑いできますよ。なんばグランド花月は2012年にリニューアルされ、新喜劇を見るだけではなく大阪ならではの味を楽しむこともできるようになりました。まだまだ紹介し足りないほど所狭しと見所満載な大阪に、是非訪れてみてはいかがでしょうか。
大阪についてあれこれ考えてみました。
大阪の観光といったら通天閣、大阪城、新世界に万博公園。テーマパークでは海遊館に有名なユニバーサルスタジオジャパンまで幅広いジャンルを取り揃え、何日いても飽きない街大阪。そして誰もが知っているのは道頓堀でしょ。言葉だけで聞くと道頓堀ってなにそれと思うかもしれないけれど、グリコの大きな看板や、阪神タイガースのファンが飛び込んだりしてニュースになったのは道頓堀なんです。あー、知ってる知ってると思った方は一度大阪に行ってみたいですよね。
道頓堀はアクセスがすごく便利な場所にあるんです。電車から行きたいわという方は関東方面からも九州方面からも新幹線で新大阪で降りて、地下鉄御堂筋線に乗り換えて「なんば駅」ですぐの場所。遠方で飛行機からくる際には南海空港線の「関西空港駅」から「泉佐野駅」におりて、南海本線に乗り換えたら「なんば駅」でOK。もしくはJR関西空港線の「関西空港駅」から「日根野駅」まで行き、それからJR阪和線に乗り換えて「天王寺駅」へ。そこから地下鉄御堂筋線で「なんば駅」に行けちゃいます。
駅から出ると、そこで待っているのはあの有名な大阪の道頓堀。誰もが知っているその大阪ミナミに降り立つと、平日でも活気を帯びた商業地であることが分かります。そしてなによりお楽しみは大阪といえば「食い倒れの街」でしょう。道頓堀に行くまでにも周辺にはいろんなお店が沢山立ち並んでいます。少し足を伸ばすと黒門市場があるんです。商店街は生鮮食品だけじゃなく、食べ歩きも出来るグルメも取り揃えてあるんですよ。ちょっと大阪の人の台所を見るのも面白いですよ。
さて、メインの道頓堀。まずは大阪の食文化についてちょっと一言。大阪の人は食べるものを無駄にせず、それをいかに活かすかというバイタリティに溢れていたともいえます。大阪の醤油は薄口醤油と濃口醤油を料理によって使い分けるんです。意外なことに大阪は酒処でもあったので、良質なお酒を使って料理をし、そのお酒でおいしい食事をとることが出来たんですね。大阪近郊の海では豊富な魚介類、泉州地方の郷土の野菜等美味しい料理を作るのに適した場所でもあるんです。
では道頓堀のグルメといえば、有名な、かに道楽本店。ここで贅沢に新鮮なカニを食べちゃいましょ。大阪の名物お好み焼きとたこ焼きももちろんあります。数軒のたこ焼き屋とお好み焼き屋を食べ比べしながら歩いてみるのも楽しいです。ちょっと夜出歩いたなら居酒屋も豊富だし、1本100円前後の串かつをお酒と一緒にいかが。お子さんが、恋人が炭火焼肉が食べたい、ラーメン食べたい、お寿司食べたい、そんな贅沢を全て叶えてくれるのが大阪の道頓堀の街なんです。
キタとミナミ
大阪では、一般的にJR大阪駅・阪急・阪神梅田・曽根崎一帯をキタと言い、JR難波駅・南海電鉄ターミナルビル・道頓堀・千日前から心斎橋一帯をミナミと呼ぶ。
もとより厳密に分けられる地域ではないし、地名でもないが大阪人の間では日常的に愛称される呼び名である。キタとミナミはしごく対照的で、オツにすましたキタに対して、ミナミはいたって庶民的である。この愛称は古くから使われていて、もとミナミの島の門、それも六軒町あたりの遊里を言い、これに対して堂島新地(後に曽根崎新地に移転)を北の新地と言ったのに始まる。「芝居は南、米市は北」と江戸時代から人口に膾炙していた。ミナミの賑わいは、現在の道頓堀・千日前・花街の繁華街で代表され、心斎橋は東京で言えば銀座に当たり、大阪のニューモードの発祥であった。かっては、大丸やそごうと言った、その当時の流行の発信源であったデパートや暖簾を誇る老舗が軒を接していた。難波から千日前にかけての一帯がいわゆる「食いだおれの街」で織田作之助の「夫婦善哉」で有名な法善寺横町がその代表であろう。キタはいわば大阪の玄関口で、ビル街・娯楽街・郊外行き電車のターミナルから地下街とへと繁栄してきた。しかし時代の移り変わりと共にそれぞれの相違も少しづつ薄められつつあるようだ。
| 無料お見積りはこちら |
大阪は食道楽
大阪に旅行で訪問した際に、現地で食事をする機会がある場合、メリットを手に入れて選ぶ方法が存在します。大阪市において展開している飲食店をネットで探すとき、割引券やクーポンなどを使用できるところを選択するのです。割引券やクーポンを使用することで、飲食代金が安くなって支出を抑制できると言えるでしょう。従って、大阪市において食事をする場合には、そのような店を探していくことが手法となります。なお、大阪市の飲食店で割引券やクーポン券を用いる際には、使用における条件を確かめなければいけません。飲食店を利用する際には代金を支払わなければならないものの、次のようなケースがあるでしょう。それは、カードを用いて決済する方法や現金で支払う場合で、その時の状況に合わせて使うかもしれません。大阪市における飲食店でカードを使って決済するとき、次のような方法を考えていいでしょう。それは、支払いをすることによってポイントが貯まるシステムを組み込んでるカードを使います。以上より、大阪市に立地する飲食店で食事を行う場合には、カードを検討してもいいと言えるでしょう。なお、大阪市の飲食店でカード決済を選ぶ場合には、事前に限度額をチェックすることが求められます。このように、大阪市で食事を決断した際には、利点を獲得できる選択肢を考えていいでしょう。
大阪の多様な文化イメージ
大阪のイメージと言うと、食文化、漫才、落語、町工場、大阪人の性格等々多様な印象が世間にありますが、なかでも大阪市内と河川との関係は意外に歴史的にも密接な繋がりがあります。大阪市の地名には水や河川にちなむもの(船や橋など)が多くあります。難波、北浜、船場、淀屋橋、天神橋など水や河を連想させる地名であり、今でこそ、その面影は息を潜めておりますが、かつての大阪は舟が縦横無尽行き交うまさに「水の都」そのものでした。そうした河川や運河が交通の主要な手段であり、瀬戸内海各地や九州、さらには大陸との交易によって、大阪の産業を下支えしてきたのです。また、娯楽のひとつとして舟が使用されることも日常でした。遊覧用に造られた屋形船に遊山客が乗り込み、花見の名所などを川から眺めて楽しんだり、道頓堀の芝居見物も舟で行ったり、住吉大社や野崎観音などへの参詣にも舟は利用されていたそうです。しかし、戦後になって、陸上交通が台頭してきたことで、水上交通は衰退し始め、また工場から出される排水などによって、水質環境が悪化していきました。こうした河川の整備や水質問題に取り組むきっかけとなったのが、昭和25年に近畿地方や四国地方に大きな被害を与えたジェーン台風でした。海に面している大阪は、台風によってもたらされたダメージは大きく、多くの高潮被害を受けたことで、高潮の防御対策や環境整備のために、多くの河川が埋め立てられ、生活歩道などに変化を遂げていったのです。しかし、それでも現在(平成25年)の大阪市内では、33河川、総延長146kmに至り、大阪市の面積の約1割を水面が占めています。また、河川の水質改善や環境整備はさらに進められ、大阪の水をめぐる環境は劇的に回復しつつあります。そうした水都大阪をさらに促進させようと、大阪府や市だけでなく、経済界に市民やNPO法人等が加わり、人間活動としての河川を礎に美しい水都の街づくりが進められています。また、大阪市内の各地を舟で巡るクルージングも盛んに行われ、清涼感を味わいながら、大阪の街並みを川面から楽しめることができます。また、浪華八十八橋と呼ばれたほど橋の多かった大阪だからこそ、陸上では渡りなれた橋を下からくぐるのも楽しみのひとつです。こうした河川の整備により、大阪はかつて賑わいを見せた水の都に変化しつつあります。大阪に住む私自身、大阪の人々がもっと河川を身近に感じ、河川と共存することで、日々の生活がより豊かになることを期待しています。
大阪という地名は、もともとは、大和川と淀川の間に南北に横たわる、上町台地の北端あたりをさし、古くは摂津国東成郡に属した。現在の大阪市のもとである、大阪の町は、古代の日本の最初の本格的な首都である、大化の改新の際の、難波長柄豊碕宮や、住吉津難波津を起源にもつ、歴史的な国際的港湾都市であった。江戸時代になると、日本屈指の大都市となり、日本経済の中心都市となった。15世紀に、「大坂」という名称で呼ばれるようになり、江戸時代の中期には、「大坂」と「大阪」が混在して使われるようになった。明治維新後の、1868年に、新政府がもとの大坂三郷に大阪府を置いたことが、「大坂」に代わって、「大阪」が正式な名称として使わはじめたきっかけであったといえる。明治維新の直後は、廃藩置県による、「大名貸」の貸し倒れや、地租改正による金納化によって、大阪の経済は大きな打撃を受けたが、経済産業が近代化するにつれて、次第に西日本の中心地としての地位を確立していった。現在の大阪は、関西の経済や文化の中心的な地域である。大阪府は、日本第3の都市圏にある愛知県を、域内総生産で上回っている。また、アジアのゲートと呼ばれている福岡県に対しては、福岡空港に対して、大阪の域内に存在する。関西国際空港が、国際線旅客数、国際貨物取扱量で、大きく上回っている。大阪市は、大阪府の府庁所在地である。政令指定都市に指定されており、近畿地方の行政、経済、文化、交通の中心地域である。サンフランシスコ(アメリカ合衆国カリフォルニア州)やサンパウロ(ブラジル連邦共和国)、ミラノ(イタリア)などと姉妹都市であり、香港やシンガポール、マニラやバンコクなどと、ビジネスパートナー都市となっており、各国の総領事館も多く存在するなど、国際的にみても、その存在は重要なものとなっている(平成25年のアメリカの調査によると、世界33位の金融センターと評価されている)。平成24年時点における、大阪市の人口は、2677375人であり、日本の中においても、大都市である。市内経済総生産は、約22兆円であり、近畿地方の経済圏の中心地であるといえる。大阪市を含め、大阪府全域が、瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖な気候であるが、夏場の暑さは、非常に厳しいものとなる。現在、大阪市は「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という理念の下で、市政の改革に取り組んでいる。大阪という地名は、もともとは、大和川と淀川の間に南北に横たわる、上町台地の北端あたりをさし、古くは摂津国東成郡に属した。現在の大阪市のもとである、大阪の町は、古代の日本の最初の本格的な首都である、大化の改新の際の、難波長柄豊碕宮や、住吉津難波津を起源にもつ、歴史的な国際的港湾都市であった。江戸時代になると、日本屈指の大都市となり、日本経済の中心都市となった。15世紀に、「大坂」という名称で呼ばれるようになり、江戸時代の中期には、「大坂」と「大阪」が混在して使われるようになった。明治維新後の、1868年に、新政府がもとの大坂三郷に大阪府を置いたことが、「大坂」に代わって、「大阪」が正式な名称として使わはじめたきっかけであったといえる。明治維新の直後は、廃藩置県による、「大名貸」の貸し倒れや、地租改正による金納化によって、大阪の経済は大きな打撃を受けたが、経済産業が近代化するにつれて、次第に西日本の中心地としての地位を確立していった。現在の大阪は、関西の経済や文化の中心的な地域である。大阪府は、日本第3の都市圏にある愛知県を、域内総生産で上回っている。また、アジアのゲートと呼ばれている福岡県に対しては、福岡空港に対して、大阪の域内に存在する。関西国際空港が、国際線旅客数、国際貨物取扱量で、大きく上回っている。大阪市は、大阪府の府庁所在地である。政令指定都市に指定されており、近畿地方の行政、経済、文化、交通の中心地域である。サンフランシスコ(アメリカ合衆国カリフォルニア州)やサンパウロ(ブラジル連邦共和国)、ミラノ(イタリア)などと姉妹都市であり、香港やシンガポール、マニラやバンコクなどと、ビジネスパートナー都市となっており、各国の総領事館も多く存在するなど、国際的にみても、その存在は重要なものとなっている(平成25年のアメリカの調査によると、世界33位の金融センターと評価されている)。平成24年時点における、大阪市の人口は、2677375人であり、日本の中においても、大都市である。市内経済総生産は、約22兆円であり、近畿地方の経済圏の中心地であるといえる。大阪市を含め、大阪府全域が、瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖な気候であるが、夏場の暑さは、非常に厳しいものとなる。現在、大阪市は「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という理念の下で、市政の改革に取り組んでいる。
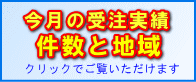
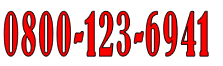
![]()

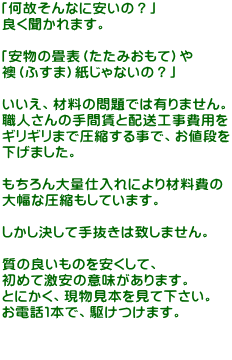
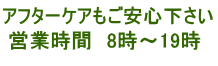
大阪全域迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
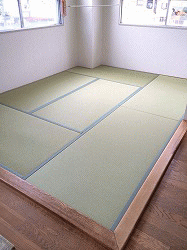
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
リニア新幹線開業後の大阪の経済の地盤沈下にどう対処すべきか
中央リニア新幹線は国の全国総合開発計画における整備計画路線としては東京と大阪の間を結ぶ路線であり、その施工主体は国であるとしていた。それが鉄道会社単独での施工に変わり、最初に名古屋まで部分開業として、その後に大阪まで延伸する計画に変更された。このことが大阪の経済にどのような変化を齎すのかを考えてみたい。新幹線には、経済活動を活性化させる作用があることは良く知られているが、地方の富を中央が吸収してしまう作用があることはあまり知られていない。つまり、名古屋部分開業によって、リニア沿線全体の経済力が上がることが期待できる一方で、名古屋などの経済力が相対的に低下する懸念がある。それは、首都圏に本社を置く会社が名古屋に支社機能を置かなくても良くなり、宿泊する観光客が減るからだ。新幹線の開業や乗り入れによって山形・長野などの経済が地盤沈下を起こしてしまったことも、これが原因である。そして、リニアの名古屋部分開業によって、東京・名古屋連合軍が大阪の強敵となって立ちはだかることになると予想される。それに次いで大阪までリニアが来ると、もちろん大阪の富も首都圏に吸い上げられることになるだろう。だから、リニアが大阪に来ることで大阪経済が大いに発展することはなく、東京への一極集中の度合いがより強まって、むしろ大阪経済の地盤沈下が予想される。しかし、大阪にリニアを通すことは国の総合交通体系構築上必要不可欠なことであるからには、リニア開業後の大阪経済が弱体化することを最低限度に抑制する必要がある。それに、リニアがずっと名古屋止まりであると、大阪は首都圏から半永久的に見放されてしまう危険もある。国の交通体系構築は、高速道路や新幹線を東京を中心に整備することによって進められて来たが、国や自治体の財源枯渇の状況からしても、大阪市を中心としたそれは在来鉄道線や一般道路に軸足を置いて整備するのが現実に適っているだろう。その方が庶民の街でもある大阪市と市民のキャラクターにも合致すると言うものだ。それに、大阪市は商業の街でもあり、一般市民も商業への関心が高いので、地元の公共交通機関を育てることが地域発展に効果的である。また、関東と関西の大きな違いは、前者は何につけても東京一極集中であるのに対して、後者は大阪市の他に京都・神戸などの数多くの極を持つことである。大阪人と京都・神戸人の気質は、ほぼ均質な関東の人々の想像を絶する相違があるが、それは、関西という狭い地域内での文化の多様性に起因するものであろう。狭い地域に多様な文化を包含する関西において、東京と同じ発想での経済の活性化を図るべきではない。複数の中核となる都市とその周辺地域とを密接に連携させることによってじっくりと地元経済を発展させてから、リニアを大阪に迎えるのが良いと考えられるのである。まずは名古屋開業までが第一の正念場であろう。
大阪という地名は、もともとは、大和川と淀川の間に南北に横たわる、上町台地の北端あたりをさし、古くは摂津国東成郡に属した。現在の大阪市のもとである、大阪の町は、古代の日本の最初の本格的な首都である、大化の改新の際の、難波長柄豊碕宮や、住吉津難波津を起源にもつ、歴史的な国際的港湾都市であった。江戸時代になると、日本屈指の大都市となり、日本経済の中心都市となった。15世紀に、「大坂」という名称で呼ばれるようになり、江戸時代の中期には、「大坂」と「大阪」が混在して使われるようになった。明治維新後の、1868年に、新政府がもとの大坂三郷に大阪府を置いたことが、「大坂」に代わって、「大阪」が正式な名称として使わはじめたきっかけであったといえる。明治維新の直後は、廃藩置県による、「大名貸」の貸し倒れや、地租改正による金納化によって、大阪の経済は大きな打撃を受けたが、経済産業が近代化するにつれて、次第に西日本の中心地としての地位を確立していった。現在の大阪は、関西の経済や文化の中心的な地域である。大阪府は、日本第3の都市圏にある愛知県を、域内総生産で上回っている。また、アジアのゲートと呼ばれている福岡県に対しては、福岡空港に対して、大阪の域内に存在する。関西国際空港が、国際線旅客数、国際貨物取扱量で、大きく上回っている。大阪市は、大阪府の府庁所在地である。政令指定都市に指定されており、近畿地方の行政、経済、文化、交通の中心地域である。サンフランシスコ(アメリカ合衆国カリフォルニア州)やサンパウロ(ブラジル連邦共和国)、ミラノ(イタリア)などと姉妹都市であり、香港やシンガポール、マニラやバンコクなどと、ビジネスパートナー都市となっており、各国の総領事館も多く存在するなど、国際的にみても、その存在は重要なものとなっている(平成25年のアメリカの調査によると、世界33位の金融センターと評価されている)。平成24年時点における、大阪市の人口は、2677375人であり、日本の中においても、大都市である。市内経済総生産は、約22兆円であり、近畿地方の経済圏の中心地であるといえる。大阪市を含め、大阪府全域が、瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖な気候であるが、夏場の暑さは、非常に厳しいものとなる。現在、大阪市は「成長は広域行政、安心は基礎自治行政」という理念の下で、市政の改革に取り組んでいる。
古来より大阪は”水の都”として知られる都市でした。人々の暮らしは古くより川に親しむものであり、水上交通の発展にともなって経済、文化ともに交易の中心として栄えてきました。現在、そのように、かつての大阪の、川辺、水辺とともにあった人々の暮らしや大阪特有の地形、土地性、人々がにぎやかに交流して活気のあったまちの有り様を見直し、再び取り戻し、また今後につなげていこうと、さまざまなプロジェクトが実施されています。「水都大阪」は、2009年にはじまってから人々のさまざまなネットワークがつながりあって、次第に大きく発展してきたまちづくりの構想とプロジェクトで、特に2011年に開催された「水都大阪フェス2011」で、より広く多くの人々に知られるようになった感があります。「めぐる・たのしむ・つなぐ・かんじる」をテーマに開催されたこの「水都大阪フェス2011」は、堂島川、土佐堀川、その川辺の各会場を中心舞台にさまざまなアートイベントや音楽ライブなどが開催されたり、飲食店が立ち並んでたくさんの来場者で賑わったお祭りです。期間中は、例えば、中之島公園のエリアでは、リバーサイドピクニックというイメージで、「アートピクニック」や「ボードゲームピクニック」「キャンドルナイトピクニック」「モーニングピクニック」など、テーマをそれぞれに持つピクニックイベントが行われていたり、船に乗ってバラ園や大阪のまちなみを鑑賞し、クルージングを楽しもうという「バラ園リバークルージング」や手漕ぎのゴムボートに乗りこんで「水上さんぽ」を楽しもうという「エコボートde水上さんぽ」など、川や水そのものを間近で体感したり、風景やまち自体を改めて見つめることができるような提案やユニークな試みが数々実施されていました。そして、水都大阪フェスティバルは2018年、2019年の開催へと引き継がれています。大阪の土地を私達の身近な生活という視線で見つめ、大阪という土地特有の文化やその背景にある水辺の暮らしに再び想像をめぐらせてみることができるようなプログラムが盛りだくさんであった「水都大阪フェスティバル」。ここで出会う人々のさまざまなコミュニケーションが今後いっそう活発化して、新たなつながりやインスピレーションへと発展していく機会として、未来への希望を感じさせるのが大変魅力的です。2019年も開催されますが、また恒例のフェスティバルとしていっそう人々に愛され、親しまれるようになることを期待したいお祭りです。