
堺市内全域スピード対応!!

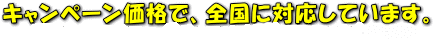



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。 ISOとは、International Organization for Standardization(国際標準化機構)の略称で、国際的な標準を定める機関です   |

| 無料お見積りはこちら |

![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
おしゃれな玄関網戸を楽しむ
網戸というのは、基本的に窓に取り付けるものだと考えている人は多くいますが、風通しの面で網戸を取り付けると良いのは、実は窓だけではなくて玄関です。玄関網戸というのはあまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、最近では戸建のリフォームの際に玄関網戸を取り付ける家庭がとても増えてきています。玄関網戸にするメリットはたくさんあり、最も大きなメリットは窓の網戸よりも数段風通しが良くなるという部分です。風の入り口である玄関に網戸を取り付けて、出口である窓にも網戸を取り付けておくと、開けている時に風の通り道がきちんとできるので非常に風通しがよくなります。風通しが良くなるとカビを防ぐ効果があります。そのため、家全体を快適な環境に変化させることができます。ただ、玄関の場合は網だとすぐに破けてしまったり、劣化が早いと考えられるので、網ではない形状のものを取り付けるようにすると長持ちするので、覚えておくと良いです。例えば、スクリーンなどを利用しているものもあるので、その場合は丸洗いをする際に洗いやすいため、取り扱いやメンテナンスがしやすいというメリットもあるので、どういったタイプが良いのかきちんと業者と相談する必要があります。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。
まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。
そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。
また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。
特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300~500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。
また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。
そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。
| 無料お見積りはこちら |
畳の変遷
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
畳(たたみ)は、イグサを編み込ん出来た敷物状の畳表(たたみおもて)で芯材になる板状の畳床(たたみどこ)をくるんで作る。縁には装飾を兼ねて、帯状の布を縫い付ける。畳には縦横比が2:1の長方形の一畳サイズと、これを横半分にした正方形の半畳サイズの二種類がある一畳サイズは三尺×六尺(910ミリ×1820ミリ)のものが基本となるが、部屋の寸法に合わせて注文生産されている為、サイズは一定していない。一般的な規格は、京間(本間)、中京間(三六間)、江戸間(関東間、田舎間、五八間)、団地間(公団サイズ、五六間)の4種類が有名である。その他にも地域ごと様々な規格が損祭する。畳の原点は大昔から存在する。現在の畳に近づくのは平安時代になってからであり、厚みが加わるとともにその大きさの規格化が進められている。平安時代までは板床に敷くクッションの一種の様な感覚で使われていたが、室町時代に入ると、書院造の登場により部屋全体に敷かれる様式があらわれ、茶道の拡大に伴い、正座とともに普及していった。江戸時代になると、重要な建築物の要素としてみなされるようになり、城や屋敷の改修工事を司る役職として畳奉行が任命される例もみられた
襖が破れたらすぐに直しましょう
和室にあるものと言えば、畳が真っ先に浮かぶでしょう。フローリングでは和室とは呼びません。しかし、和室には畳だけではなく、襖もあります。襖の柄次第で和のテイストが強くなったり弱くなったりするわけです。襖は紙ですから、破れやすいと言うのが特徴として挙げられます。破れても生活に支障はないでしょう。しかし、見た目によくありません。だらしない雰囲気が出てしまうと、せっかくの和室も台無しになってしまいます。襖が破れたらすぐに直す、これを基本としましょう。襖の修繕は業者に依頼しなくてもOKです。素人でもできるので心配はいりません。とくに、最近は襖の貼り替えをしたことがない人でも、失敗せずに貼り替えられるように便利なアイテムがあります。かつては、襖の貼り替えと言えばのりを塗る必要がありました。この作業は思いのほか面倒です。ですが、のり付きの襖紙を使えば、手間はかかりません。初心者でも難なく作業できるでしょう。ホームセンターで売られているので、入手するのも面倒ではありません。また、貼り替え作業にはいくつかの道具が必要になってきます。しかし、全て家にあるようなものなので、わざわざ買い揃える必要はないでしょう。
和紙以外の素材でできた障子紙について
障子に張られている紙は和紙であるのが当たり前だと思い込んでいる人が多いですが、近年になり、和紙以外の素材の障子紙が登場してくるようになりました。和紙には独特の風合いや高級感がありますが、いかんせん天然素材であるため、強度や耐久性があまり高くありません。もちろん通常使用に耐えられないほど弱いわけではありませんが、小さなお子さんやペットがいる家庭、不特定多数の人が出入りする場所などで使用する場合は、何かと問題が出てきます。そのような場所では、多少乱暴な取り扱い方をしても破れない強さが障子紙に求められます。また、汚れが付いてしまった時に簡単に拭き取ることができるようになっているのが望ましいです。そのような機能を持つ障子紙でないと、障子紙の張り替え頻度が高くなってしまい、費用がかさんでしまうことになります。 その要請に応えるために誕生したのが、和紙以外の素材で作られた障子紙です。少し突ついたくらいではビクともしない強度を持っていますので、まだ物心がつかない小さなお子さんや室内でペットを飼っている家庭などには最適です。また、汚れを水拭きできるようになっているため、長く美しい状態を保ち続けられるようになります。ちなみに、和紙の表面にコーティング加工が施された障子紙も販売されています。
| 無料お見積りはこちら |
花粉で悩んでいる方は網戸も気にする
花粉症の人は他の人よりも網戸の掃除をしっかりと行わなくてはなりません。春先に花粉で悩まされてしまう方が多いですが、他の人の症状が軽くなってきているのに自分の症状が軽くならないと悩んだ経験をした事がある方も多いでしょう。その方は網戸に原因があると覚えておくと良いです。網戸には大量の花粉がついてしまいます。花粉は非常に細かいので網目の小さい網戸を使用していても部屋の中に入ってきてしまいます。付着している花粉が自然に無くなっていく事はありません。ほとんどの場合は風が吹く事により部屋の中に入ってきてしまいます。そのため花粉の季節が終わっているのにも関わらず部屋の中に入ってきてしまいます。そろそろ花粉の時期が終わると感じた場合は、すぐに網戸の掃除をするようにしましょう。乾いたタオルなどで網戸を軽く拭いてみると黄色くなる場合が多いです。黄色くなった物のほとんどは花粉になります。一度網戸を洗うまたは網戸の拭き掃除を行って再度乾いたタオルで拭いてみると網戸についた花粉を取る事ができているのかを確認できます。花粉の症状が軽くなってきても外に出たくないと感じる方もいますが、自分が長く辛い思いをしないように網戸の掃除を頑張ってみると良いでしょう。
網戸はきれいに
かなり長いこと網戸を使っていると、知らない間になかなか洗ってもうまく取れなくなってしまうようなごみが詰まってしまうことがあります。この範囲が広がってしまうと、そのままにしておくと網戸としての効力が弱くなっていきます。汚い状態では、家の中に入ってくるはずの新鮮な空気も汚れてしまいます。このような状態のままで網戸を放置するのはよくなく、できるだけ早めに網戸の交換をすべきです。網戸の交換は、網戸の交換や障子の交換などを仕事としている業者がありますので、ここに依頼するのがよいでしょう。きちんとした知識があり技術力もありますので、丁寧な作業で交換してもらうことができます。あっという間に対応してもらえるので、プロへの依頼がベストです。最近は網戸の張替えが手軽にできるような道具も販売されていますが、素人ではなかなかうまく網戸を張り替えることはできません。交換するのであれば、綺麗に仕上げておきたいものです。ですから、プロへの依頼が理想的です。交換を専門としている業者がメリット性は高いのですが、最近は便利屋さんのような商売をしているところでも、網戸の交換程度の仕事はらくらく対応してくれるところもあります。
網戸の張替えを少しでも綺麗に
網戸の張替える理由は様々です。網戸が古くなったということもあるでしょうし、破損したなどの理由が多いわけです。さて、張替えるのであれば本体、つまりはフレームはそのまま使うことになります。それができれば、大分安くやってもらえることになります。自分で張替えることもできなくはないでしょうが、やはりプロによってもらった方が間違いなく綺麗にできるわけですから、そちらのほうがお勧めできます。プロでも基本的には網戸張替え方法というのは同じです。まずは網戸を綺麗にして、そして網を剥がしてそこに新しい網を合わせていきます。そして、枠に沿って嵌めることができるようになっている部分に専用のゴム状のものとかあるいはパッキンのようなものになっているやつをはめ込んでいくという形で網を張ります。張り替えの基本はこれだけなのでプロでも別にやることは同じなのですがピンと網が綺麗に張られているのかどうか、ということに違いがあるわけです。自分でやろうとするとさすがにそれが綺麗に出来ないということが多いわけですからそういう意味でもプロにお願いするという事の方がよいわけです。網戸の張替えは圧倒的に業者にお願いするとメリットがあるといえるでしょう。
| 無料お見積りはこちら |
堺市について
大阪府堺市は、数百年も前から海外との貿易を行っていた、経済の中心地として一時代を築いた歴史のある都市です。北は大阪市や松原市、西は高石市、南西は和泉市、東は大阪狭山市や富田林市、南東は河内長野市と接している政令指定都市です。2014年5月の調査で、大阪府堺市の人口はおよそ84万人となっており、大阪の南部地域における中核的な都市といえます。大阪府堺市は交通のアクセルにも優れており、大阪市や関西国際空港へ行くのにも便利な立地です。
大阪府堺市から新大阪駅へは、地下鉄御堂筋線、南海高野線の堺東駅から、およそ40分で行くことができます。また梅田へは、同じく堺東駅から、およそ30分で行けます。そして関西国際空港へは、南海線の堺駅からおよそ30分、大阪国際空港へは、堺東駅からおよそ50分で移動できます。大阪府堺市では、1993年に堺市景観条例を制定しています。これは大阪府堺市の景観の整備や保全を目的としたものです。素敵な大阪府堺市の景観形成を、包括的な構想をもって推進し、効果的な景観誘導を行う狙いがあります。
大阪府堺市は、地域まちづくり支援事業を行っています。これは自分たちの地域での身近な問題を、住民が主体的に解決する校区レベルにおける活動について、大阪府堺市が補助金を交付して、市民が参加する身近なまちづくりを促す事業です。これによって、自分たちの住まいの問題意識を多くの人が共有、解決するきっかけにすることが可能となります。そして、大阪府堺市に住むメリットとして、堺市特定公共賃貸住宅というものがあります。
この建物は法律に則って、大阪府堺市が建設した特定優良賃貸住宅です。地域のさまざまな賃貸住宅のニーズに対応し、大阪府堺市に住む人の生活の向上や安定の推進を目的としています。また単身者が申請できる住宅も、大阪府堺市では用意しています。2014年は、民間保育所緊急整備費補助金交付の申請も行っています。これは保育所の建物の改修や、耐震補強のための修繕に必要な資金を、大阪市堺市が一部交付するというものです。
大阪府堺市は、労働者を対象にした就職や雇用などの分野にも力を入れています。合同企業説明会や就職困難者のための就労相談、緊急雇用創出基金事業の他、無料でのメンタルヘルスケアの相談会なども実施しています。そして、2014年から消費税が5%から8%へ引き上げられ、所得の少ない人の負担を考慮する考えから、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金という給付措置も、大阪府堺市では2014年4月より臨時的に実施しています。
堺市の良いところについて
日本には数多くの隠れた秘湯や観光スポット、イベント開催地などがありますが、特に大阪府にも数多くの見どころがあり、その中でも堺市は色々と見どころのある街です。毎月何かしらのイベントが堺市各地で開催されているため、活気と賑わいのある街としても、この堺市は人々の心や記憶に残る印象深い地域なのです。地域に関しての情報は、地域住民の情報発信によって日本各地に広まっていますが、こと堺市に関してはより積極的な広報活動が行われているため、堺市に関する様々な豆知識やお得な情報を簡単に知ることができます。最近ではインターネット環境も改善されつつあるので、現代のネット世代の若者にとっても住みやすい地域として、堺市は若者の多い街となっていくことが予想されています。特に無線通信環境もショッピングモールを中心に充実され始めているため、堺市の外出先や買い物の途中などでも気軽に携帯端末からインターネットを楽しむことが出来るのです。このように人々の日々の平穏な暮らしを支えるさまざまな環境が充実していることが堺市の隠された大きな魅力で、今後もこういった大きなメリットが人々の生活に大きな利便性を与えることが期待されています。
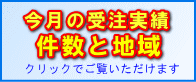
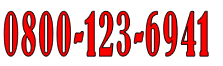
![]()

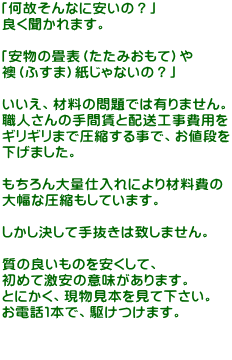
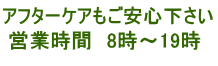
堺市迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
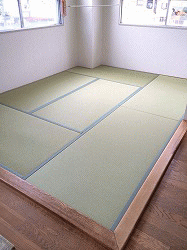
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S様邸 畳新調 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
日本の文化 畳たたみ
外国から伝わった文化をアレンジして使用することが多い日本ですが、畳に関しては日本独自の文化です。ただ、畳が現在のような形状になったのは、現在確認できる限りでは奈良時代であり、それ以前は現在のござのようなものであったと推測されています。
但し、形状は奈良時代に確立されていても、奈良時代と現代とでは使い勝手が異なります。当時はベッドのような寝具、あるいは座る際の座布団、クッションのような使用法でした。現代のように畳が床一面に敷き詰められるようになったのは、鎌倉時代以降となります。
ただ、畳を使用していたのは身分の高い家でした。町人に普及し始めたのは安土桃山時代のことであり、一般的になったのは江戸時代の中期です。農村に関しては明治時代以降の普及となります。ですから、実は畳は一般人にとっては、まだまだ新しい文化だと言えるのです。
畳はメンテナンスフリーとはいかず、定期的なメンテナンスが必要となります。もちろん、掃除等といった日常的なメンテナンスも必要ですが、もっと大掛かりなメンテナンスも必要なのです。大掛かりなメンテナンスは裏返し、表替、新畳の3つです。
裏返しは、ござの部分を表裏逆にすることです。表替は、ござ部分を張替えることです。新畳は、すべて新しいものと交換することです。時期の目安としては、それぞれ新品の状態から、裏返しが3~4年、表替が6~7年、新畳が15年となります。
襖の張替え
襖が家庭の中にあるだけで、その部屋はとても厳かな雰囲気になります。この襖はわが国に古くから伝わっておりますので、とても貴重な存在です。和室の部屋が家庭にあるところはまだまだ多いですが、昔は家の中にある部屋のほとんどが和室だったことを考えると、その数もだんだんと少なくなってきております。さて、襖がある部屋があるだけでもすばらしいことですが、せっかくある襖ですから、常にきれいにしておきたいところです。ですから、定期的に張替え作業を行っておくのがよいです。襖には保湿機能や調湿機能があります。ですから、新しい襖であれば、この機能をしっかりと果たしてくれます。専門の業者に依頼すれば、その部屋の用途にあった襖を提案してもらうことも可能です。ですから、単に張替え作業を依頼するだけではなく、そういったどんな襖が最適なのか、このあたりの相談もきちんと行っていくことができます。まず最初にメールで相談できる専門業者もありますので、気軽に問い合わせをしてみるとよいです。特に、エアコンを使用する季節であれば、新しい襖にしておくことで、その部屋の湿度もきちんと調節され、すがすがしい部屋で生活していくことができます。
 猫や犬など
猫や犬など
ペットを飼っておられる方へ
ペットを飼っている方にとって、畳やふすま、更に障子など和室で爪とぎをしたり粗相をしてしまうことは日常茶飯事といえます。定期的に張り替えてはいても繰り返される状態に、あきらめかけている方も少なくありません。しかし、頻繁に穴をあけてしまったり、爪とぎをしてしまって不快な状態になってしまうのを避けるための、丈夫なプラスティク障子や爪が滑りやすいように加工してある襖紙もあります。定期的に張り替えるとはいえども、破けにくいものを張り替えることによって、張替の頻度はずっと少なく出来ます。ペットのつめや小さいお子さんのいたずらで困っておられるならば、是非ご相談下さい。通常よりも快適にきれいな襖、障子に生まれ変わり、いたずらや爪あとに惑わされることなく快適です。