
全国の提携店とのネットワークで、全国にお伺い致します。
滋賀エリアスピーディーに対応します!!
郡部にもお伺い致します。



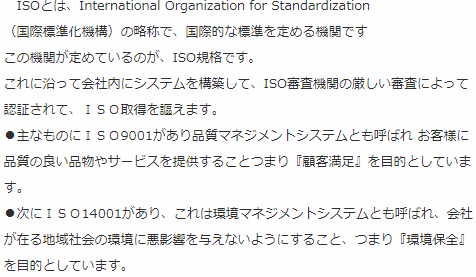
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)


実は優秀な網戸アミドの効果
現代において多くのご家庭に当たり前のようにある網戸。網戸はあって当たり前で、その効果について考えた事がない方も多いのではないかと思いますが、実は網戸は非常に優秀で便利なアイテムなのです。まず、網戸の役割として誰もが思い浮かぶのが虫の侵入を阻むということです。外気を室内に入れつつ、虫の侵入を阻んでくれるのは、地味なようでとても重要なことです。また、網戸が侵入を阻んでくれているのは虫だけではありません。ホコリや花粉などの微細なものをキャッチしてくれているのです。そのため、花粉の季節などには実は必須なのです。また、網目の細かいものなどは外から部屋の中の様子を隠してくれるという効果もあります。このように実は非常に優秀な網戸ですが、わりと破れてしまったり破損したりことも少なくありません。そういった場合には業者に依頼して張り替えてもらうという方法もありますが、よりお金をかないためには、自分で網戸の張り替えを行ってしまうというのがおすすめです。実は網戸の張り替えはご自宅でも比較的簡単に短時間で行うことができるので、休日の時間がある時などに、ネットの動画などを参考にしてチャレンジしてみるのが良いのではないかと思います。
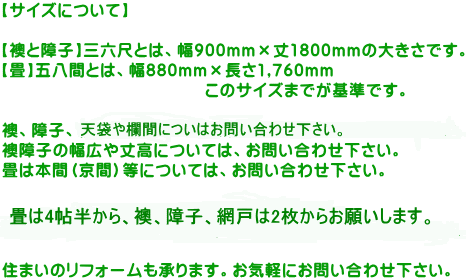
| 無料お見積りはこちら |
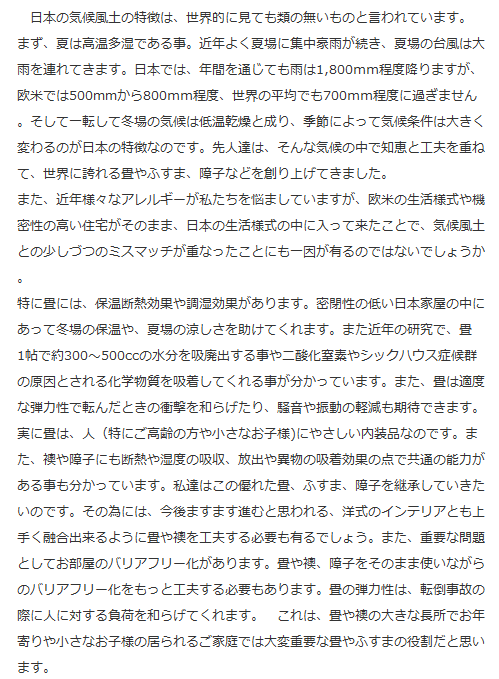
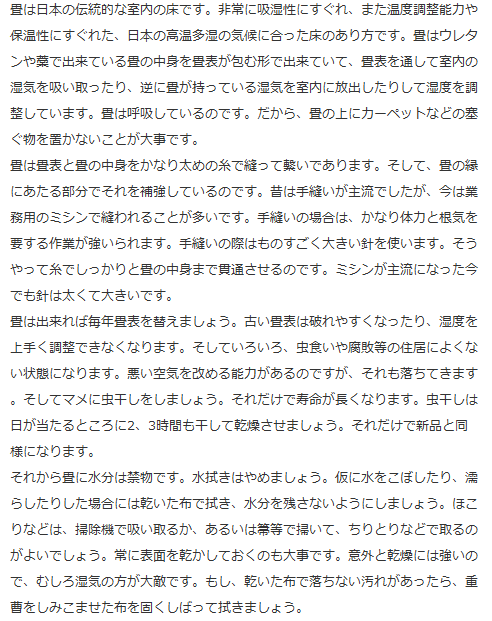
畳の替え時は2〜5年から始まります。新しい畳に替えてから1、2年経つと紫外線による日焼けや傷みなどが目立ってしまいます。すると最初に畳表を裏返しきれいにする表替えをします。早めに表替えしておくときれいな状態を保ちやすくなります。
また表替えをしていない場合5〜10年未満で傷みがひどくないのであれば畳裏返しができます。綺麗に使用していれば紫外線などの日焼けもしにくく劣化も遅いので十分使用することができます。ただ、10〜20年一度も取り替えていないと総取り替えになります。畳自体は長く持つものですが表面は頻繁に掃除していないとシミなどが目だちます。風通しが悪いとカビやダニが発生してしまうので手入れが必要です。表替え、裏替えするだけで新品の畳になったようになるので業者に頼むのがおすすめです。
畳の表替え裏替えなどを自分で行う人がいますが、業者やプロにお任せするのがおすすめです。なぜなら畳専用の糸で縫い上げなければいけないので、素人が自分で行うことは難しいです。糸を使わずに行う人もいますが、出来栄えが違います。
業者では、表替えなど一枚ずつの値段で表記されているので出来栄えの評判や値段をみてお願いする業者を選ぶのが良いです。出張料など含まれていない場合もあるのできちんと確認しておくべきです。お得に替えてもらえるところも多いのでぜひ頼むことをおすすめします。
昔ながらの襖と今の襖の違いとは
襖は日本独自の文化を持つ部屋を仕切る道具で、昔ながらの襖は何枚もの和紙を張り重ねられて作られています。そのため重ねられた和紙によって湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥時には湿気を放出する機能が働き湿度を一定に保ってくれます。そして、和紙は湿気だけでなく、空気中の化学物質を吸着する性質があります。さらに襖の下地は通気性がよく、湿度の調整ができるのでカビを防いでくれます。そのため、押入れの襖は押入れの中をカビから守ってくれるのです。その上、襖紙は手軽に張替えることができるので、リーズナブルにお部屋のイメージチェンジが行なえます。襖は日本文化の代表的な建具といえますが、最近ではさまざまな芯材の襖が登場してきました。内部構造(下地)の違いから昔ながらの和襖と量産襖の2種類に分類され完成品になると外見からは判断できませんが、耐久性や環境面でそれぞれに特徴があり、価格も違ってきます。後者は芯材を機械生産するため安く購入できます。また張替え時は襖紙をめくらずに上から重ね貼りをしていくことになります。そのため、シミが発生する場合があります。また、通気性や湿度調整機能は伝統的なものと比べると低くなってしまいます。
| 無料お見積りはこちら |
比叡山延暦寺
滋賀県大津市の北西方、京都との境に南北に連なる地塁山地、それが比叡山である。その山体の大部分が秩父古生層からなり、南部には花崗岩がみられる。山頂付近一部の急斜面もあるがは概して緩斜面をつくっている。最高点は京都市側の四明ガ岳の海抜848m。山上には、平安時代の初期、伝教大師最澄によって開かれた比叡山延暦寺がある。延暦7年(788年)南都(奈良)の仏法を修業した最澄が比叡山に登って比叡山寺を造立、自作の薬師如来坐像を安置、仏教興隆の祈願道場とした。これが後の一乗止観院、すなわち根本中堂の起こりとされている。薬師堂・文殊堂・経堂の3宇があり、本尊を祀る薬師堂がその中央に建っていたので、根本中堂と称したのだと言う。延暦23年(794年)京都に遷都した桓武天皇は、比叡山へ御幸し比叡山寺を都の鬼門鎮護の霊場に定めた。比叡山延暦寺は、天台宗門三大本山のひとつとされる巨刹で、堂宇は東部の東塔、西寄りの西塔、北部の横川の3地区に分かれ、さらにこれが東塔の東谷・南谷・西谷・北谷無動寺谷、西塔の東谷・南谷・北谷・南尾谷・北尾谷・横川の香芳谷・戒心谷・解脱谷・兜卒谷・飯室谷・般若谷の計16谷に分かれている。これを比叡山の三塔十六谷と呼ばれる。寺の盛時の平安後期の頃には、三塔十六谷に3000余の坊舎が満ちみちて、その勢威は白河法皇をして『加茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺の僧兵)は、これ朕が心に従わざる者』と嘆かしめた程であった。元亀2年(1571年)史上有名な織田信長の比叡山焼き討ちにより、全山焼き払われたが、江戸時代の初め、徳川家康の援助などによって復興された。巨杉に囲まれて建つ東塔の根本中堂や西塔の釈迦堂などの壮大な伽羅は、長い間仏教の霊地として敬われて来た歴史を余すこと無く伝えている。登山道としては大津市側には坂本から根本中堂に登る東塔坂、京都市側には白川道・雲母坂・走出道などがある。しかし昭和初年にケーブルカーが設置されてからは、登山道はあまり利用されることは少なくなっているようだ。今は四明ガ岳山頂には、自然科学館や高山植物園などを備えた遊園地がある。滋賀県側からは、日吉大社の門前町・坂本から表参道を経て、無動寺谷を通って登る登山道がある。山中には滋賀県大津市から京都大原方面へ抜ける東海自然歩道が通っている。
(滋賀県の近江商人)
風土記の逸文にこうある。「近江の国は、淡海を似ちて国の号を為す。故にまたの名を細波の国と言う。目の前に湖上の漣を向い観るが故なり」近江一国が巨大な盆地であり、盆地の中に大きな淡海が横たわる・淡海は一方でくびれ、その姿が琵琶に似ているところから、何時の頃からか琵琶の湖と呼ばれ、名付けられた。国内いたるところから静かな海を観る事が出来る。時には一杯に広がりをみせ。時には山の合間にほにみえる。昔も今も変わりなく、近江はまず淡海の国である。県面積の6分の1を占める琵琶湖はよきにつけあしきにつけ、近江の人々の生活を人情をあるいは文化までをも左右してきた。東海道を旅する人々は、車窓から見える琵琶湖の美しさに感嘆する。国境の山々を添景に静かにたゆう湖を見る時、誰しもふと、この地に降り立ちたい衝動にかられる。周囲の山地に囲まれた近江盆地に入るにはどの方向からきても、峠かトンネルを越さねばならない。歴史に名高い3つの関所、愛知の関を通るのは北陸本線、不破関を通るのが東海道本線、そして国道1号線は鈴鹿関を通る。京都からの入り口には、歌に詠まれた逢坂の関があり、峠を越せばもう湖国である。湖と山とで織りなす風景は旅人を深く魅了してやまない。古来、今の滋賀県、近江国は北陸、東山(中仙道)東海の東国3道がことごとく集まる交通の要路に位置した。旅人達の多くは近江の土を踏んだ。長い旅路の途上で静かに横たわる琵琶湖がどれだけ心の慰めになったか計り知れないものがある。しかしそれが逆に、いわゆる通過地の宿命を与える結果となったのも否めない。滋賀県に独自の文化の定着が比較的少ないと言われる結果となったのも、ここに理由があるのだろうか。この傾向は政権争覇の上でも顕著に現れる。今の滋賀県、おうみは、いたずらに戦場となる事のみ多く、天智天皇の大津京も織田信長の安土城も激しい戦火の中に消え去った。今の滋賀県は物資の集散地だっただけに、近江の人は早くから他国の人情や文化に触れることが多かった。地形的には盆地の中に位置しながらも近江商人が開明的だったのは、このためで多くの、近江人も自ら行商人となって他国に旅立って行った。天下に知られた近江商人はこの様にして生まれた。
滋賀県竜王町のケンケト祭
竜王町山之上 杉之木神社で毎年5月3日に行われます。織田信長が甲賀水口での戦いで従軍した、この地方の人々が鎧を脱いだ装束に倣った格好で踊られる薙刀踊りが奉納されます。名称は踊りをはやす音頭から来たと言われています。
最近では少なくなってきていますが、襖がある住宅はまだまだたくさんあります。襖と一言で言っても、種類があるんです。構造による違いがあります。昔からある本襖は、木を格子に組んだものに、紙を何枚か重ねた状態の下地になっています。張り替える時は、古い襖紙を剥がして新しいものを張ります。下地に板を貼ってある、板襖というものがあります。これは、張り替えがしやすい特徴があります。
建材ふすま
下地を発砲材にしたものや、段ボールのものもあります。これらは、量産でき、かつ軽量であるメリットがありますが、基本的に張替えは出来ません。
襖紙にも種類があります。鳥の子紙という襖紙があります。ランクが分かれていて、最高級品は手漉きで作られています。それより下のものは、機械によって作られていて、材料も再生紙を使用しているものがあり安価です。その他に、織物の襖紙があります。こちらも、ランクが分かれていて、高級なものは、天然繊維で作られています。紙に比べて織物の方が丈夫である特徴があります。張り替えの方法もいくつかあります。糊を刷毛で塗って張り替えるものや、アイロンを使用して張り替えるものや、両面テープを使ったり、シールタイプのものもあります。最近では壁紙を襖に利用するなど、自由でインテリアを重視したものも増えています。
大津市・ 彦根市・ 草津市・ 東近江市・ 長浜市・ 甲賀市・近江八幡市・ 高島市・ 守山市・ 栗東市・ 湖南市・ 野洲市・米原市・ 日野町・ 愛荘町・竜王町・ 木之本町・ 安土町・高月町・ 多賀町・甲良町