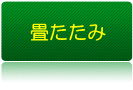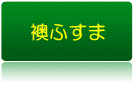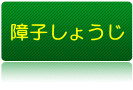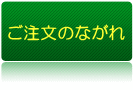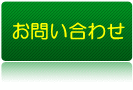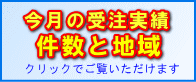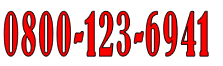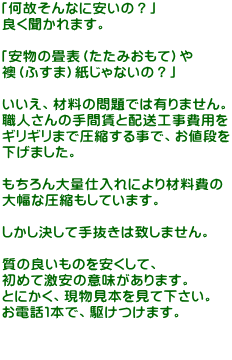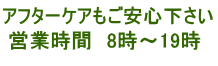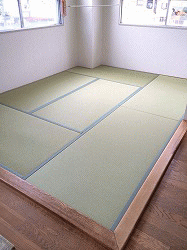横浜市内スピード対応!!
企業努力で全国でも仰天の激安価格、料金を実現しました。
関東圏、神奈川県、関西圏から全国が施工エリアです。

襖ふすま、障子、網戸アミド、畳たたみの張り替え交換修理修繕と新調。ペットディフェンスも扱っています。高い品質と確かな施工を維持しつつ、驚きの張替え価格、料金を実現しました。業界トップクラスのスピーディーな対応と無料お見積りで、
皆様に喜んで頂ける、安心安全施工をお約束致します。



|
弊社では、輸入畳たたみ表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。 ISOとは、International Organization
for
Standardization(国際標準化機構)の略称で、国際的な標準を定める機関です   |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
網戸アミドに気を使って室内のほこりを減らす
網戸は羽虫の侵入を防ぐだけのものと思っている人が多いですが、それは昔の情報です。今の網戸は高機能なものが数多く存在し、住宅のほこりを減らすことができます。ほこりは主に微生物や花粉、砂や土などで構成されていますが、これらをメッシュの細かい網戸でシャットアウトすることが可能です。見た目薄い黒布に見えるほどに細かいメッシュの網戸は花粉や砂などの侵入を防ぐことができ、なおかつ風邪をしっかりと通すことができます。空気清浄機とあわせてメッシュの細かい網戸に張り替えることによって、室内のほこりはかなり減っていくのです。今まで古くてメッシュの粗い網戸を使っていたならばホームセンターなどで張替えてもらうといいでしょう。自分でも張替えを行うことはできますが、少し隙間ができてしまうとそこからほこりが侵入してしまいます。プロの手で確実に網戸を張替えてもらうと安心です。最新の高機能網戸に張替えたと単に花粉症の症状が軽減されたという事例も存在します。換気は生活する上で重要ですが、その際に外のほこりを室内に入れてはいけません。メッシュの細かい網戸を上手く活用し、室内を清潔に維持しましょう。そうすることで健康的で掃除が楽な住宅にすることができます。
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mm
の大きさです。
【畳たたみ】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖ふすまの天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳たたみは本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳たたみは4帖半から襖ふすま、障子、網戸は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
日本の気候風土の特徴は、世界的に見ても類の無いものと言われています。
まず、夏は高温多湿である事。近年よく夏場に集中豪雨が続き、夏場の台風は大雨を連れてきます。日本では、年間を通じても雨は1,800mm程度降りますが、欧米では500mmから800mm程度、世界の平均でも700mm程度に過ぎません。
そして一転して冬場の気候は低温乾燥と成り、季節によって気候条件は大きく変わるのが日本の特徴なのです。先人達は、そんな気候の中で知恵と工夫を重ねて、世界に誇れる畳やふすま、障子などを創り上げてきました。
また、近年様々なアレルギーが私たちを悩ましていますが、欧米の生活様式や機密性の高い住宅がそのまま、日本の生活様式の中に入って来たことで、気候風土との少しづつのミスマッチが重なったことにも一因が有るのではないでしょうか。
特に畳には、保温断熱効果や調湿効果があります。密閉性の低い日本家屋の中にあって冬場の保温や、夏場の涼しさを助けてくれます。また近年の研究で、畳1帖で約300~500ccの水分を吸廃出する事や二酸化窒素やシックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着してくれる事が分かっています。
また、畳は適度な弾力性で転んだときの衝撃を和らげたり、騒音や振動の軽減も期待できます。実に畳は、人(特にご高齢の方や小さなお子様)にやさしい内装品なのです。
また、襖や障子にも断熱や湿度の吸収、放出や異物の吸着効果の点で共通の能力がある事も分かっています。
私達はこの優れた畳、ふすま、障子を継承していきたいのです。
その為には、今後ますます進むと思われる、洋式のインテリアとも上手く融合出来るように畳や襖を工夫する必要も有るでしょう。また、重要な問題としてお部屋のバリアフリー化があります。畳や襖、障子をそのまま使いながらのバリアフリー化をもっと工夫する必要もあります。畳の弾力性は、転倒事故の際に人に対する負荷を和らげてくれます。 これは、畳や襖の大きな長所でお年寄りや小さなお子様の居られるご家庭では大変重要な畳やふすまの役割だと思います。
そしてこの優れた畳、襖、障子の新たなる普及の為、コストの圧縮を図り、高品質を保ちながらも出来る限りお求め易いお値段で畳、ふすま、障子作りを追求し続けています。
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
畳の作りと種類について
子供の頃から真冬に、こたつに入っているのが大好きで、どんなに寒くてもストーブは使わず、コタツだけで、暖を取るのが大好きです。最近は、若い方がフローリングにこたつをすることが増えているみたいです。ですが、コタツと言ったら畳だと思うのです。特に掘りごたつは最高で、出かけるのが嫌になるほどです。一度、仕事の出張でヨーロッパに行くことがあったのですが、とにかく寒くて、一緒に行った人は日本食が恋しいということでしたが、自分は、食べ物よりも、畳とこたつが恋しかったです。日本人はやはり畳だと思います。畳は、日本で利用されている伝統的な床材です。芯材になる板状の表面をい草の編み込んでできた敷物状の畳表でくるんで作るのです。縁には畳表を止めるためと、装飾を兼ねて、畳べりと呼ばれる帯状の布を縫い付けるのが一般的です。また、琉球畳に代表されるものでは、縁のなものもあります。畳には、縦横比が、2:1になっている長方形の1畳サイズと、これを半分にした正方形の半状サイズの2種類があります。一般的な企画としては、本間、中京間、江戸間、団地間の4種類が有名でありますが、このほかにも地域ごとに様々な企画が存在しています。
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
衛生的な洗える畳とは
アトピーの子供がいるので、畳はダニの発生が心配で使えないという人がいるかもしれません。それに、畳は汚れても頻繁に取り替えることができないから不便だと考えている人もいるはずです。現在は畳も進歩して、発泡スチロールや木材チップなどを素材に使って害虫を寄せ付けないタイプのものもあります。
それが、さらに進化して洗える畳ができているのです。従来のイ草などの代わりにポリスチレンなどを使って洗うことを可能にしたのです。ダニを寄せ付けず、クッション性もあるので小さな子供やお年寄りのいる家庭でも喜ばれています。
多くの人が利用する宿泊施設や保育所、老人ホームなどでも好評です。特に高齢者のいる施設では、お風呂場に設置することで転倒の危険性を防ぎます。年配者は固いタイルの上で転んだ場合、重大な怪我をする危険性があります。
洗える畳を風呂場に設置することで、もし転んでもその被害を軽減することができます。それに、発泡スチロールなどを使っているのでとても軽く女性が持って運ぶこともできます。自由に置き場所を変えることもできるのです。
レンタルで交換してくれるので、いつでも清潔な畳を使うことができ衛生上も安心です。カラーバリエーションも豊富で様々な色が部屋の雰囲気を明るくします。
子供のイタズラに備えられる襖
襖は部屋と部屋を仕切る建材であるのと同時に、見た目の美しさと精神的な癒やしを求められる存在でもあります。 これは大人であれば誰しもが承知している事柄なのですが、小さなお子さんともなるとそうはいきません。 襖の張り替えが必要になったという理由の多くが、子供のイタズラ(追いかけっこをしているうちに体当たりしてしまった、油性マジックで落書きをされたなど)だったりします。 子供は元気に暴れ回っているぐらいでちょうどよいと俗に言いますが、何かある度に襖が壊れたり汚れたりしていてはたまりません。 では、それに対する備えは何かあるのと言いますと、二つ存在します。 一つは、襖の表面にベニヤ板を張り付けることです。これはペイントすることにより、全く別の空間を作ることも可能になるのですが、子供が体当たりしても破かれる心配がない(襖紙の上に両面テープでベニヤ板を張り付けているだけなため、そこに激突しても大けがを負うことはありません)のが最大の利点です。 もう一つが、襖紙としてクラフト紙を貼ることです。 こちらは強度面での改善は望めませんが、近くにペンを置いておいて、「これなら好きに落書きしても構わないよ」と子供に言うことで、被害をそちらに吸収(正確に言えば、襖の一つを子供用のアート空間にする)することが可能となり、全体的な被害は軽減できます。
襖の歴史は長く、それは障子よりもさらに古くからあるとも言われています。日本の建築美を飾る建具の1つとして、襖ほど注目されたものはありません。平安時代ごろから始まったと言われ、現代までその姿を残してきているというのは驚くべきことです。一般的に普及してきたのは、江戸時代からのようですが、襖は欠かせない日本建築の1つであり続けています。そしてそれを張替えたり、修理したり、新調したりするための建具の業者が日本にはたくさんあります。というのは、襖は消耗品の1つであり、やがて張替えなどのメンテナンスが必要になるものだからです。 襖の張替えのタイミングは、見た目の悪さ、汚れの目立ち、カビ、破れ、劣化といったものです。どれほど大切に使っても、10年くらいで張替えが必要になるでしょう。張替えの業者は、ネット検索で探したり、自宅近くにも建具屋さんを見つけることができるかもしれません。とはいえ依頼する前に、ある程度の張替え施工の費用がどのくらいなのか、相場を調べておくのは良いことです。業者の言い値が相場に沿ったものであることがわかり安心できます。襖のデザインは、無地や目立たないものが好まれていますが、やや派手でモダンな感じのものも、雰囲気が変化して良いものです。
障子は和室にあり、とても繊細なものです。一般家庭にある和室の障子は、基本的に破れやすい普通紙でできています。従いまして、ちょっとした瞬間にビリッといった感じでやぶれてしまいます。小さい子供がいる家庭ですとかなりの確率で破いてしまいます。大人だったとしても、取っ手の部分を掴もうとして、ちょっと手が滑ってしまって、取っ手ではなく障子紙のところに手がいって、そのまま破いてしまうこともあります。ちょっとだけの破れならまだ良いですが、これが何度も繰り返しとなってくると、そのままにしておくのは非常にみっともないです。そんな時にはどうするのが良いか、それは障子の張替えです。障子の張替えを行うタイミングですが、できれば、最初にどこかしら破いてしまったときに業者にお願いするのが良いのですが、ちょっとだけの破れで毎回依頼するとなると、結構面倒です。ですから、何か所か目立ってきたタイミングで業者に連絡を入れて、お願いしてみると良いです。こうすることによって、綺麗な和室を保つことができるようになります。これは非常に大切なことです。せっかくの和室をできるだけ綺麗に保たせるためにも、重要なポイントになってきます。
横浜市の歴史と横浜市内各地域
横浜市は神奈川県の東部に位置する市で、同県の県庁所在地であると同時に県内最大の市でもあります。北は川崎市、南は鎌倉市・逗子市・横須賀市、西は大和市、藤沢市、東京都町田市に接し、東は東京湾に面しています。2014年2月現在の人口は約370万人で、都市人口としては東京23区に次いで国内第2位、市町村としては国内最多となっています。1956年の地方自治法改正と同時に政令指定都市となり、現在は行政区として18区を擁しています。
現在の横浜市の辺りは、かつての武蔵の国と相模の国に当たります。平安時代の後期ごろから地方武士が台頭しはじめ、鎌倉幕府の成立以降は本格的な開発が始まりました。近世には神奈川・保土ヶ谷・戸塚(それぞれ現在の神奈川区・保土ヶ谷区・戸塚区辺り)が、東海道の宿場町として栄えました。また、六浦(現在の金沢区辺り)は金沢八景が浮世絵の画題となるなど、景勝地として知られるようになりました。一方、横浜市の名の由来となった横浜村(現在の中区辺り)は、小さな漁村でした。
横浜の名が大きくクローズアップされるようになったのは、1859年の開港によってです。これにより横浜は国際色豊かな港町となり、急激に発展しました。1889年には市制が敷かれることとなり、ここに横浜市が誕生しました。現在の横浜市の行政・経済の中心部はこの頃作られた市街に集中しています。横浜市庁舎のある関内地区は、開港当時外国人居留地と日本人居留区との間に関所を設け、その内側と外側をそれぞれ関内・関外と呼んでいたことに由来します。
また、中華街や山手地区など、今では横浜市を代表する観光スポットとなっている地域も、開港に伴って形成されました。一方、山手地区に隣接する本牧地区は、違った経緯をたどって国際色を帯びるに至りました。第二次世界大戦後に駐留したアメリカ軍のベースキャンプが設けられたことでアメリカの音楽やファッション、食文化などが大量に流入し、周辺にはそれらを紹介する店などが立ち並ぶようになりました。本牧発のアメリカ文化は、1960年代から70年代にかけて若者を中心に大きな影響を与えました。
横浜市の北西部地域である港北区や都築区、青葉区などはこれらの中心部とはまったく異なるかたちで発展を遂げました。渋谷・新宿などの東京の西部が発展するにつれ、交通アクセスのよい横浜市のこれらの地域がベッドタウンとして機能するようになったのです。港北ニュータウンをはじめとする大規模開発が行われ、そこに住む人々は「横浜都民」などと呼ばれたりするようにもなりました。また、横浜市南部の金沢区・港南区・戸塚区辺りは、高度経済成長期に建設された大規模な団地が街づくりの核となっています。
神奈川県の地域ごとの特徴
神奈川県は東京都に次ぐ日本で第二位の都道府県です。神奈川県の人口密度は、東京都、大阪府に次ぐ第三位となっています。神奈川県は、東部と、中央部、西部で性質が大きく異なっています。神奈川県の東部は横浜市や川崎市を中心に大都市化や工業化が進んでおり、特に東京湾に面し京浜工業地帯の一角を形成する場所となっています。中央部は、相模原市や海老名市を中心に形成されており、都市化や工業化が進んでいますが、東部よりは規模としては小さくなっています。
一方の西部は、小田原市を中心に街が形成されていますが、足柄山地や箱根山が連なり、緑豊かな地域となっています。特に西部にある箱根は、温泉として有名で、首都圏やその他日本全国から観光客が集まる、一大温泉街となっています。神奈川県の県庁所在地は横浜市にあり、横浜市は横浜駅やみなとみらい21地区を中心に大都市が形成されています。また、近隣の区や市は、東京のベッドタウンとしての役割も持っており、人も多く居住する場所となっています。
神奈川県には、その他に、横須賀市などがある三浦半島や、鎌倉市、茅ケ崎市など、大きく有名な街がいくつかあります。特に、鎌倉市は、鎌倉時代に幕府がおかれた街で、現在でも寺社や歴史的な場所が多く残っており、日本の小京都と言われる場所になっています。この鎌倉市も箱根と同じように、多くの観光客が集まる場所となっています。また、鎌倉の近くには藤沢市になりますが江ノ島もあり、江ノ島も神奈川県を代表する観光名所となっています。
神奈川県は県の地域によって気候も異なっています。東部では、ヒートアイランドの影響を大きく受けており、夏は暑く、熱帯夜になる日も非常に多くなっています。気温が高めであるため、冬場に積雪もそれほどありません。湘南や三浦半島の地域では、海風の影響もあり、夏場でもあまり酷暑とはならず、1年を通して比較的穏やかな気候となっています。相模原市などの内陸部では、冬は寒くなり積雪が多く、夏は内陸部である為、猛暑日となる日も多くなっています。
箱根などの神奈川県西部については、冬は特に山間部では大雪となることが多いですが、夏は涼しく避暑地となる地域となっています。神奈川県では、日本の他の地域では過疎化が進み、人口減少が続いていますが、この地域に関しては首都圏への人口集中により、今後も当面は人口が増え続けると予想されています。現在でも多くの商業施設や企業本社が集積していますが、人口増加に伴い、横浜市、川崎市を中心に今後増々都市化が進んでいくと考えられています。