
全国提携店とのネットワークで全国にお伺い致します

萩市全域にスピーディーに対応します!!



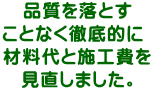
 |
 |
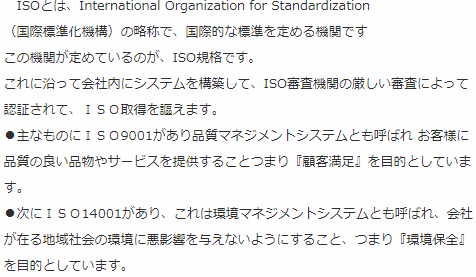
  |

 | 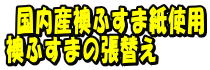
|
![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)
 |
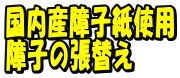
|
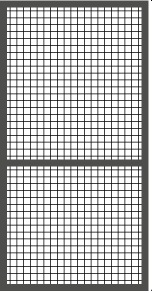 |
|
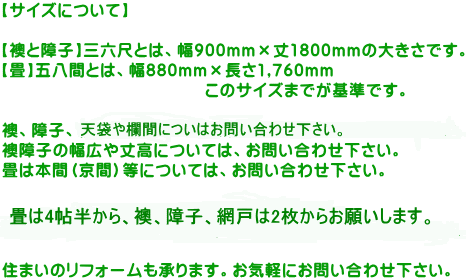
| 無料お見積りはこちら |
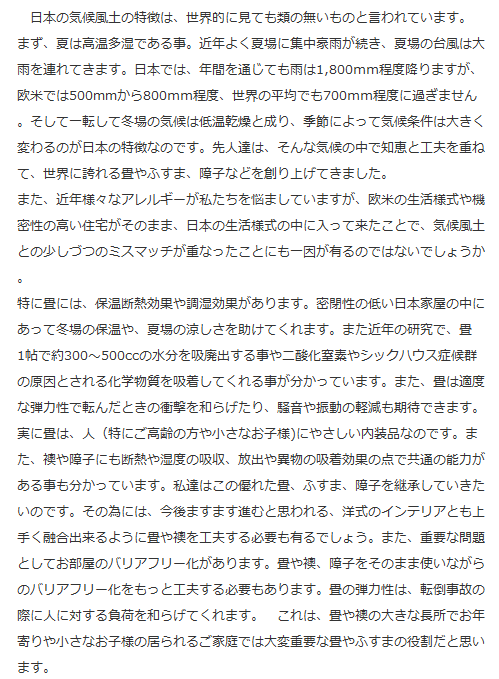
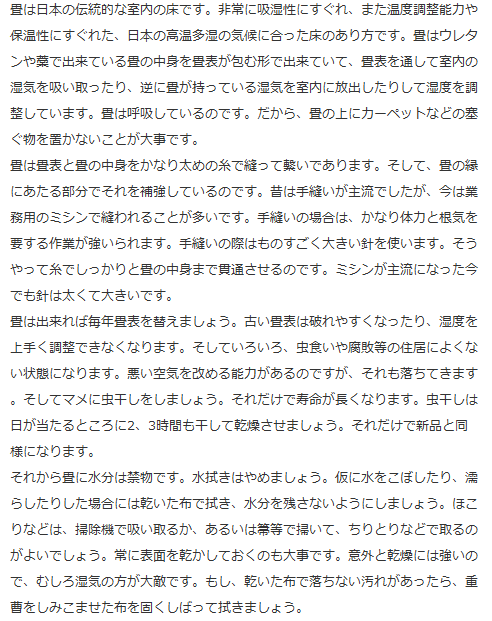
日本の住宅と言って真っ先に思い出すのは何でしょう。ふすま、障子と合わせて必ず出てくるのが畳ではないでしょうか。青々とした畳がずらりと敷き詰められた大広間、お寺や旅館で必ず見られる風景です。個人の住宅の中でも嘗ては広い畳の間がステイタスシンボルでした。近年洋風建築やマンションが増えたといえ畳敷きの部屋が全くないお宅は珍しいでしょう。しかしそのメンテナンスというとどうでしょう。ずいぶんおろそかになっているのではないでしょうか。一昔前までは大掃除と言えば畳をあげて家の前に並べ天日干しした後パンパンとはたいて埃を出す。そしてまた床に新しい新聞紙を敷いて畳を敷きなおす。これが庶民の日常風景でした。今もうそういった風景は映画の中でしか見られなくなっているといっても過言ではありません。
ご承知のように畳はイグサという植物繊維でできています。その自然素材が湿気を吸ったり吐いたり程よく室内の湿度を調整してくれ程よいクッション性を提供してくれますが当然寿命があります。表が擦り切れたりヘリが擦れたりすればそれはもう寿命を迎えているということです。昔は表替えをしたりヘリを縫い直してくれたりというお店もありましたが今では見つけるのがむつかしいでしょう。思いきってネットで探してでも新しいものに交換されることをお勧めします。最近では紙で出来た和紙畳というものもあります。まっさらな畳の敷かれた部屋を見たとき「何とかと畳は新しい方が」とうなずかれることと思います。
日本の家屋というのは、意外と紙で出来ている部分があります。それが障子とか襖です。基本的は紙で出来ています。だからといって、簡単に作ることができるわけではなく、自分で作るのは基本的にはやめたほうがよいです。物凄く時間がかかりますし、綺麗にできるとは限らないからです。ですから、基本的には業者に依頼したほうが賢明であるといえます。言うまでもありませんが、それなりの費用はかかってしまうのです。しかし、それでもメリットはあります。とにかく綺麗にできますし、こちらのイメージ通りに作ることができます。襖は要するにドアみたいなものです。ですから、とても部屋の雰囲気に影響がありますから、良いものにしておいたほうがメリットが多いです。もちろん、まったく襖には拘らない、と言う人もいます。しかし、襖絵、というくらいですから、襖に絵を書いて、それを楽しむ、という文化があるのも確かです。色々な点で楽しむことができる家具の一つです。日ごろから、しっかりとメンテナンスをして、或いは取り替えることを検討するとよいです。基本的には消耗品の一つなのです。長く使うのもよいですが、自分が気に入るものに替えるのも十分にありです。
| 無料お見積りはこちら |
萩市には2015年の大河ドラマのゆかりの地がいくつかありますのでその一部を紹介します。萩市呉服町にある木戸孝允旧宅は維新の三傑とうたわれた木戸孝允の生家です。現在の萩市に生まれてから江戸にでるまでの約20年間を過ごした木造瓦葺の2階建ての家は、木戸誕生の部屋や庭園などよく旧態を残しており、木戸の幼少時代の手習いの書を表装した掛け軸や写真などが展示されています。萩市堀内にある萩城跡指月公園ですが、萩城は1604年に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていました。現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめており、ここ一帯は国の史跡に指定されております。萩市江向にある旧萩藩校明倫館は江戸時代中期の1718年に藩主毛利吉元が城内三の丸に創建し、1849年毛利敬親がこの地に移しました。敷地内には有備館や水練池などの遺構が遺されております。有備館は、藩士の練武のほかに、たこっくからの修行者の試合場となっており、土佐の坂本龍馬もここで試合をしたと言われております。現在は外観のみ見学が可能となっております。