
全国の提携店とのネットワークで、全国にお伺い致します。
八代市スピーディーに対応します!!



|
 |
 |
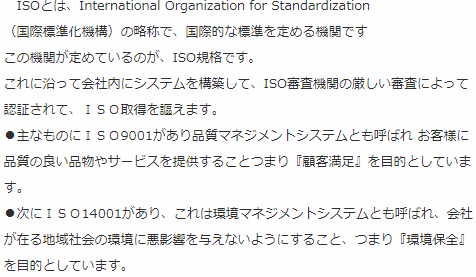
  |

|
 |
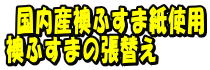
|
![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)
 |
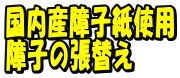
|

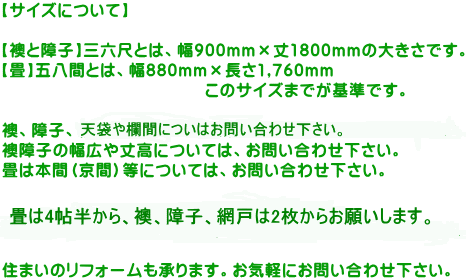
| 無料お見積りはこちら |
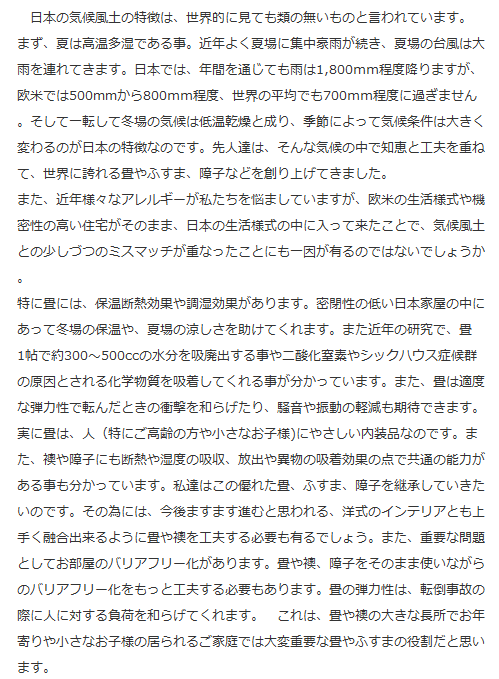
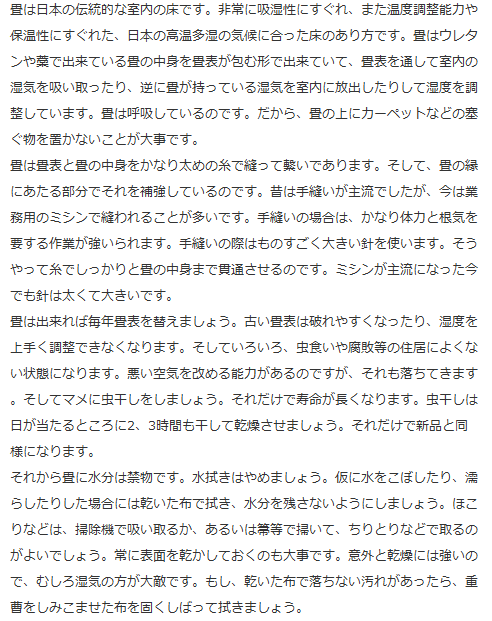
日本人の心と安らぎは畳のイ草の香りです。
ないげない時を過ごすとき、畳のイ草の香りはとても安らげます。
最近は品質やコストダウンが進んでおり、とっても手軽に、畳を楽しむことができるようになってきています。
ダニカビ、その他のさまざまなアレルギー問題を解決してくれる畳があります。
そのほかにも、畳表の変色が気になるなど、さまざまな畳についての悩みを解決できます。健康面を重視した畳が出てきていますので、安心できます。
そのほかにも、お客様のニーズに対応してくれます。デザインをはじめ、タイプ別の商品や、豊富に取り揃えているところが多いですので、家に合う畳をお探しの場合は、業者の方に相談することで家に合うものを提供していただけます。
ヘリ無しのものもあり、年配の方から赤ちゃんまでが安心して生活できるように工夫されています。ダニやカビが生えないものですと、赤やんのお昼寝も年配の方のお昼寝も何も心配することなく、お昼寝させてあげることができます。
畳を長持ちできるように手入れが簡単になってきているのもありがたいことです。
お茶や牛乳などをこぼしても強くこすらずに、しぼった布でやさしく拭き取ることで跡が残らずに済みます。このように、以前よりも手入れがしやすくなっています。
| 無料お見積りはこちら |
熊本県八代の八代城の北の丸跡の松井神社庭園
松井神社庭園は、八代城本丸跡のすぐ北側、北の丸跡にある、庭園は近世初期、八代城主加藤正方が築いたもの。北の丸には正方が八代に材城した10数年間居館と、母の妙慶禅尼の隠居所がおかれてあった。寛永9年、正方が広島へ去り、かわって八代へ入城した細川忠興は、庭を茶庭に大改造し、中央の築山の間に滝口を設け、石橋の先の森の中に消える小池のほとりに、茶室と露地をつくって茶の湯を楽しんだという。今も、当時の遺構がよく残されており、春にはあたりを色どるツツジが美しい。一隅に枝を広げる臥龍梅は忠興の手植えと伝え、長さ7メートル余りにわたって巨幹を地上にはわ、奇景を呈している。樹勢は極めてさかんで、2月下旬〜3月上旬には見事な大輪の花をつけ、
庭をそのほのかな甘い香りでつつむ。松井神社は、明治14年、旧城主、松井家の先祖をまつって造立されたもの。今次大戦前までは郷社とされていた。松浜軒は松井神社の西方にある。元禄元年、八代城主、松井氏3代直之が生母の崇芳院尼のために建てた別邸。白壁の大きな土蔵と城壁に囲まれ、正面に三間一戸、左右に入母屋造りの番所を備えた門を構える。庭には、肥後ショウブ・カキツバタ・蓮を植込んだ池を中心に、形の良い刈込みが配され、老松をのせた築山がゆったりとひろがって、池畔にたつ瀟洒な茶室が、眺めに風趣をそえている。県指定の史跡・名勝である。代々の城主の清遊の地で、築庭当時は、築山のすぐ背後まで白砂青松の八代海岸が迫り、浜の茶屋、などとも呼ばれていた。今は干拓により、海はるか彼方へ遠のいてしまっているが、一般に開放されて、市民の憩の場として親しまれている。とくに、ショウブ・カキツバタ・ツツジ・藤が花をつける4月から6月頃がよく、一隅に厩を改造してつくられた、松井家伝来の家宝を展示する宝物館もある。医王寺は八代駅の西約1.5キロメートル、八代の街中にある真言宗の寺。平安時代の創建と伝え、戦国時代兵火にやけて荒廃していたのを、近世初期、八代城主、松井氏2代、寄之が、妻の崇芳院尼の願いによって再興。以来、江戸時代を通じて、松生家歴代の祈願所とされていた。境域は約1,300平方メートル、堂宇は本堂・庫裏・山門・荒神堂などを備える。本尊の薬師如来立像は国指定の重要文化財で、檜材の一木造り、像高63.7センチメートル。ふっくらとした童顔や豊かな腰張り、ゆったりとひろがる翻波式衣分など、弘仁期の作風を残した平安中期のもの、と推定されている。本尊の右脇に、檜材の寄木造り、鎌倉後期作の聖観世音菩薩立像が、侍立している。
熊本城の宇土櫓
五階櫓の中でも「三の天守」とも呼ばれる宇土櫓(うとやぐら)は、3重5階地下1階で、熊本城では大小天守を除いて最大の櫓である。高さ約19メートルあり、近世以前に建造された天守や櫓との比較では姫路城、松本城、松江城に次いで4番目の高さである。破風はむくりを持ち、諸櫓と同じ仕様で造られているが、最上階に外廻縁を持つ。清正の創建した初代天守ではないかという見方もある。宇土城の天守を移築したものと伝えられ、明和9年(1772年)に森本一端が記した『肥後国誌』(下巻)によって通説化したが[12]、昭和2年(1927年)の解体修理の際には移築の痕跡が見られず、城戸久などがこの説を否定した。また、平成元年(1989年)の修理の際、2重目と3重目で建築方法の違いと3階部分の増設が判明している。
宇土櫓に関して記された最も古い文献である別井三郎兵衛の『御城分間』寛文6年(1666年)には「御天守西ノ御丸 五階御矢蔵」とあり、同じ寛文年間に作成された熊本城絵図には「平左衛門丸五階櫓」との記載がある。平左衛門丸には加藤平左衛門の屋敷があり、小西氏の家臣であった者の管理をする施設も併設されていたため、平左衛門丸に建てられていた櫓には「宇土三階櫓(平左衛門丸二重櫓)」などのように「宇土」を冠していたことが享保から延享期成立の『肥後録』にある。熊本城の諸櫓の再建に携わっている熊本大学の北野隆教授は宇土櫓も同様の由来で名づけられたとしている。
![]()

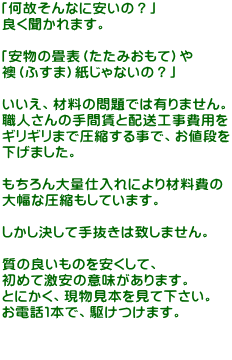
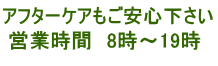
八代市迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例

G様邸
畳表替え 襖張替え

S様邸
畳表替え 襖張替え
 I様邸
I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸
縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。
H様邸
半帖縁無し畳

S自治会様
障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

八代市(やつしろし)は、熊本県の南部に位置し、人口が約13万人の街です。
正式名称は「やつしろ」と呼びますが、地元や近隣の人々は九州弁で「やっちろ」と呼びますので、県外からの観光客は最初の頃はその呼び方に戸惑うようです。
八代市は熊本市に次いで人口の多い街である為に、熊本県南部を管轄する役割を持っており、その為に国・県のいくつかの出先機関が八代市に置かれているのです。
また、九州新幹線が全線開通したことにより、それまで多くの特急が発着をしていた鉄道の主要駅が従来の八代駅から新八代駅に移ったのです。
八代市の主な物産は、畳の原材料になるイ草とトマト・イチゴ・メロン・ミカンなどが挙げられます。
特にイ草は生産が盛んで、国産のイ草での代表的な産地として全国に名を馳せ、さらに最近では、日本文化の流行を受けて海外にまで販路を広げていっているのです。
冬でも温暖な八代市は、その温暖な気候を生かして様々な農産物を栽培していますが、柑橘類の栽培は盛んで、ミカンを筆頭に、ザボン・ブンタンなどが挙げられ、特に人の頭ほどの大きさを誇るザボンの一種である「晩白柚」は、八代市の冬場の名物的な果物になっています。
また、八代市南部にある日奈久温泉では、晩白柚を湯船に浮かべる晩白柚風呂を冬季(期間は要確認)に行っています。