
西淀川区内全域スピード対応!!

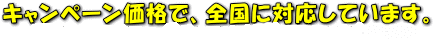



|
弊社では、輸入畳表もISO9001、ISO14001取得工場で製造されたものを使用しています。
  |


![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)

 (網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(網戸の種類)クリックするとウィンドウが開きます
(画像はイメージです)
【サイズについて】
【襖障子網戸】三六尺とは、幅900mm×丈1800mmの大きさです。
【畳】五八間とは、幅880mm×長さ1,760mm
このサイズまでが基準です。
襖の天袋や障子の欄間については、お問合せ下さい
幅広や丈高については、お問い合わせ下さい。
畳は本間(京間)等については、お問い合わせ下さい。
ご注文は畳は4帖半から襖、障子は2枚からお願いします。
住まいのリフォームも承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 無料お見積りはこちら |
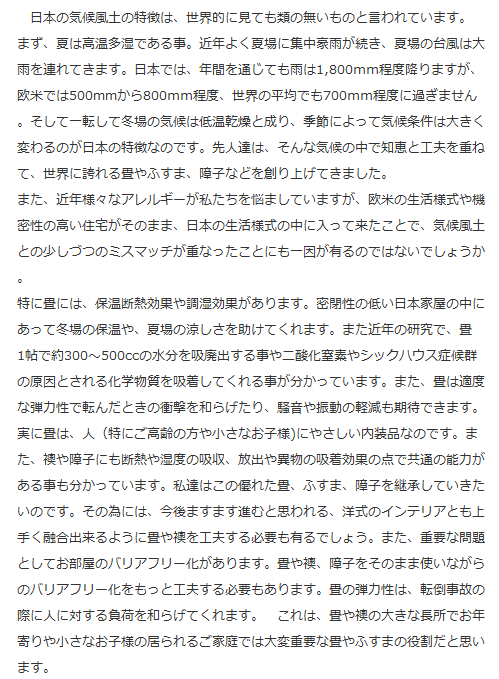
| 無料お見積りはこちら |
畳のメンテナンスについて
畳は日本の伝統的な室内の床です。非常に吸湿性にすぐれ、また温度調整能力や保温性にすぐれた、日本の高温多湿の気候に合った床のあり方です。畳はウレタンや藁で出来ている畳の中身を畳表が包む形で出来ていて、畳表を通して室内の湿気を吸い取ったり、逆に畳が持っている湿気を室内に放出したりして湿度を調整しています。畳は呼吸しているのです。だから、畳の上にカーペットなどの塞ぐ物を置かないことが大事です。
畳は畳表と畳の中身をかなり太めの糸で縫って繋いであります。そして、畳の縁にあたる部分でそれを補強しているのです。昔は手縫いが主流でしたが、今は業務用のミシンで縫われることが多いです。手縫いの場合は、かなり体力と根気を要する作業が強いられます。手縫いの際はものすごく大きい針を使います。そうやって糸でしっかりと畳の中身まで貫通させるのです。ミシンが主流になった今でも針は太くて大きいです。
畳は出来れば毎年畳表を替えましょう。古い畳表は破れやすくなったり、湿度を上手く調整できなくなります。そしていろいろ、虫食いや腐敗等の住居によくない状態になります。悪い空気を改める能力があるのですが、それも落ちてきます。そしてマメに虫干しをしましょう。それだけで寿命が長くなります。虫干しは日が当たるところに2、3時間も干して乾燥させましょう。それだけで新品と同様になります。
それから畳に水分は禁物です。水拭きはやめましょう。仮に水をこぼしたり、濡らしたりした場合には乾いた布で拭き、水分を残さないようにしましょう。ほこりなどは、掃除機で吸い取るか、あるいは箒等で掃いて、ちりとりなどで取るのがよいでしょう。常に表面を乾かしておくのも大事です。意外と乾燥には強いので、むしろ湿気の方が大敵です。もし、乾いた布で落ちない汚れがあったら、重曹をしみこませた布を固くしばって拭きましょう。
畳は常に呼吸しています。部屋の換気を忘れないようにしましょう。換気は1日に数回、朝と夕方ともう一回くらい、した方がよいでしょう。換気をまめにすると、畳の湿度を調整する能力が増します。フローリングの床よりも、空気をきれいにする能力があるので、呼吸器等にハンデがある人には良いでしょう。それから直に布団を敷くので、ベッド等のやわらかいマットレスよりも骨格に影響が出ない眠りを保証してくれるというメリットもあります。
平安時代に生まれた畳は部屋の一部に使用され、室町の書院つくりでは部屋全体に畳が使用され始めました
現代的な日本家屋の起源を探していくと室町時代の書院つくりに行き着くとされています。書院つくりの建物は床の間のある座敷を指すだけでなく、武家が好んで立てた建築様式そのものを指すとも言われています。いくつか共通する条件として、建物内を仕切るのは引き戸の建具を使用している、室内は畳を敷いている、天井に板を張っている、住民が生活する場所と客室がわかれている、客室には床の間があり、違い棚・座敷飾りなどを設置して迎える準備をしていることなどが挙げられます。
室町以降の日本家屋や建築に大きな影響を与えた書院つくりの建物で、必ずあるのが、襖と障子、そして畳です。襖は、家屋内を区切るために使われるもので襖障子とも言います。歴史ドラマなどで必ず見かけることができ、左右に滑らせて移動し開閉させます。武家屋敷やお城のような何10帖もあるような部屋であれば、襖障子の数も大幅に増え、大きく開放したり、完全に区切ったりすることができます。障子は家屋内と外を区切る窓の役割をしており、平安時代に明かりを取り入れるために生まれた明障子が起源と言われています。
襖と障子、それぞれ日本の風土や生活環境に合わせて生まれましたが、もう一つ書院つくりの建物で欠かせないのが畳です。元々の障子は唐から日本に入ってきたものですが、畳と襖は日本で生まれたものです。そんな畳は地域の風土と切っても切れない関係にあり、世界に類を見ない日本独特のもので、古来の畳は、単にわらを積んだだけと考えられており、平安時代からその規格化が進んだと言われています。初期の頃の畳は、部屋全体にではなく、公家や貴族が座る場所や寝床など必要な場所にのみに畳を使用していることが、当時の公家の生活を描いた絵画などで確認できます。
畳の素材は、現在と同じイネ科の多年草の葉と茎やい草を使用しています。当時の畳は筵のようなもので5~6枚を重ね、い草で作った畳表をかぶせて錦の縁をつけて固定し使用しています。今とは作り方や形こそ違いますが、畳の原型であり、書院つくりの建物ではこの畳を殆どの部屋で使用していたのです。また、現代では地域によって畳の寸法が違うことがあります。例えば、京都・大阪以西のほとんどで使用される京間・本間・関西間寸法、愛知・岐阜等で使用される中京間、関東・東北地方・北海道などで使用される江戸間・関東間・田舎間・五八間がそれです。
各地域の生活や風土によってかわる畳の材料であるい草は、日本最古の医書に薬草として記録もされており、自然の魅力を生活に取り入れる事のできる点が大きな魅力で、真新しい畳の自然の香りが好きな方もいるほどです。最近では、畳表に使用するい草の持つ天然の抗菌作用が注目されており、サルモネラ菌や黄色ブドウ球菌などへの効果が確認されています。さらに、気になる足の匂いを軽減する作用もあるという研究もあり、毎日の生活で気なる安全と安心に強い味方になると考えられています。畳は、日本独自の敷物で平安時代に生まれ、室町時代には部屋全体に、そして現代ではそれぞれの地域や風土、住民の生活に合った形で利用されているのです。
| 無料お見積りはこちら |
襖のイタズラ対策いろいろ
小さいお子さんやペットが居ると、どうしても目を離した隙にイタズラをされてしまうものです。特に猫や赤ちゃんは、目についたものを引っ掻く、開けるという事をしてしまうため、対策が必要です。赤ちゃんが襖を開けてイタズラしないように、ロック出来る専用グッズもあります。一般的には、100均の突っ張り棒などで襖の戸を開けられないように工夫している家庭が多いようです。襖の溝の所に突っ張り棒をはめ込めば、赤ちゃんが簡単に開ける事は出来ません。猫のイタズラ対策には、『イタズラ防止スプレー』というものもあり、猫の嫌いな臭いでイタズラ出来ないようにするといった方法です。他にも、『引っ?き傷防止シート』を襖に貼って、猫が引っ掻こうとすると滑るようにしておきます。そうする事で猫は『この場所では引っ掻く事が出来ない』と思い込み、悪戯をやめる場合があります。また、小さなお子さんは襖に落書きをしてしまう事があります。クレヨンやマジックなどで描かれる場合が多く、消す事は困難になります。この場合、落書きを防止する事は難しいですが、襖の材質によっては落書きを落とせる場合もあるため、一度材質を調べてみてください。自分で張替えなど行った際、耐久性の強い材質のものにすれば、洗剤や除光液で落す事も可能になります。壁や襖の質を綺麗に保つためには、こういった工夫も必要です。いざという時に、ある程度の知識を持っておくようにしましょう。
面倒な網戸の張替え修理
網戸の張替え修理が、とてつもなくめんどくさいと思ったことはありませんか?
張替え修理をするときには網戸を窓サッシから外すことになりますね。ですが、そんなに簡単に適当にやって外せというようなものでもないので地味にこれすら大変ということがあります。
それこそ網戸に外れ止めがされていることすらあります。その解除する方法がわからないこともありますよね。
ですから、張替え修理がわかる人でもとにかく手間がかかる行為なんです。網戸は、割と強い日差しを受けることによって、雨風に晒されることとか経年劣化でボロボロになったりしますから、不注意で破れたりしてしまうこともあるんです。
張替え修理をしないといけないことになってもいざやろうとすると求められる道具もたくさん必要になってくるでしょうし意外と腰が重くて上がらないなんてこともあったりするわけです。また張替えをするには、場所の確保も必須ととなります。
小さな小窓の網戸の張替え修理であれば、小さな場所でもよいでしょうけど長いものであれば自分の身長以上の大きさなんてことになるわけで、そこからさらに余裕をもって広い場所が求められます。張替え修理とは自力でやろうとするとここまで面倒なこことでもあるわけです。
緑陰道路が整備されている大阪市西淀川区
西淀川区は大阪府大阪市にある区で、古代には無数の島があり難波八十島と呼ばれていました。西淀川区は江戸時代に新田開発が進められたことで農業が行われるようになり、明治時代後期に入ると工業化が進みました。大阪市の行政区としての西淀川区が発足したのは大正14年のことで、当初は「下淀区」という区名が候補にあげられていました。昭和18年に境界の見直しが行われ、現在の区域となりました。西淀川区北部は兵庫県と接しています。大阪市西淀川区には大野川緑陰道路が整備されており、散歩やサイクリングに利用できます。薬用植物を含む約100種類もの樹木が植栽された緑豊かな環境で、住民の憩いの場として愛されています。大阪市西淀川区には複数の公園もあり、佃ふれあい公園もその一つです。木製複合遊具が設置されているため子どもの遊び場として利用でき、ゲートボール場もあります。西淀川区にはJR東西線と神戸線、阪神電気鉄道本線と阪神なんば線が走っており、大阪市営バスや阪神バスも利用できます。また、高齢者を対象とした「にーよんバス」と呼ばれるコミュニティバスも運行されています。昭和50年までは阪神国道線も運行されていました。西淀川区内には阪神高速3号神戸線、5号湾岸線、11号池田線の出入口もあります。
| 無料お見積りはこちら |
天下の台所大阪で美味しい食べ物を見つけよう
大阪府は県庁所在地が大阪市であり、西日本最大の都市です。大阪は長い間日本の文化の中心であった京都の近く、西日本最大の都市てして発展したため独特の文化が築かれています。食文化や芸能文化などがよく知られています。言葉にも独特のものがあります。大阪弁は、東京言葉や京言葉等と共に日本でよく知られている方言の一つです。大阪弁は汚い、怖い、荒っぽいなどあまり良いイメージがありませんが、大阪弁には、大阪言葉またの言い方を浪速言葉と河内言葉があるようです。よくやくざ映画などで使われている言葉は河内言葉のようです。大阪言葉を使う人は、河内言葉を使う人と一括りにはして欲しくないようです。食文化も有名です。全国からあらゆる食材が集まる天下の台所であることから、独特の食文化が栄え、大阪食い倒れという諺まであります。大阪人は破産しそうなほど飲食に贅沢をするという意味ですが、大阪人は食べ物自慢にうるさい、大阪には食べきれないほどのおいしい食べ物が沢山あると言った意味があります。しゃぶしゃぶや懐石料理、うどんすきや大阪寿司などの本格料理から、タコ焼きやお好み焼き、串カツなどの庶民の味などの料理が楽しめるところです。タコ焼きの道具などは各家に必ずあるようです。昔から土産物は、岩おこしや昆布などで、食材を生産するというより食材が集まる場所であったことから、大阪独特の産物やお土産はあまり聞いたことがありません。大阪駅でのお土産の一番販売の多いのは、伊勢名物の赤福餅です。伝統野菜のキュウリや大根が見直されてきたり、和泉でしかできない水茄子や和泉の玉ねぎ、水菜などの特産品もありますが現在では廃れてきています。昔から大阪の味として親しまれてきた、鱧や河豚、きつねうどん、うなぎなどがあります。特に河豚は全国消費量の約6割が大阪での消費で、代表的な料理がてっちりやてっさが人気で安く食べられる店もあります。昔商人の食卓で、半助と言う蒲焼にした後の鰻の頭を使った炊き合わせやサバなどの魚の骨でだしを取る吸い物の船場汁など、無駄のない料理も数多くあります。鶴橋などのコリアタウンがある所では、焼き肉店も多く、日本でホルモン焼きが広まった最初の場所です。インスタントラーメンや酢昆布などの発祥が大阪の食品や料理も多くあります。今では飲食店が道頓堀通りの北側に様々なジャンルの店舗が軒を連ね、一年中賑わっています。観光客も様々な食を楽しむために訪れて人気を集めています。
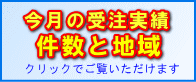
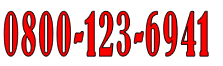
![]()

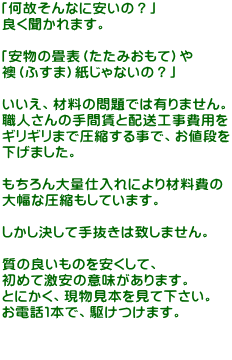
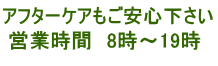
西淀川区迅速に対応します

D保育所様
和紙畳の張替え工事例
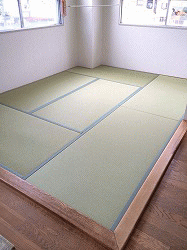
N様邸 障子張り替え
障子は、お部屋のフィルター

I様邸
畳と障子の張替え工事

K様邸 縁無し畳施工
お洒落に出来上がり
ました。

H様邸 半帖縁無し畳

S自治会様 障子張替え

お茶室の畳表替え工事

S様邸
和紙カラー畳表 施工事例

N様邸
襖、和紙畳張り替え

N様邸
襖ふすま張替え施工
襖は一般的には、和紙または織物で作られています。そのため通気性が良く、湿気を吸いやすいところが特徴です。湿気を吸うということは、室内の湿度を下げるということです。つまり襖の設置により、室内は快適な空間になるのです。
ところが吸うことにより、襖の内部には湿気がたまっていきます。湿度が低い日には、この湿気はある程度は放出されます。しかし湿度の高い日が続くと、湿気が入ったままとなり、襖の内部には徐々にカビが生えてくることになります。そしてカビにより、襖紙は変色してきますし、匂いも不快なものとなっていくのです。開閉時に、カビの胞子がぱらぱらと落ちてくることもあります。
そのため多くの人が、数年おきに襖紙を交換しています。一般的には、だいたい5~10年に1回の頻度で交換されています。
カビの生えていない新しい襖紙にすることで、見た目はきれいになりますし、匂いや胞子の心配もなくなります。また、専門業者に交換を依頼した場合には、内部の組子の部分もきれいにしてもらえます。カビや汚れを拭き取ってもらえますし、オプションで防カビ加工をしてもらうことも可能となっています。
これにより、再び安心して襖に湿気を吸わせることができるようになります。