
御坊市スピーディーに対応します!!



|
 |
 |
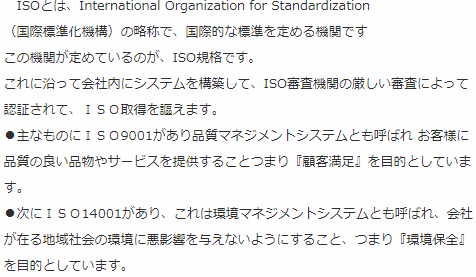
  |

|
 |
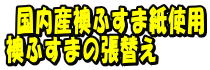
|
![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)
 |
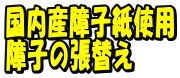
|
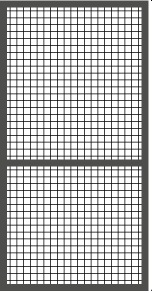 |
|
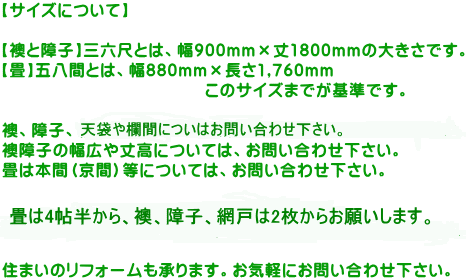
| 無料お見積りはこちら |
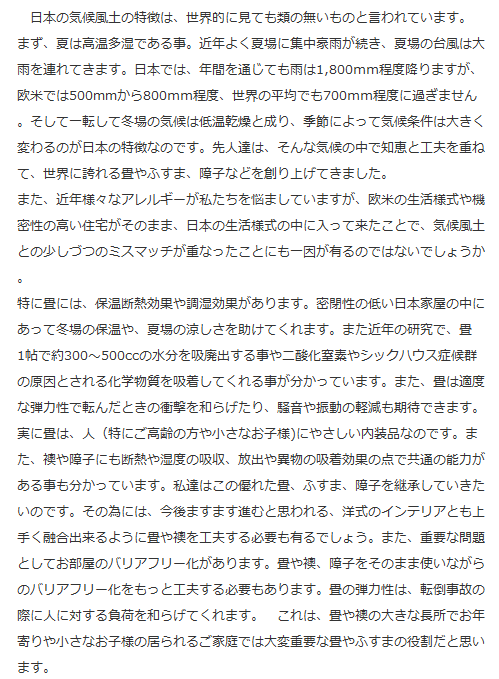
畳たたみの構造
私達が普段座ったり寝転がったりしている畳は三つの部分からできています。 大きくて畳の要ともなる畳床、い草でござのように表面を覆っている畳表、縁となる畳縁です。
畳は寿命があるものですが、この三つの部分をメンテナンスしながら長く使っていきます。
中心部となる畳床が一番重要な部分です。
中心部さえしっかりしていれば、周りのござ部分を定期的に張替えながら使っていけば、10年以上はもちます。
昔はわらから作られた物が主流でしたが、現代では軽くて断熱性に優れた健在床なども多く使用されています。
畳表はメンテナンスに大切な部分です。
表が傷んできたら裏返して再利用することができ、裏がまた傷んできたら、新しい物へと張替えることで、畳をリニューアルすることができます。
いわば部屋の顔とも言うべき部分で、定期的に張替えて部屋をリフォームすることができます。
縁となる部分は柄や色、デザインを始め、素材も様々な物があります。
裏返し、表替えなどのメンテナンス時には新しい物への交換が必要となり、その都度選ぶことが可能です。
また、最近では縁のない物も人気が高まっていて、洋風の部屋に和を取り入れるのに使用されています。
この三つの部分を傷みの状態に応じて、専門の業者に頼んでメンテナンスを行ってもらいます。
近くに専門業者がないという方でも、インターネットで探すと簡単に見つけることができるので、必要に応じて利用するのがおすすめです。
襖張替えでお部屋をリフレッシュ
家の中を模様替えして気分をリフレッシュさせたいというときにおすすめすることができるのが襖の張替えです。和室などにある襖の張替えをしてみることで、家の中を全く新しい雰囲気にすることもできることも多いです。
和室の襖を張り替えて模様替えをすれば、その和室の空間がそれまで持っていたイメージを根本から変えるような空間に仕上げることもできます。襖の張替え一つだけでもイメージを大きく変えられるのは襖の存在が大きいからです。
襖の張替えを行う場合には自分の好みの柄に張り替えることによって、より和室の空間を自分好みの空間に変えることもできます。張替えをすることができるような紙も最近ではさまざまな種類のものがあるので選ぶ楽しみがあります。
襖の張替えをして家の中をリフレッシュするときに欠かせないことがプロの張り替え会社に依頼をすることです。プロの張り替え会社ならば部屋の雰囲気を壊すことなく、しっかりとした張り替えをしてもらえるので重宝します。
襖の張り替えをして家の中をリフレッシュすれば、新しいことにチャレンジするという気持ちが湧き上がることもあります。襖の張替え一つでも人生をより豊かに過ごすことができるヒントが多く隠されていることもあります。
| 無料お見積りはこちら |
御坊市は、和歌山県中央部に位置して人口25千人、総面積43.93km2の市。和歌山県紀中・日高地域の中核都市である。和歌山県の海岸線のほぼ中央部にあり、日高川の河口がある。 南北に長い地形で、紀伊水道に面した部分はほぼ平坦であるが、市の東側は山地になっているところもある。黒潮の影響で年間を通じて温暖多雨で、冬も霜が降りることはほとんどない。
市の開発は古い、遠く先土器時代から人々が住みつき天田遺跡、野島遺跡からは当時の遺物が多く出土しており、古墳も県下では和歌山市に次いで多くあり広範囲に渡って分布していて全部で50基を越える。そのほとんどは6・7世紀頃に地方の小豪族が盛んに活躍していたことが分かる。さらに中世では、有田・日高地方の領主湯川氏が亀山城を構え天正14年(1586)豊臣秀吉に滅ぼされるまで、12代140余年にわたって居城とした。その後近世になって文禄4年(1595)紀伊浅野家の家臣佐竹伊賀守が、この地に西本願寺の日高別院を移築した時からである。ちなみに御坊の地名の由来は、日高御坊の門前町として発展したことによる。市域は日高川河口周辺に広がり、南北に細長い峡小な形をなしている。面積はそう広くはないが県下第2の平野部である御坊平野がその大半を占める。また地勢をみると南西部の海岸地帯に発達した段丘が特徴的で、河口港として発展したところである。日高郡の中心的な存在であるところから、群の代官所も置かれていた。背後には広大な日高材の産地を控え、伝統的な製材業・木工業が今も盛んで、全国生産の40%を占める麻雀牌、90%を占めるサイコロなどの製造工場もある。農業では御坊平野が肥沃な穀倉地帯で稲・麦を中心にすいか・レタス・キュウリなどを栽培している。
(亀山城)
御坊駅の北東間近に、標高130mほどの亀山と言う山がある。湯川氏の居城跡で、永享11年(1439)頃、甲斐源氏の流れをくむ紀伊武田氏の一族湯川光春が、ここに亀山城を築いた。以後この城は湯川氏の本城として、12代直春は日高別院んも創建者として知られが、畠山氏の請に応じて、河内飯盛城の軍と戦って討死した。次の12代直春は、天正13年(1585)太田城を水攻めで落とした豊臣秀吉の軍勢に水陸から攻撃され、自ら亀山城に火をはなち、芳養泊城に逃れた。その後も熊野を根拠地として、紀州平定をもくろむ秀吉に激しく抵抗。秀吉が翌14年2月、本領安寧を約束して講和を求めてきたことにより、両者は和解した。しかし、大和郡山城に居た秀吉の弟の秀長を訪ねた時、謀略にあって毒殺され、ここに湯川氏の時代も終わりをつげた。城跡は、前方に紀伊水道と日高川、四周に御坊平野を一望に収める景勝の地である。当時、城は本丸、二の丸をはじめ大小28郭を構え、本丸の大きさは東西約80m、南北40mを占め、四方に2・3mの土塁をめぐらせていたと言う。現在は、城の遺構としてわずかに土塁の一部と古井戸を残すのみである。