
和歌山県田辺市スピーディーに対応します!!



|
 |
 |
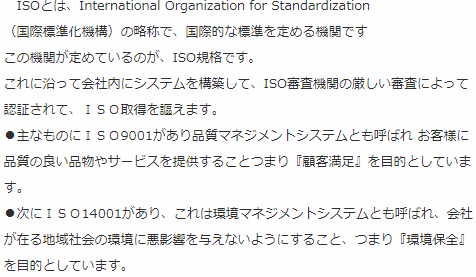
  |

|
 |
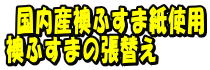
|
![障子の張替えご成約のお客様 国産上質紙[厚口]にお値段そのままで 只今グレードアップキャンペーン中!!](logo_syo1.gif)
 |
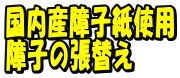
|
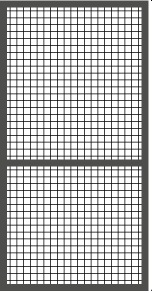 |
|
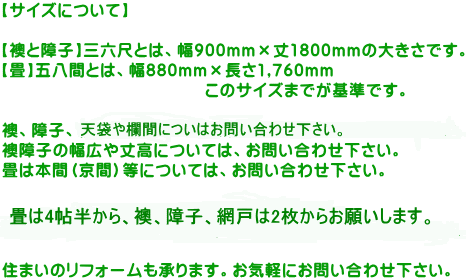
| 無料お見積りはこちら |
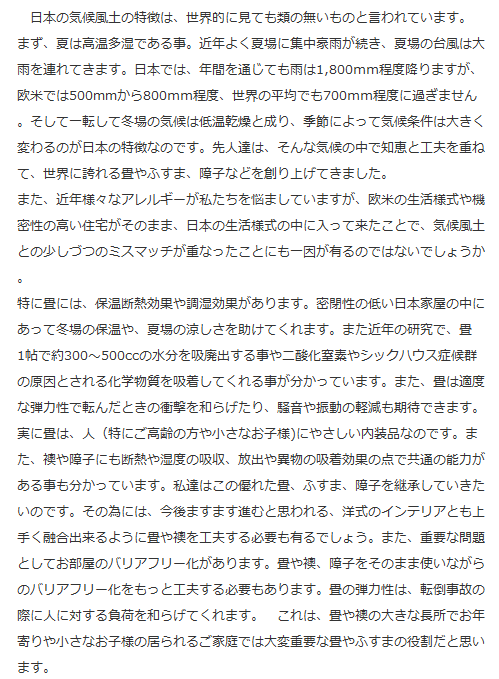
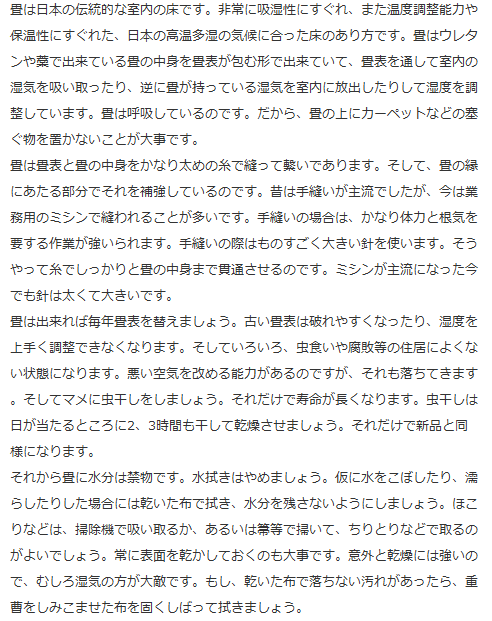
襖は和室には必ずあるものです。襖の柄や色によって、部屋の雰囲気はがらりと変わります。和室にあった落ち着いたものが多いのですが、それでもトレンドというものがあるので、それに合わせて張り替える人もいるということです。
襖や障子は自分でも張り替えることができるので、数年に一度、もしくは年に一度だけ張り替える、という人もいます。自分で張り替えるときには、まずはじめに必要なものをきちんとそろえておいた方が張り替えるときにはとても楽です。
襖紙には水をつけて貼るタイプのものの他に、アイロンで貼るタイプのもの、粘着ふすま紙というものがあります。自分で張り替える人は水をつけて貼るタイプのものを選択する人が多いです。用意するのは洗面器や竹べら、カッターなどがあります。
襖は障子と違って、枠をはめて作っているものなので、まずは上下の枠をはずします。そして左右の枠をはずして、引き手金具をはずします。そこから順に襖紙の古いものをはがして、破れているだけの場合は補修紙で補修をします。
襖紙をはるときに気になるのは丸めてある紙がまっすぐになるかどうかです。巻ぐせがついているので貼るときには襖よりも少し大きめにはって、余ったところを裁断するといいということです。きちんと水平になっているところで行うようにします。
| 無料お見積りはこちら |
熊野速玉大社は神宮駅の北西約1キロメートル、市街北端を流れる熊野川の近くにある。熊野三山の一社で、一名、熊野神宮。また昔は熊野権現とも称し、昭和21年の制度改革の際、正式名を熊野速玉神社大社と改めた。当社の創建年代は明らかではないが、熊野権現垂迹縁起書によれば、神代、熊野速玉大神・夫須美大神・家津美御子大神の熊野神が、各自遍歴の後、紀州の神蔵峯に天降って鎮座された。ついで阿須賀社北の石淵に移られ、その後ここか家津美御子だけが熊野川上流の本宮に降臨されたという。また、当社は景行天皇の代に、現社地に新しく社殿を造営して、阿須賀社から結御子速玉之男神を観請されたと伝えている。これが熊野速玉大社の草創といわれ、新宮の名の起源とも言う。隔絶した地理的条件も手伝って、当社が中央に知られるようになったのは、かなり遅く、新抄格符抄に天平神護2年神封4戸を充てられたとあるのが記録の初見である。しかしその後、朝野の崇敬を受けて急速に発展し、延喜7年従一位、天慶3年正一位に昇叙され、延喜の制では明神大社に列した。平安から江戸時代にかけての社運は、室町・戦国の一時期を除いて、いわゆる、熊野詣でにぎわい、その繁栄ぶり目覚しいものであった。ことに平安時代は法皇・上皇を始めとする貴族の三詣が続き、鎌倉時代に入るとそれに武士層も加わった。一遍上人・文覚上人の参詣も有名である。その後、室町・戦国時代は、下剋上の世にあ武士層の檀那を失い、また熊野に本拠おいて回国した修験者が地方に定着したことなどから、一時衰退の様相を示した。が、江戸時代に入ると庶民層も加わって再び盛んになり、蟻の熊野詣、と言われるほどの盛況を見せた。社殿の造営も用明天皇即位2年から天保7年徳川家定の前後20回に及ぶが、明治16年の大火災で神輿庫・宝蔵を残して、社頭のほとんどを焼失した。現在の社殿は同27年以降の再建で、近年鉄筋コンクリート造りの社殿も新築された。社殿配置は旧熊と多少変わっているが、約50万平方メートルの広大な地域を占め、丹塗りも鮮やかな壮麗な社殿が建ち並んでいる。まず、参道を進むと右手に見えるのが、神宝館。その前面にはナギの巨木が古い社歴を物語るかのようにそびえている。さらに進み人門をくぐると、正面に3つの鈴門をもった、神明造りの社殿1棟が建つ。ここは左から第一殿を結宮、中央台三殿を証誠殿、右第四殿を若宮と呼び3神を1社殿に祀っている。